
社宅と家賃補助の違いとは? それぞれのメリット・デメリットを比較
企業が導入する法定外福利厚生には、社宅や家賃補助といった住宅に関する制度があります。住宅に関するサポートを行うことで、従業員が安定した生活基盤を整えやすくなるほか、引越しを伴う入社・転勤をスムーズに進められます。
人事総務部門のご担当者さまのなかには、法定外福利厚生の充実化に向けて「社宅と家賃補助の違いを改めて理解したい」「従業員にとって喜ばれる制度を選びたい」とお考えの方もいるのではないでしょうか。
この記事では、社宅と家賃補助の違いやそれぞれのメリット・デメリットについて解説します。
→【おすすめ!】記事と合わせて読みたい「社宅制度と住宅手当のメリット・デメリット」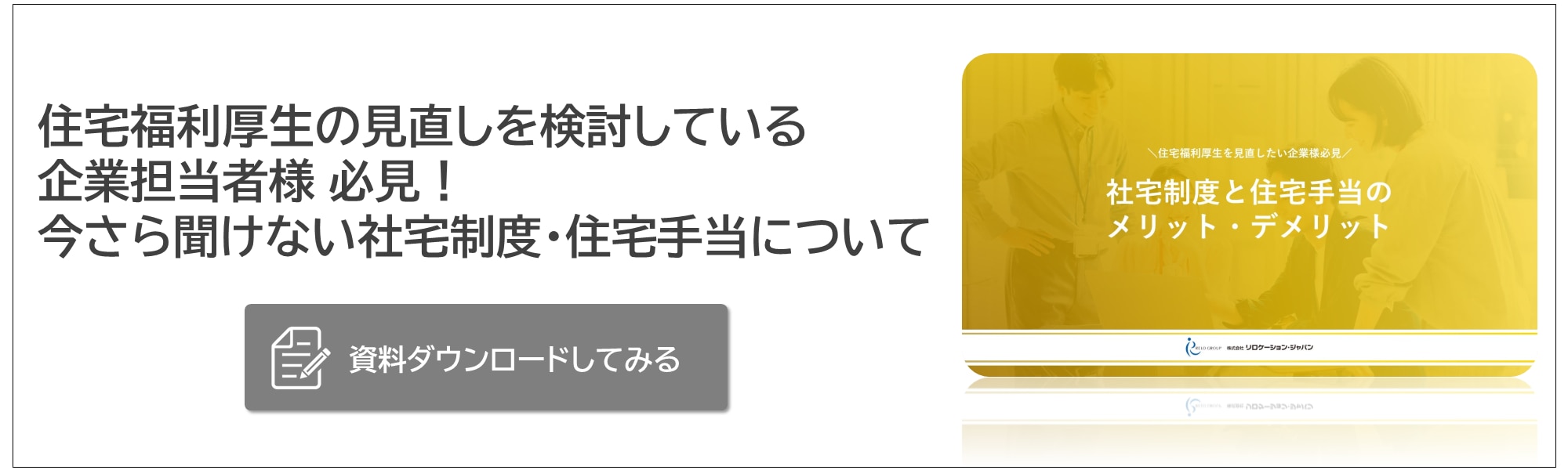
社宅と家賃補助の違い
社宅は、企業が所有または借り上げた物件を従業員に貸し出して、給与から一定の使用料を徴収する制度です。
これに対して家賃補助は、従業員が個人で契約している賃貸住宅の家賃を企業が一部補助する制度です。どちらも法定外福利厚生の一種ですが、支給するものや税金(所得税)の扱い、賃貸住宅の借主に違いがあります。
▼社宅と家賃補助の違い
社宅 | 家賃補助 | |
支給するもの | 住宅 | 現金 |
税金の扱い | 非課税となる | 給与として課税される |
賃貸借契約の名義 | 企業(借上社宅の場合) | 従業員 |
社宅を貸与する場合には、一定割合以上の使用料を従業員から徴収していれば給与として課税されません。家賃補助を支給する場合は、手当の金額にかかわらず給与として課税対象となります。
なお、福利厚生における社宅の位置づけについてはこちらの記事で解説しています。併せてご確認ください。
出典:国税庁『No.2597 使用人に社宅や寮などを貸したとき』
社宅のメリット・デメリット
社宅を貸与する場合のメリット・デメリットは、以下が挙げられます。
▼社宅のメリット
メリット | |
企業側 |
|
従業員側 |
|
▼社宅のデメリット
デメリット | |
企業側 |
|
従業員側 |
|
※賃貸物件の居住・使用によって発生した損耗や破損などを復旧する工事のこと
社宅では、従業員自身で賃貸住宅を契約する必要がないため、遠方からの入社や転勤をする従業員がスムーズに生活環境を整えられます。また、社員寮の場合には入居者同士のつながりが生まれるほか、手当が給与として課税されないことも従業員に喜ばれる理由の一つです。
ただし、企業が保有する物件を貸与する場合は、共用部分の清掃や設備の修繕・メンテナンス、退去後のハウスクリーニングなどを自社で対応する必要があり、労力・費用の負担がかかります。
賃貸住宅を借り上げる場合にも、不動産管理会社との契約・解約手続き、家賃の支払いといったさまざまな業務が発生するため、人事総務部門の負担が増加します。自社のみで運用管理が難しい場合には、外部のサポート会社に外注することも一つの方法です。
なお、社宅を導入するメリットについてはこちらの記事でも詳しく解説しています。併せてご確認ください。
→【詳しく知りたい!】『リロの社宅管理』を導入・利用企業様の事例はこちら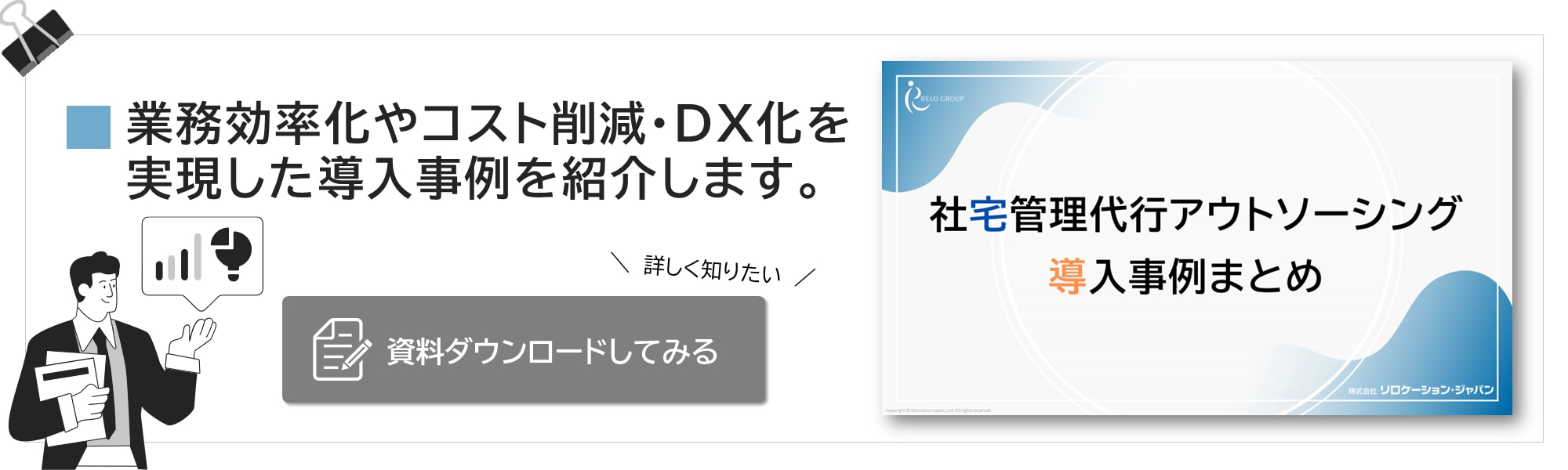
家賃補助のメリット・デメリット
家賃補助を導入するメリット・デメリットは、以下のとおりです。
▼家賃補助のメリット
メリット | |
企業側 |
|
従業員側 |
|
▼家賃補助のデメリット
デメリット | |
企業側 |
|
従業員側 |
|
家賃補助では、自社で物件を購入または借り上げる必要がありません。そのため、土地購入や建築費、敷金・礼金などの初期費用がかからないほか、物件の維持管理、賃貸借契約の手続きの負担も抑えられます。
また、給与に上乗せして手当を支給する仕組みとなることから、従業員が住みたい物件を自由に選べるというメリットもあります。
ただし、家賃補助の手当は給与として課税対象となります。企業と従業員が折半で負担する社会保険料の額が増加する可能性がある点には注意が必要です。
さらに、家賃補助を支給する従業員は、会社の近くにある賃貸住宅に住む人を対象とすることが一般的です。そのため、持ち家で暮らす従業員や、遠方でテレワークをする従業員などから不満を招く可能性もあります。
従業員の生活スタイル・就業形態・家族構成などを踏まえて、ニーズに対応できる規定を作成することが求められます。
まとめ
この記事では、社宅と家賃補助について以下の内容を解説しました。
- 社宅と家賃補助の違い
- 社宅のメリット・デメリット
- 家賃補助のメリット・デメリット
社宅と家賃補助は、従業員の住宅に関する経済的な負担を抑えて、安定した生活基盤を整えるために役立つ福利厚生です。
ただし、税金の扱いや物件の契約手続き、運用管理にかかる負担などが変わるため、企業の運用体制、従業員のニーズなどを踏まえて自社に合った制度を導入することが重要です。
『リロケーション・ジャパン』では、転貸方式による借上社宅のフルアウトソーシングや社有社宅の運用代行を承っております。社宅の運用管理を行う負担を削減して、従業員に喜ばれる福利厚生を導入できます。
詳しくは、こちらをご確認ください。





