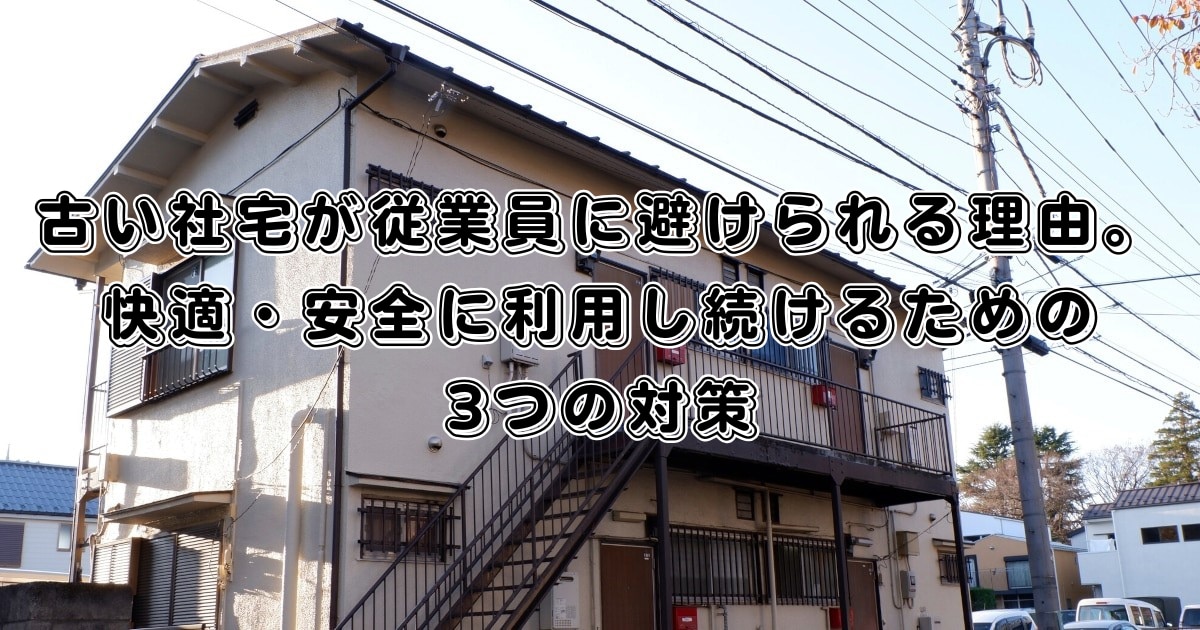
古い社宅が従業員に避けられる理由。快適・安全に利用し続けるための3つの対策
社有社宅を長年運用していると、経年劣化によって部屋の設備や建具などが古くなります。古い社宅は、見た目や使い勝手が現代のライフスタイルと合わなくなったり、設備の故障・不具合が発生したりする可能性があり、従業員から避けられる場合もあります。
人事総務部門のご担当者さまのなかには、「古くなった社宅はなぜ避けられるのか」「社宅を快適かつ安全に使用し続ける方法はないか」などと対応を検討されている方もいるのではないでしょうか。
この記事では、古い社宅が避けられる理由や快適・安全に使用し続けるための対策について解説します。
→【おすすめ!】社宅だけじゃない!?社有社宅・寮管理の煩雑業務もまるっと解決!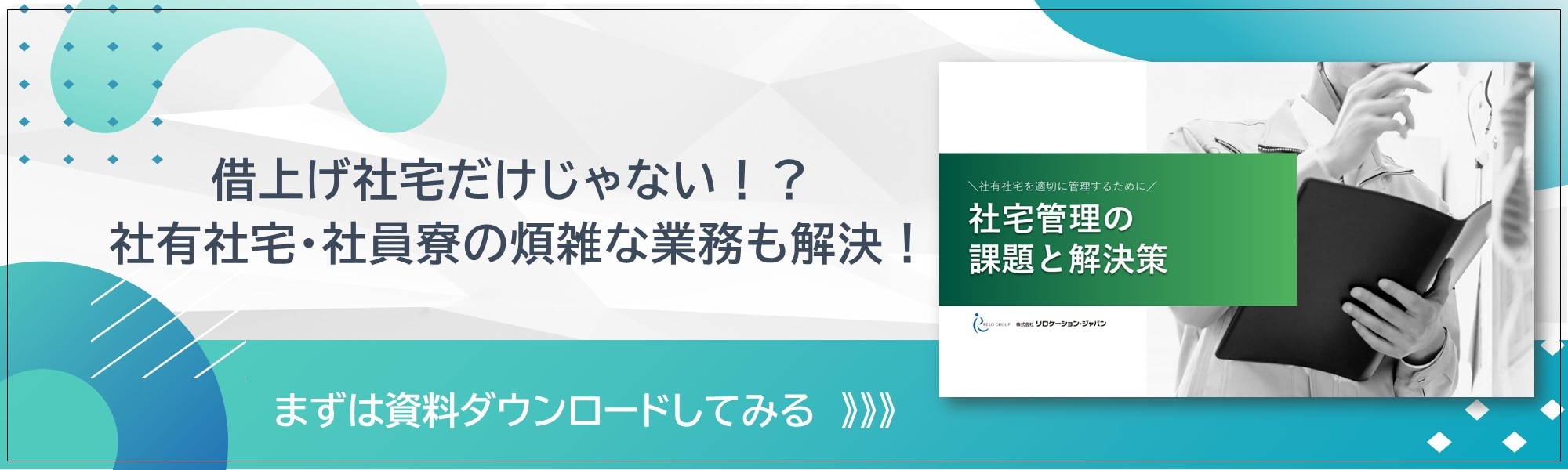
目次[非表示]
古い社宅が避けられる理由
社宅制度を運用していても、築年数がたって設備や建具が古くなっている状態では、従業員に入居を避けられてしまうことがあります。古い社宅が従業員から避けられる理由には、以下が考えられます。
現代のライフスタイルに合わない
古い社宅では、物件の間取りや設備が現代のライフスタイルに合っていない場合があります。現代のライフスタイルに合わない社宅は、生活のストレスや不満につながることから、入居を避ける従業員もいます。
▼現代のライフスタイルに合わない社宅の例
- キッチンやトイレなどの水回り設備が古い
- リビングとダイニングの空間が分離している
- 和室中心で洋室がない
- 室内に洗濯機置き場がない など
ただし、従業員のなかにはライフスタイルよりも住居費の節約を重視する人もいます。取得してから数年経った社有社宅の場合、減価償却期間が終了して会社側が負担する必要が少なくなったことで、従業員から徴収する社宅使用料を安く設定しているケースもあります。
また、社有社宅には単身向けと世帯向けの物件があり、それぞれ住居に求める条件は異なります。家族構成を考慮した間取りであれば、入居希望者が現れる可能性があります。
害虫やカビが発生しやすい
古い社宅では、害虫やカビが発生しやすくなり、健康面への影響につながったり、住みづらさを感じたりすることがあります。
築年数がたった物件は、外壁や配管などの劣化によって小さな隙間ができやすくなり、害虫が侵入しやすくなります。また、結露や雨漏りなどによってカビが発生することも考えられます。
害虫やカビが発生している場合には、対策を講じて入居者が住みやすい環境へと改善を図ることが必要です。
耐震性に不安がある
築年数が古い社宅の場合、耐震性を不安に感じて入居をためらうケースもあると考えられます。
建築基準法が改正された1981年以前に建てられた建築物は、現在の新耐震基準を満たしておらず、耐震補強工事が行われていない場合があります。
実際に阪神・淡路大震災や新潟県中越地方地震などの過去に発生した大地震では、新耐震基準を満たしていない建築物に被害が集中していることが報告されています。新耐震基準の施行以前に建築された物件の場合には、耐震化が求められます。
なお、従業員が「社宅に住みたくない」と思う原因についてはこちらの記事で解説しています。併せてご確認ください。
出典:国土交通省『Ⅰ 住宅・建築物の耐震化に関する現状と課題』
古い社宅を快適・安全に利用し続けるための対策
古くなった社宅を利用してもらうには、従業員が快適かつ安全に過ごせる住環境を整えることが必要です。企業が行える対策には、以下が挙げられます。
①リフォームやリノベーションを行う
設備や建具が老朽化していたり、間取りが現在のライフスタイルに合わなかったりする場合には、リフォームやリノベーションを実施する方法があります。
見た目がきれいになるとともに住みやすい部屋に改修することで、入居希望者が増えると期待できます。
▼リフォームやリノベーションの実施例
- 2DKから1LDKに間取りを変更する
- 和室を洋室にする
- キッチンやトイレ、浴室を最新の設備に入れ替える
- 老朽化したフローリングや畳、壁紙を貼り替える など
また、共用部にワークスペースやトレーニングジムなどの共用施設を新たに設けると社宅の付加価値創出につながり、従業員満足度、企業イメージの向上にも結びつくと考えられます。
なお、社有社宅のリフォームやリノベーションについてはこちらの記事をご確認ください。
②防虫・防カビ対策を行う
全面的なリフォーム・リノベーションが難しい場合でも、防虫・防カビの対策を行うことで快適性の向上につながることが期待できます。
▼防虫・防カビ対策の一例
- 木材保護塗料を塗る
- 防虫・防カビ効果がある断熱材を入れる
- 床下工事を行う
- ハウスクリーニングを実施して汚れやカビを除去する
- 水回り設備や空調、天井・壁・窓などに防カビ加工を行う など
③BCP拠点として整備する
社宅にBCP(事業継続計画)の拠点としての機能を持たせて活用することも一つの方法です。BCPとは、自然災害やパンデミックなどの非常事態が発生した際に事業の継続と復旧を行うための対策・対応を定めた計画のことです。
非常事態が発生した際に、社宅を避難場所または業務継続の拠点として利用できるように整備しておく必要があります。
▼BCP拠点として活用するための対策
- 社宅内で業務を行えるようにITインフラを整備する
- 帰宅できない従業員が宿泊するための寝具や生活用品を備える
- 防災グッズや非常食を備蓄する など
なお、BCPを策定・運用する流れについてはこちらの記事で解説しています。
→【おすすめ!】借上げ社宅管理の業務改善方法とは?詳しく知りたい。
借上社宅に切り替えることも一つの方法
社有社宅が老朽化して利用する従業員が見つからない場合は、社有社宅を廃止して借上社宅に切り替えることも選択肢の一つです。借上社宅は、企業が賃貸借契約を交わした物件を従業員に貸し出す制度です。
▼借上社宅のメリット・デメリット
詳細 | |
メリット |
|
デメリット |
|
人事総務部門が借上社宅を運用する際の業務負担を軽減するには、外部の事業者に委託する方法もあります。
なお、社有社宅と借上社宅の違いについてはこちらの記事をご確認ください。
まとめ
この記事では、古い社宅について以下の内容を解説しました。
- 古い社宅が避けられる理由
- 古い社宅を利用し続けるための対策
- 借上社宅に切り替えるメリット・デメリット
社宅は住居費を抑えられる制度ですが、従業員によって「住居費を節約したい」「住み心地やライフスタイルを重視したい」といった希望は異なります。
特に住み心地やライフスタイルを重視する従業員の場合、古い社宅は間取り・設備への不満、快適性・耐震性への不安などから避けられることがあります。
社宅を利用してもらうには、リフォームやリノベーション、防虫・防カビ対策、BCP拠点としての整備などを行い、従業員が快適かつ安全に過ごせる住環境を整えることが求められます。
また、入居希望者が見つからない場合や、建物の維持管理にかかる費用が負担となっている場合には、借上社宅へ切り替えることも一つの方法です。
『リロケーション・ジャパン』の社宅管理サービスでは、包括転貸方式による借上社宅のフルアウトソーシングに対応しています。社宅管理に関する社内業務を削減しながら、従業員に喜ばれる社宅の運用を実現いたします。
詳しい内容は、こちらの資料をご確認ください。





