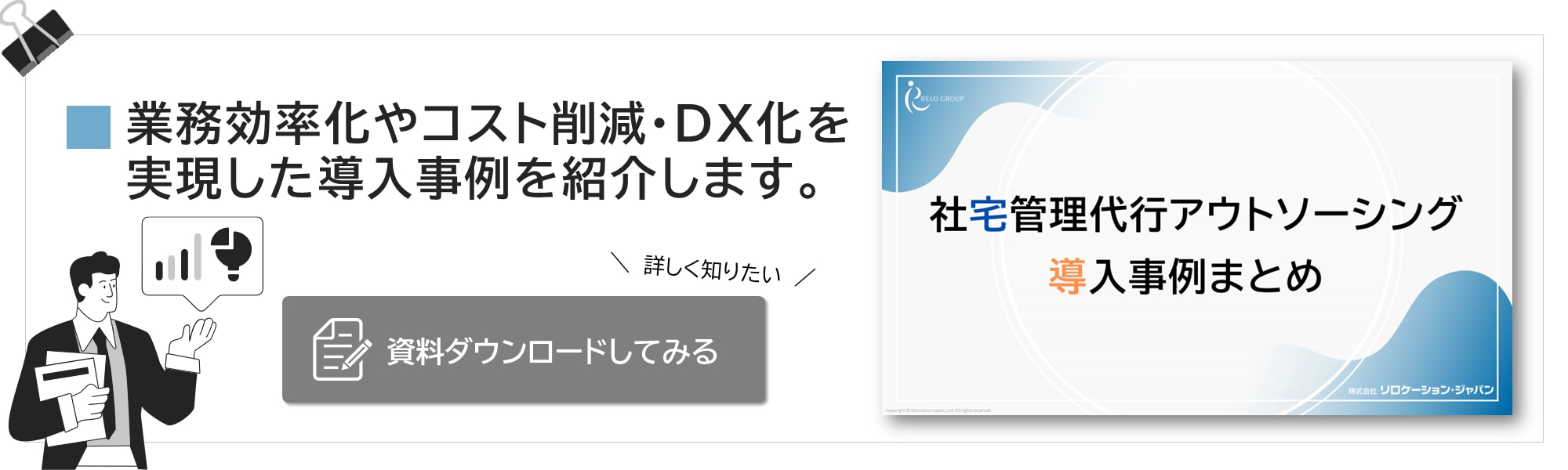定期借家契約の注意点。物件を社宅として借りる際に確認しておくポイント
企業が物件を借りる際は、物件の賃貸人と賃貸借契約を締結します。賃貸借契約における契約形態の一つに“定期借家契約”があり、従来の普通借家契約とは更新の有無や契約方法などが異なるため、仕組みを理解しておく必要があります。
人事総務部門のご担当者さまのなかには「定期借家契約はどのような契約形態なのか」「企業が物件を借りる際に気をつけることはあるか」など気になる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
この記事では、定期借家契約の仕組みや契約を締結する流れ、企業が社宅として物件を借りる際の注意点について解説します。
→【気になる!】借上げ社宅管理の業務改善方法とは?詳しく知りたい。 
目次[非表示]
定期借家契約とは
定期借家契約(ていきしゃっかけいやく)とは、契約で定めた期間が満了すると更新されることがなく、確定的に賃貸借契約が終了する契約を指します。
一般的な普通借家契約の場合では、期間に定めがない契約とみなされ、賃貸人による正当な事由がなければ賃借人の希望に応じて更新することが可能です。これに対して定期借家契約は、期間の満了によって契約が終了します。
▼定期借家契約と普通借家契約の比較
定期借家契約 | 普通借家契約 | |
契約方法 | 公正証書等の書面による契約に限る | 書面や口頭による契約が可能 |
更新の有無 | 更新がない | 正当事由がない限り更新 |
1年未満とする賃貸借の効力 | 1年未満の契約も有効 | 期間に定めがない賃貸借とみなされる |
契約期間が決まっている定期借家契約は、いつまで入居するか期間が決まっていない人や1年以上の長期入居を予定している人にとっては退去のリスクがあります。
一方で、1年未満の転勤や中長期出張、転勤時の仮住まいのように、短期間だけ社宅として利用したい場合には有効活用することが可能です。定期借家契約の賃貸物件は、通常よりも家賃が安く設定されていることや、同じ家賃でも築浅物件や設備の充実した物件に住むことができるといったメリットもあります。
定期借家契約と普通借家契約の違いについては、こちらで詳しく解説しています。
出典:国土交通省『定期借家制度をご存じですか・・・?』
定期借家契約の締結から終了までの流れ
定期借家契約で社宅物件を借りる際は、書面によって契約書を取り交わすことが必須とされています。
▼契約締結から終了までの流れ
流れ | |
契約締結まで |
|
契約成立から終了まで |
|
定期借家契約の締結前に、賃貸人から「賃貸借の更新がなく、期間の満了により終了する」ことが記載された文書が契約書とは別に交付され、事前説明を受けます。
賃貸人が不動産会社に契約の仲介を依頼している場合には、宅地建物取引士による重要事項説明(※)を行う際に同時に事前説明を受ける場合もあります。
また、契約期間が1年以上の場合には、期間満了の1年~6ヶ月前までの間に「期間満了により賃貸借契約が終了する」ことが賃貸人から通知されます。ここで再契約の合意がなければ、期間満了後に退去が必要です。
※宅地建物取引業法第35条に基づいて、宅地建物取引士が契約に関する重要事項の読み上げと書面の交付を行うこと。
出典:e-Gov法令検索『宅地建物取引業法』/国土交通省『定期借家制度をご存じですか・・・?』
→【おすすめ!】記事と合わせて読みたい「原状回復の基本知識と課題解決のポイント」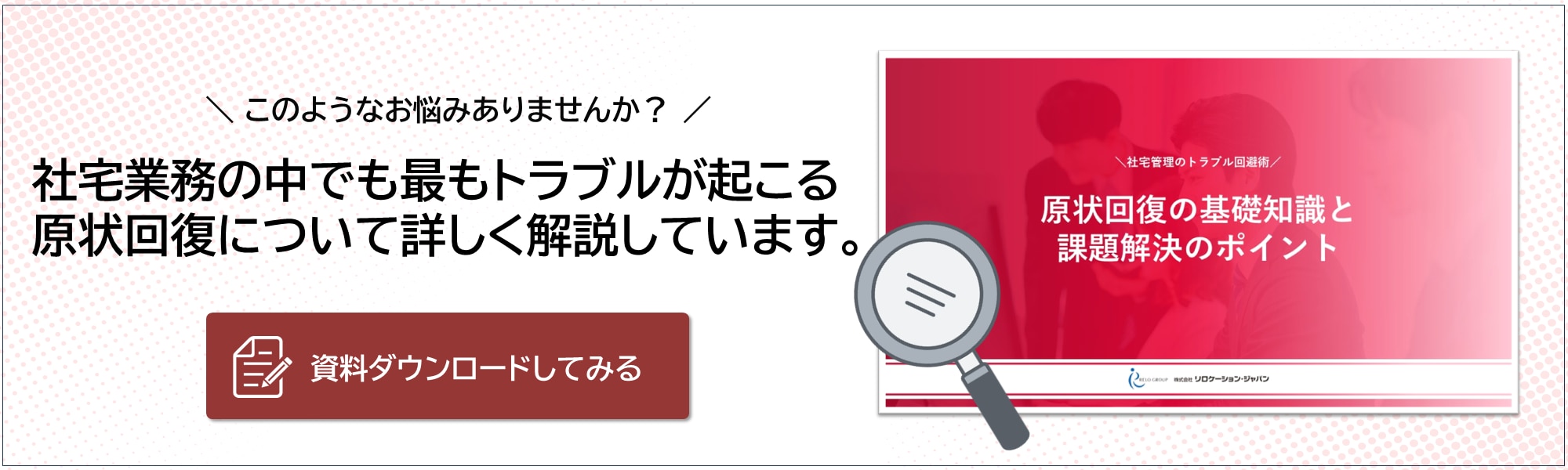
定期借家契約で社宅物件を借りる際の注意点
定期借家契約で社宅物件を借りる際は、中途解約や再契約の可否、特約事項などについて注意が必要です。
➀原則として中途解約はできない
あらかじめ契約期間が定められている定期借家契約では、原則として中途解約は認められていません。ただし、以下に該当する場合には、賃借人が中途解約の申し入れを行うことが可能です。
▼中途解約の申し入れが認められる条件
- 床面積が200㎡未満となる居住用の建物
- 賃借人が転勤・療養・介護などのやむを得ない事情により、その物件での入居が困難となった
中途解約の申し入れが認められる場合には、申し入れの日から1ヶ月が経過した日に賃貸借契約が終了となります。
ただし、中途解約に関する特約事項が定められている場合はその定めが適用されるため、事前に契約内容を確認しておくことが必要です。
定期借家契約の中途解約について、詳しくはこちらの記事をご確認ください。
出典:国土交通省『定期借家制度をご存じですか・・・?』『定期建物賃貸借 Q&A』
②再契約には双方の合意が必要になる
定期借家契約は、期間が満了すると更新はありませんが、賃貸人・賃借人の双方が合意している場合に限り、再契約することができます。引き続き入居を希望する場合には、賃貸人との交渉を行い合意を得る必要があります。
また、再契約する際には、最初の契約と異なる内容が定められる場合もあるため、事前説明の文書や契約書をよく確認することが欠かせません。
▼再契約時のポイント
- 最初の契約内容と変更点はないか賃貸人に確認する
- 最初の契約と同様に事前文書の交付と説明を受ける
- 敷金の精算は最終的な退去時に行う
出典:国土交通省『定期借家制度をご存じですか・・・?』『定期建物賃貸借 Q&A』
④賃料増減請求権の特約が定められている場合がある
賃料増減請求権とは、土地や建物の借家契約において当事者がもう一方に家賃(または地代)の改定を請求できる権利を指します。
定期借家契約であっても賃貸人による家賃の増減請求ができると定められている可能性があるため、注意が必要です。また、賃借人から賃貸人に対する家賃の減額請求を認めない特約が定められていることもあります。
出典:国土交通省『定期借家制度をご存じですか・・・?』『第2部 継続賃料にかかる鑑定評価の方法等の検討』
まとめ
この記事では、定期借家契約について以下の内容を解説しました。
- 定期借家契約の概要
- 定期借家契約を締結する流れ
- 定期借家契約の物件を社宅として借りる際の注意点
定期借家契約ではあらかじめ入居できる期間が決まっているため、1年未満の転勤や長期出張、転勤時に住居が決まるまでの仮住まいとして活用することが可能です。
ただし、物件によって契約期間や更新の可否などが異なるため、社宅の入居期間と合致しない場合には、普通借家契約での契約を検討する必要があります。
また、定期借家契約を締結する際は、普通借家契約と手続きの流れが異なるほか、中途解約や再契約の可否、特約事項などについて注意が必要です。
『リロケーション・ジャパン』では、転貸方式による借上社宅のフルアウトソーシングを行っております。物件探しから賃貸借契約の手続き、解約まで幅広い業務に対応しており、社宅管理の工数削減に貢献します。
詳しくは、こちらをご確認ください。