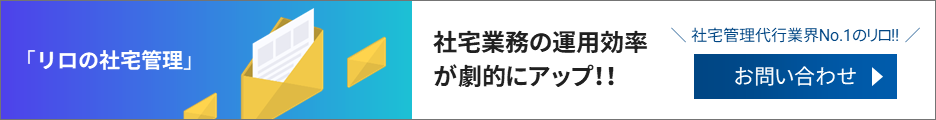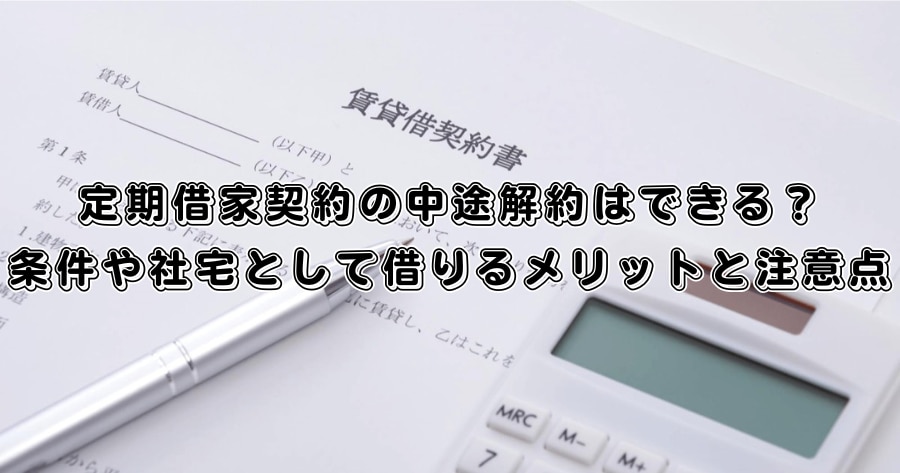
定期借家契約の中途解約はできる? 条件や社宅として借りるメリットと注意点
※2025年2月18日更新
賃貸物件の契約形態の一つに、あらかじめ契約期間が定められている“定期借家契約”があります。定期借家契約は、契約期間が満了した際に更新されることなく、確定的に賃貸借契約が終了する仕組みです。
定期借家契約の賃貸物件を借上住宅として利用する場合、「急な転勤が決まった」「契約期間中に従業員が退職した」などの理由で、契約期間の途中で解約が必要になるケースも想定されます。社宅担当者のなかには、定期借家契約の中途解約ができるか気になる方もいるのではないでしょうか。
本記事では、定期借家契約の概要や中途解約の原則、社宅として借りるメリット、注意点について解説します。
→【おすすめ!】借上げ社宅管理の業務改善方法とは?詳しく知りたい。
目次[非表示]
定期借家契約とは
定期借家契約とは、契約時にあらかじめ契約の期間が定められている賃貸借契約のことです。契約期間が満了すると、原則として契約は終了し、借主は物件を退去することになります。
流通の多い普通借家契約は、借主の権利が非常に強く保護されており原則自動更新となるため、家主からの解約は認められていません。家主から解約する際は、正当事由とあわせて借主との協議が必要になります。
一方で、定期借家契約の場合は自動更新がなく、契約時に契約期間が明確になることが特徴です。
▼普通借家契約と定期借家契約の違い
普通借家契約 | 定期借家契約 |
正当事由と合わせて借主との協議や明け渡し交渉・法的な手続きをしない限り契約は更新される | 期間満了とともに契約が終了する |
なお、一般的な賃貸借契約となる普通借家契約と、定期借家契約の違いについては、こちらの記事で詳しく解説しています。併せてご確認ください。
定期借家契約の中途解約はできる?
定期借家契約は、貸主があらかじめ契約期間を定めている賃貸借契約のため、契約期間中の中途解約は原則的に認められていません。
理由は、借主都合で中途解約すると、残存期間の家賃収入を得られなくなり、貸主側の不利益につながるおそれがあるためです。ただし、一定の条件を満たせば中途解約ができるケースもあります。
出典:国土交通省『定期建物賃貸借 Q&A』
定期借家契約の中途解約が可能となる条件
定期借家契約で賃貸物件を借りた場合、中途解約は原則できませんが、以下のいずれかの条件に当てはまる場合には解約ができることもあります。
①解約権留保特約を定めている
定期借家契約書に借主の解約権留保特約を定めている場合は、契約期間中に中途解約が可能です。
解約権留保特約とは、契約期間中の解約を認める特約を指します。『民法』第617条・618条で以下のように定められています。
▼民法第617条・618条
第六百十七条 当事者が賃貸借の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合においては、次の各号に掲げる賃貸借は、解約の申入れの日からそれぞれ当該各号に定める期間を経過することによって終了する。
一 土地の賃貸借 一年
二 建物の賃貸借 三箇月
三 動産及び貸席の賃貸借 一日
2 収穫の季節がある土地の賃貸借については、その季節の後次の耕作に着手する前に、解約の申入れをしなければならない。
(期間の定めのある賃貸借の解約をする権利の留保)
第六百十八条 当事者が賃貸借の期間を定めた場合であっても、その一方又は双方がその期間内に解約をする権利を留保したときは、前条の規定を準用する。
引用元:e-Gov法令検索『民法』
借主による解約権留保特約がある場合には、貸主に対して解約の申し入れをしたあと、3ヶ月の経過後に契約を終了できるようになります。
出典:e-Gov法令検索『民法』
②中途解約権を行使できる
定期借家契約で解約権留保特約を締結していない場合でも、中途解約権を行使できる条件を満たす場合には、中途解約が認められます。
『借地借家法』第38条第7項では、以下の条件を満たす場合に借主が定期借家契約を解約できることが定められています。
▼中途解約権を行使できる条件(下記3点を満たすこと)
- 住居用の建物
- 床面積が200㎡未満の建物
やむを得ない事情で建物を生活の拠点として使用することが困難になった場合
▼借地借家法第38条第7項
第一項の規定による居住の用に供する建物の賃貸借(床面積(建物の一部分を賃貸借の目的とする場合にあっては、当該一部分の床面積)が二百平方メートル未満の建物に係るものに限る。)において、転勤、療養、親族の介護その他のやむを得ない事情により、建物の賃借人が建物を自己の生活の本拠として使用することが困難となったときは、建物の賃借人は、建物の賃貸借の解約の申入れをすることができる。この場合においては、建物の賃貸借は、解約の申入れの日から一月を経過することによって終了する。
引用元:e-Gov法令検索『借地借家法』
"やむを得ない事情”とは、転勤や療養、親族の介護などが該当します。中途解約権を行使して、定期借家契約における解約の申し入れをした際は、申し入れをした日から1ヶ月経過後に契約を終了することが可能です。
出典:e-Gov法令検索『借地借家法』
③貸主に違約金を支払う
貸主に違約金を支払うことで定期借家契約を中途解約できる場合もあります。
違約金によって中途解約する場合は、定期借家契約で定める残存期間の賃料分を貸主に支払うことが一般的です。例えば、1年の定期借家契約を10ヶ月で解約したい場合、残りの2ヶ月分の賃料を違約金として支払います。
契約時に解約権留保特約を定めておらず、中途解約権を行使できない場合の解約手段です。
なお、こちらの記事では、短期解約による違約金の基本情報や物件の注意点、社宅規程を定める際の注意点について解説しています。併せてご覧ください。
定期借家契約で中途解約を行う際の流れ
定期借家契約を中途解約する場合、まずは契約書を確認して中途解約に関する条項の有無・解約条件・違約金について確認します。もし契約書に中途解約に関する定めがない場合は、借地借家法などの法令に中途解約が認められたケースがないか確認します。
▼中途解約手続きの流れ
- 契約書確認
- 解約通知書作成・送付
- 賃貸人との交渉
- 合意書作成
- 物件明け渡し
- 敷金返還
解約通知の方法や期間については契約書に定められているため、その内容に沿って手続きを進めることが求められます。
ただし、契約書の内容確認や賃貸人との交渉は煩雑になりやすく、場合によっては裁判所への申し立ても必要となります。
定期借家契約を社宅に利用する際には、中途解約のリスクに備えて社宅管理の専門家のサポートを受けることも有効です。法的な知識や交渉経験に基づき、手続きを円滑に進めることができます。
なお、社宅管理業務のアウトソーシングについてはこちらの記事で詳しく解説しています。併せてご確認ください。
定期借家契約の物件を社宅にするメリット
定期借家契約の賃貸物件を社宅として借りるメリットとしては、賃料や契約期間が挙げられます。
▼メリット
- 安い賃料で借りられる可能性がある
- 短期間で契約できる
契約期間が定められている定期借家契約の物件は、入居できる人が限定されるため、借主を見つけやすくするために周辺相場よりも家賃が低く設定されていることがあります。社宅に入居する従業員との条件が合えば、社宅運用にかかるコストを削減できる場合があります。
また、普通借家契約では多くの場合、契約期間が1〜2年で定められています。一方、定期借家契約では、普通借家契約と比較して短期間で借りられる物件もあるため、1年未満の転勤や長期出張など、入居期間と契約期間が合致する場合などに有効です。
なお、一般的な賃貸借契約となる普通借家契約と、定期借家契約の違いについては、こちらの記事で詳しく解説しています。
→面倒な社宅管理業務をまるっとお任せしたい。サービス概要資料はこちら 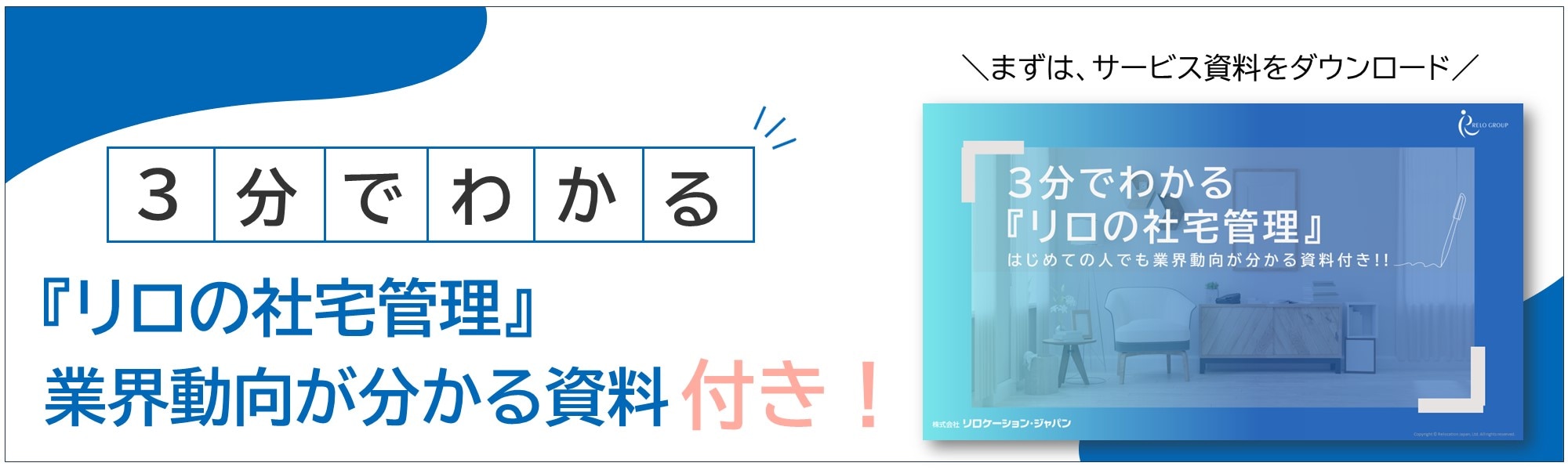
定期借家契約で社宅を借り上げる際の注意点
定期借家契約の物件を社宅として借りる場合には、契約期間満了後の扱いに注意が必要です。
▼定期借家契約による借上社宅の注意点
- 自動更新ではないため、契約期間満了後は退去が必要
- 貸主と借主双方の合意がなければ再契約はできない
契約期間満了後は自動更新されないため、長期利用または退去する時期が未定の利用には不向きといえます。契約期間を超えて使用したい場合は貸主との合意が必要となり、再契約には改めて手続きを行う必要があります。
社宅として利用する場合は、業務の関係で契約当初の予定よりも長い期間物件が必要になることがありますが、その際には柔軟な対応がしにくいと考えられます。
まとめ
この記事では、定期借家契約について以下の内容を解説しました。
- 定期借家契約の概要
- 定期借家契約における中途解約の原則
- 定期借家契約を中途解約できる条件
- 定期借家契約で中途解除を行う際の流れ
- 定期借家契約で社宅を借りるメリット
定期借家契約は、原則として借主による中途解約は認められていません。ただし、場合によっては中途解約の申し入れが可能なケースがあります。
社宅として運用する際は、急な転勤や退職などで中途解約が必要になる場合もあるため、契約時に中途解約の条件を確認しておくことが重要です。ただし、手続きが煩雑になりやすいため、社宅管理の専門家のサポートを受ける方法もあります。
また、定期借家契約の物件は、周辺の物件よりも家賃が安く設定されていたり、短期間で契約ができたりする物件もあるため、社宅の入居期間や立地などに応じて選定することがポイントです。
『リロケーション・ジャパン』の社宅管理サービスでは、貴社のニーズを的確に捉えたコンサルティングを行います。社宅物件の選定や契約形態についてお悩みの方は、ぜひお問い合わせください。
→【おすすめ!】借上げ社宅管理の業務改善方法とは?詳しく知りたい。
社宅管理業務に役立つさまざまな資料をご用意しています。こちらからダウンロードいただけます。