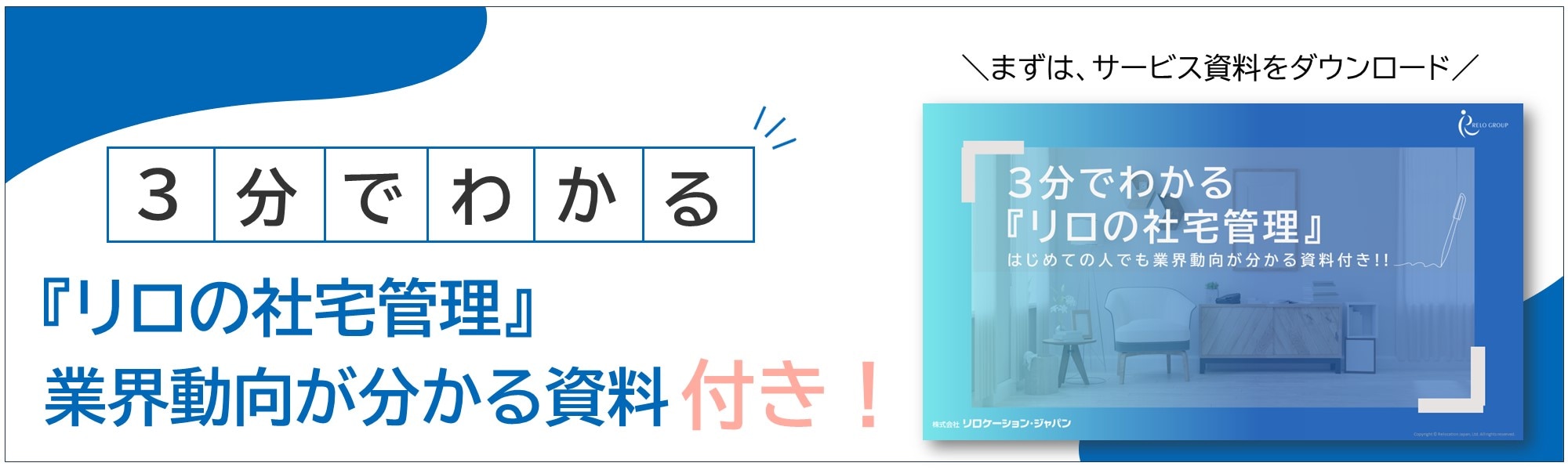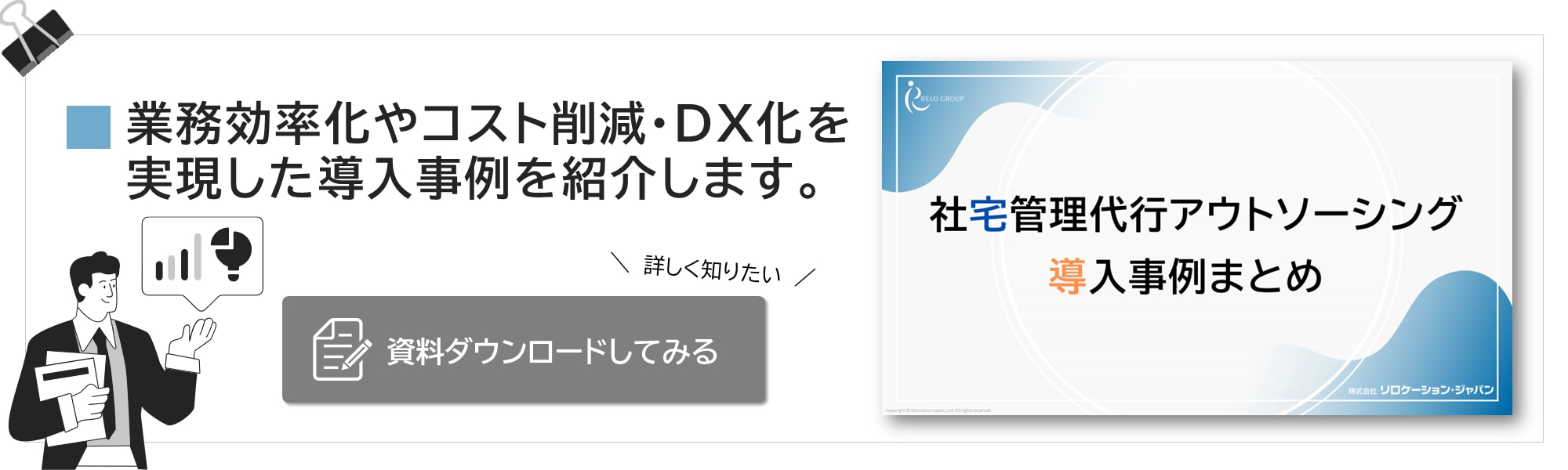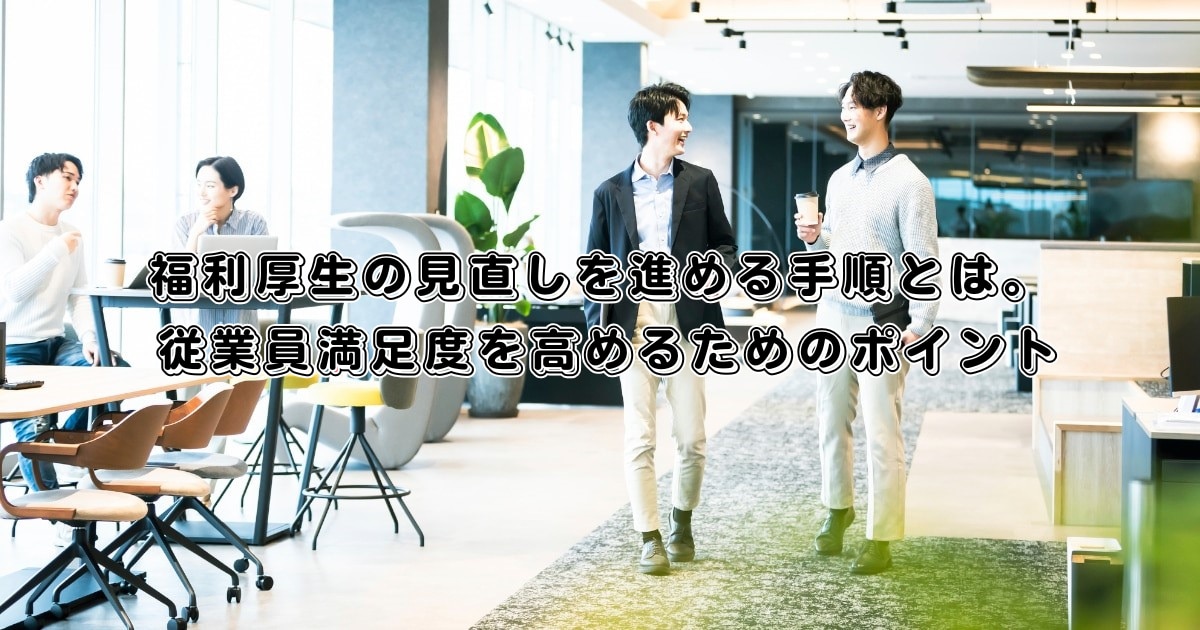
福利厚生の見直しを進める手順とは。 従業員満足度を高めるためのポイント
社会や時代の変化とともに、人々の働き方、仕事に対する価値観などが変化しています。企業が導入している福利厚生においても、働き方やライフステージの変化などによって従業員のニーズを満たせなくなっているかもしれません。
特に近年では、ワークライフバランスの確保や育児・介護との両立、心身の健康づくりなどが企業経営の重要なキーワードとして注目されています。
従業員が安心して働き続けられる魅力的な職場を目指すために、福利厚生の見直しを検討している人事総務部門のご担当者さまもいるのではないでしょうか。
この記事では、福利厚生を見直す理由と目的をはじめ、具体的な実施手順、見直しを行うときに押さえておくポイントについて解説します。
目次[非表示]
→【おすすめ】記事とあわせて読みたい!『リロの社宅管理』サービス概要資料はこちら
福利厚生を見直す理由と目的
福利厚生は、従業員の就業・生活環境を整えるために、本人または家族に対して経済的な支援や生活の質を高めるためのサポートを行う制度です。
従業員が求める福利厚生は、社会や働き方の変化とともに変化します。既存制度の利用率や満足度が低い場合には、従業員のニーズを踏まえて見直しを行うことが必要です。福利厚生の見直しが必要となる主な理由には、以下が挙げられます。
▼福利厚生の見直しが必要となる理由
- テレワークの普及による働き方の変化
- 共働き世代の増加による育児・介護の両立支援ニーズの顕在化
- 少子化に伴う若年人口の減少と人材の流動化による人材獲得競争の激化
- 従業員の健康保持・増進に関する社会的ニーズの高まり など
福利厚生の満足度は、従業員エンゲージメントに直結する重要な要素の一つです。人材の定着化や優秀な人材の採用につなげるためには、福利厚生の見直しを通じて安心して長く働き続けられる職場を目指すことが重要です。
従業員にとって満足度の高い福利厚生へと見直しを行うことは、生産性の向上や組織の活性化、ひいては企業価値の向上にも結びつくと考えられます。
福利厚生の見直しを進める手順
福利厚生を見直す際は、現在の利用状況や問題を明らかにしたうえで、従業員の意見を取り入れて新しい制度を選定する必要があります。
➀現行の制度に対する評価を行う
現行の福利厚生に対する評価を実施します。各制度の利用率や満足度を調査することで、見直しが必要な福利厚生を特定できます。
▼制度に対する評価を行う方法
- 各制度の利用率と運用コストを可視化する
- 従業員アンケートで既存制度の満足度を定量的・定性的に調査する
- 運用コストに対して利用率や満足度が高い・低い制度を整理する
制度の利用率を可視化する際は、従業員の年齢や性別、家族構成などの属性を区分して整理すると、ニーズの分布を把握しやすくなります。
②利用率・満足度が低い原因を分析する
アンケート調査の内容を踏まえて、福利厚生の利用率・満足度が低い原因を分析します。
利用率・満足度が低くなる原因として考えられる問題をアンケートの項目に含めておくと、調査結果の分析がしやすくなります。
▼利用率・満足度が低くなる原因の例
- 制度の存在を知らなかった
- 利用したいが適用条件を満たしていなかった
- 利用したいと思わない(利用する機会がない)
- 申請方法が複雑で面倒に感じる など
③福利厚生の見直し案を策定する
現状の評価と利用率・満足度が低くなる原因を踏まえて、見直し案を策定します。
見直し案を策定する際は、従業員の声を取り入れて「あると嬉しい制度」「既存制度で改善してほしいこと」などのニーズを把握することが重要です。
また、運用のコストや体制面、課税・非課税の区分などを考慮して実現可能性のある施策を考えることも必要です。
▼見直し案の策定例
- 満足度が高く利用率が低い場合は、適用対象とする条件を緩和する
- 利用率・満足度が低い制度を廃止してニーズが高い新制度を導入する など
④見直し案の実行と効果検証を行う
策定した見直し案に基づいて、新しい制度の運用を開始します。運用前までに以下の準備を行っておくことが必要です。
▼運用前に行っておく準備
- 就業規則の変更方針を定めて従業員へ周知を行う
- 新制度の規定を作成して従業員に共有する など
新制度の運用を開始して一定期間が経過したあとは、利用率の集計や満足度の調査を行って効果検証を実施します。結果を踏まえて改善策を講じることで、従業員にとってより満足度の高い制度運用へとつながります。
なお、住居に関する福利厚生の一種となる“社宅制度”の見直しについては、こちらの記事で解説しています。併せてご確認ください。
→【詳しく知りたい!】『リロの社宅管理』を導入・利用企業様の事例はこちら
福利厚生を見直すときのポイント
福利厚生を見直すときは、目的を明確にしたうえで利用しやすい申請手続きの仕組みづくりや、不公平感を生まないような制度設計が求められます。
➀見直しを行う目的を明確にする
福利厚生は働き方や従業員ニーズの変化に伴って見直すことが望まれますが、企業によって最終的に成し遂げたい目的は異なります。
見直しを行う目的を明確にしたうえで、従業員にとっても「利用したい」と思うような魅力的な福利厚生を導入することがポイントです。
▼福利厚生を見直す目的の例
- 利用率の低い制度を見直して運用コストの削減を図りたい
- 育児・介護による離職を防いで人材の定着化を図りたい
- 働きやすい職場づくりによって優秀な人材を確保したい
- 健康保持・増進によって欠勤や休職を防ぎたい など
②申請手続きを簡略化する仕組みを整える
新しい福利厚生の利用を促進するために、申請手続きを簡単に行える仕組みを整える必要があります。
▼申請手続きを簡略化する方法
- 申請・承認フローを短縮する
- 社内ポータルサイトにWeb申請窓口を設置する
- オンライン申請ができるツールを導入する など
パソコンやスマートフォンから利用申請を行えるようにすると、管理者の承認や経費の処理なども円滑に行うことが可能です。
③公平性や納得感のある制度設計を行う
福利厚生を見直す際には、公平性や納得感のある制度設計が欠かせません。
2020年4月(※)に施行されたパートタイム・有期雇用労働法により、雇用形態の違いによる不合理な待遇差を設けることが禁止されました。
雇用形態にかかわらず同じ職務を行っている従業員であれば、同一の福利厚生を提供する必要があります。
また、福利厚生の対象者や利用条件を定める際は、根拠と理由を明確にして不公平感を生まないようにすることも重要です。
※中小企業は2021年4月から適用
出典:政府広報オンライン『2021年4月1日からパートタイム・有期雇用労働法が中小企業も適用に。』
→面倒な社宅管理業務をまるっとお任せしたい。サービス概要資料はこちら!
まとめ
この記事では、福利厚生について以下の内容を解説しました。
- 福利厚生を見直す理由と目的
- 福利厚生の見直しを進める手順
- 福利厚生を見直すときのポイント
福利厚生に対する従業員のニーズは、働き方やライフステージの変化などによって変わります。現行の制度で利用率や満足度が低くなっている場合には、見直しを行うことが必要です。
従業員の満足度を高める福利厚生へ見直すことで、人材の定着化や採用活動の強化、企業価値の向上などに結びつくと期待できます。
なかでも住宅に関する福利厚生は、企業における法定外福利厚生費の多くを占めており、従業員にとってニーズが高い制度といえます。
『リロケーション・ジャパン』では、社宅制度の構築や規定内容の見直しをサポートしております。住宅手当の対象外となる従業員に対しては、“個人版転貸サポート”による新しい福利厚生の選択肢をご提案いたします。
「社宅制度を新たに導入したいが、制度設計に不安がある」「社宅制度に不満の声が上がっており、規程を見直したい」という方は、当社にお任せください。