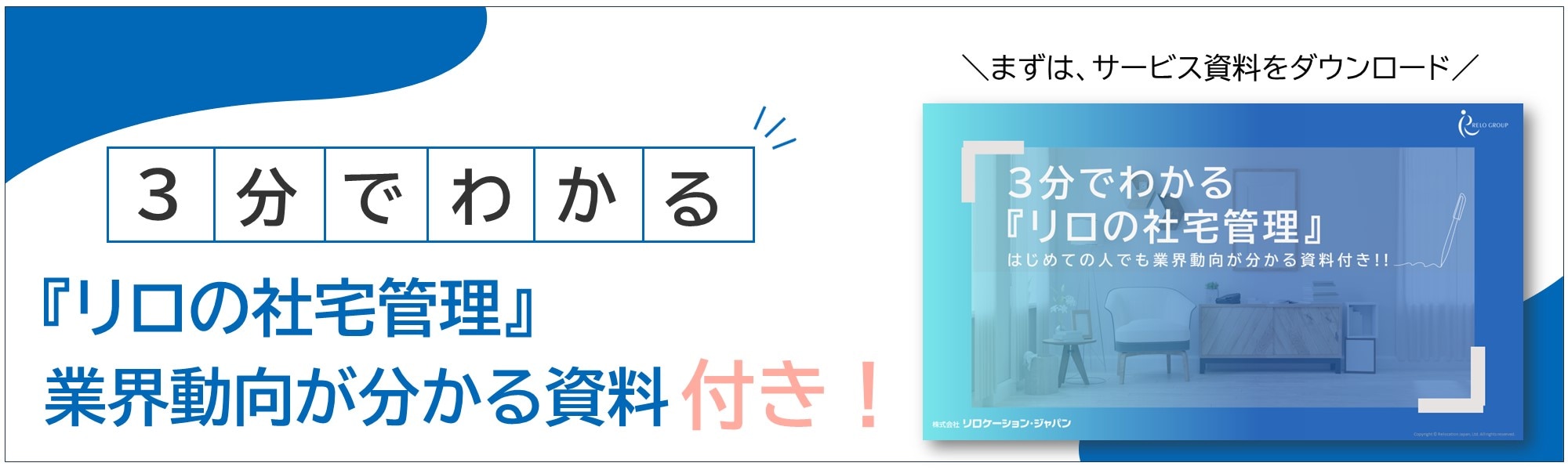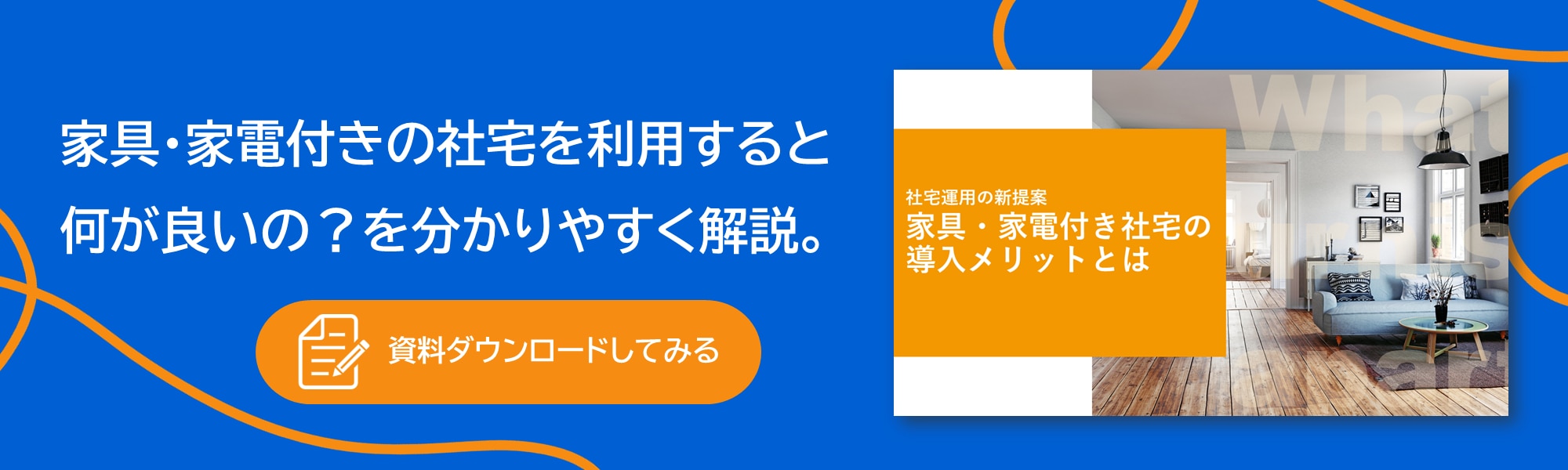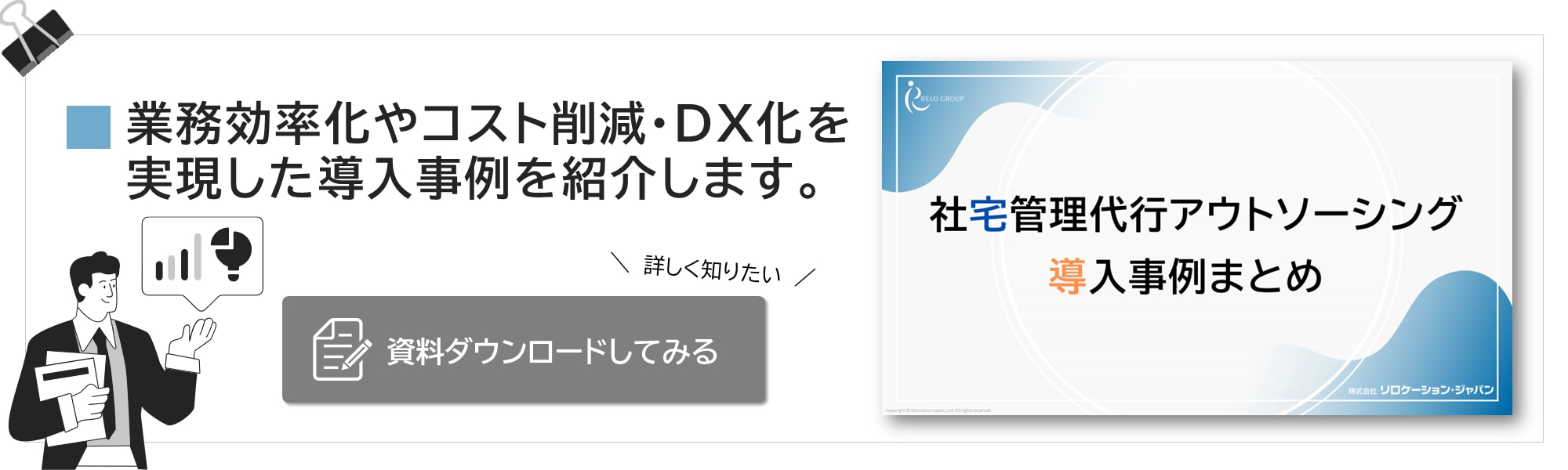福利厚生を充実させて満足度を向上! 従業員に喜ばれる制度8選
福利厚生には、法律で導入が義務づけられている“法定福利厚生”と、企業が任意で導入できる“法定外福利厚生”の2種類があります。
企業イメージを高めるには、法律で定められた範囲に加えて、従業員に喜ばれる法定外福利厚生を充実させることが重要です。
人事・総務部門のご担当者さまのなかには「現在の福利厚生を見直して従業員の満足度を高めたい」「人材の定着化や採用力の向上につなげたい」とお考えの方もいるのではないでしょうか。
この記事では、従業員に喜ばれる主な法定外福利厚生をご紹介します。また、会社として捻出するコストが満額で従業員に提供できるかを確認するため、各制度の課税区分についても解説します。
法定外福利厚生の種類についてはこちらの記事で詳しく解説しています。
目次[非表示]
- 1.法定外福利厚生を充実させる効果
- 2.住宅に関する福利厚生
- 2.1.➀家賃補助・住宅手当
- 2.2.②社宅・社員寮
- 3.健康保持・増進を図る福利厚生
- 3.1.③人間ドックの受診費用補助
- 3.2.④スポーツジムの利用支援
- 4.飲食支援の福利厚生
- 5.従業員の成長を促す福利厚生
- 5.1.⑦資格取得費用の支給
- 5.2.⑧書籍購入費の補助
- 6.まとめ
→面倒な社宅管理業務をまるっとお任せしたい。サービス概要資料はこちら!
法定外福利厚生を充実させる効果
近年、仕事と生活の両方を大切にする“ワークライフバランス”や、従業員の健康管理を経営的な視点で捉えて戦略的に投資する考え方が重視されています。
法定外福利厚生は法律による導入義務はありませんが、心身の健康維持や働きやすい職場づくりのために欠かせない制度といえます。法定外福利厚生を充実させることで、企業に対してもさまざまな効果が期待できます。
▼法定外福利厚生を充実させる効果
効果 | 理由 |
企業価値の向上 | 福利厚生を通じて従業員を大切にする取り組みが社会的な評価につながる |
人材の定着化 | ワークライフバランスが取れた働きやすい職場は、従業員満足度の向上につながり離職を防げる |
入社希望者の増加 | 魅力的な福利厚生で競合他社との差別化を図り、応募者の増加を図れる |
生産性の向上 | 心身の健康維持や仕事に対するモチベーションの向上により、業務のパフォーマンスが高まる |
従業員のニーズと自社の目的に合わせて福利厚生の充実化を図ると、満足度の向上につながります。具体的には、ワークワイフバランスの確保やキャリアアップ、心身の健康促進、生活の安定化などを支援する制度が挙げられます。
次の段落では、従業員から喜ばれやすい制度をジャンル別に紹介します。各制度における課税・非課税の対象についてもまとめました。
住宅に関する福利厚生
住宅は、従業員が安定した生活を送るために欠かせない基盤です。生活費の多くを占める住居費の負担を抑える福利厚生を導入することで、生活の安定化につながります。
➀家賃補助・住宅手当
家賃補助・住宅手当は、従業員が契約する家賃や住宅ローンの一部を補助する制度です。企業が毎月の住居費を補助することで、生活費の支出が抑えられて家計にゆとりが生まれると考えられます。
企業の導入目的を踏まえて、対象とする従業員の年齢や世帯の種類、支給額の上限額などを定めることが必要です。
▼課税・非課税の対象
給与に上乗せして支給する家賃補助・住宅手当は、税法上の給与所得に該当するため、所得税の課税対象となります。
出典:国税庁『No.2508 給与所得となるもの』
②社宅・社員寮
社宅・社員寮は、企業が従業員に対して住居を貸与する制度です。住居費の負担を抑えたり、入社・転勤時に速やかに住居を確保できるように支援したりする目的があります。
社宅・社員寮には、企業が所有する物件を提供する“社有社宅”と、賃貸物件を借り上げて貸与する“借上社宅”の2種類に分けられます。
▼課税・非課税の対象
社有社宅と借上社宅のいずれであっても、従業員から賃貸料相当額の50%以上となる社宅使用料を徴収している場合は、所得税は課税されません。
なお、住宅手当との違いや社宅使用料の決め方については、こちらの記事をご確認ください。
出典:国税庁『No.2597 使用人に社宅や寮などを貸したとき』
→【おすすめ!】記事とあわせて読みたい「家具・家電付き社宅の導入メリットとは」
健康保持・増進を図る福利厚生
従業員に活力を持って働いてもらうには、心身の健康が欠かせません。福利厚生を通じて健康保持・増進を支援することで、体調不良による欠勤・離職を防止できるほか、従業員の安心感にもつながります。
③人間ドックの受診費用補助
法定健康診断(※)の範囲外となる人間ドックについては「受診費用が負担になる」といった理由で受診を控える従業員も少なくありません。
企業が費用を補助することで従業員の積極的な受診を促せるほか、健康問題が見つかった際に早期発見・早期治療につなげられます。
▼課税・非課税の対象
一定年齢以上の希望者が人間ドックを受診でき、すべての人を対象として企業が費用を負担する場合には、給与として所得税を課税する必要はありません。
※労働安全衛生法において事業者に実施が義務づけられている健康診断
出典:厚生労働省『健康診断の費用は労働者と使用者のどちらが負担するものなのでしょうか?』/国税庁『人間ドックの費用負担』
④スポーツジムの利用支援
民間スポーツクラブの法人会員となり、従業員が無料で利用できたり、月額使用料の割引を受けられるようにする制度があります。
出勤前・退社後に手軽にスポーツジムを利用できるようになると、仕事のリフレッシュ促進や運動習慣の形成を図れます。
▼課税・非課税の対象
スポーツジムの使用料を従業員に現金で支給する場合には、給与として所得税の課税対象になります。
飲食支援の福利厚生
生活に欠かせない飲食費は、従業員にとって負担になりやすい支出の一つです。また、外食中心の食生活を送っている従業員は、生活習慣病をはじめとする健康面への不安もあります。
企業が福利厚生の一環として飲食支援を行うことは、家計の負担軽減や健康的な食生活づくりにつながり、従業員の満足度が高まります。
⑤弁当の提供・割引
昼食や夜勤時の夜食に弁当を提供する制度です。無料または割引価格で弁当を提供する方法があります。
従業員が飲食費を削減できるだけでなく、外出しなくても社内で手軽に食事を済ませられるメリットがあります。また、会社で栄養バランスに配慮した弁当を食べられることは、食生活に不安を抱える従業員にも喜ばれます。
▼課税・非課税の対象
弁当を支給する際に以下の2つの要件を満たしている場合は、給与として所得税は課税されません。
- 企業が食事価額(※1)の半分以上を負担している
- 従業員の負担額が1ヶ月当たり3,500円(※2)以下
※1…外部から購入する場合は購入価格、自社で作った弁当を支給する場合は調理に直接かかった費用の合計額を指す。
※2…消費税は除く
出典:国税庁『No.2594 食事を支給したとき』
⑥ランチ費用の補助
飲食支援の福利厚生として、ランチ費用を補助する制度があります。現金で支給することで、従業員がその日の気分に合わせて食べたいものを選択できます。
「休憩時間の外食を楽しみにしている」「外に出て気分転換をしたい」といった従業員に喜ばれやすいといえます。
▼課税・非課税の対象
現金で食事代を補助する場合には、全額が給与として課税されます。ただし、深夜勤務者で夜食の支給ができず、1食当たり300円以下の金額を支給する場合は非課税となります。
出典:国税庁『No.2594 食事を支給したとき』
従業員の成長を促す福利厚生
スキルの習得やキャリアアップを支援する福利厚生は、成長意欲がある従業員のモチベーション向上を図れるほか、人材の育成によって業務パフォーマンスの向上が期待できます。
⑦資格取得費用の支給
従業員が資格を取得するためにかかる費用を支給する制度です。研修会・講習会の出席費用や試験の受講料などを支給することで、従業員のスキル向上とキャリア形成を後押しできます。
▼課税・非課税の対象
業務に直接必要とされる技能・知識を習得するための資格について企業が取得費用を支給した場合には、所得税は非課税となります。
出典:国税庁『No.2601 職務に必要な技術などを習得する費用を支出したとき』
⑧書籍購入費の補助
業務に関するスキル・知識の習得や自己啓発などを目的として、書籍の購入費用を企業が一部または全額負担する制度です。
一ヶ月の上限金額を設定して読みたい本を申請できるようにしたり、購入した書籍を社内の図書館に保管してレンタルできるようにしたりする方法があります。
書籍の購入にかかる金銭的な負担を減らすことで積極的な学びが促され、スキルの向上が期待できます。
▼課税・非課税の対象
業務に必要な技術・知識を習得するための書籍を購入する場合には、非課税の対象となります。一方、従業員の自己啓発や個人所有する書籍を企業の費用で購入する場合には、現物給与として課税の対象となります。
なお、福利厚生の見直しを進める手順についてはこちらをご確認ください。
出典:国税庁『No.2601 職務に必要な技術などを習得する費用を支出したとき』
→【詳しく知りたい!】『リロの社宅管理』を導入・利用企業様の事例はこちら
まとめ
この記事では、法定外福利厚生について以下の内容を解説しました。
- 法定外福利厚生を充実させる効果
- 従業員に喜ばれる制度8選
法定外福利厚生を充実させて安定した生活や健康づくり、スキル向上などを支援することにより、従業員の満足度向上につながります。
なかでも住居費の負担を抑えられる住宅関連の福利厚生は、安定した生活基盤を整えて、従業員が安心して仕事に集中できる環境をつくるうえで重要な制度です。
『リロケーション・ジャパン』では、転貸方式による借上社宅のフルアウトソーシングや社有社宅の運用代行を行っております。社宅の運用管理を行う負担を削減して、従業員に喜ばれる福利厚生を導入できます。
詳しくは、こちらをご確認ください。