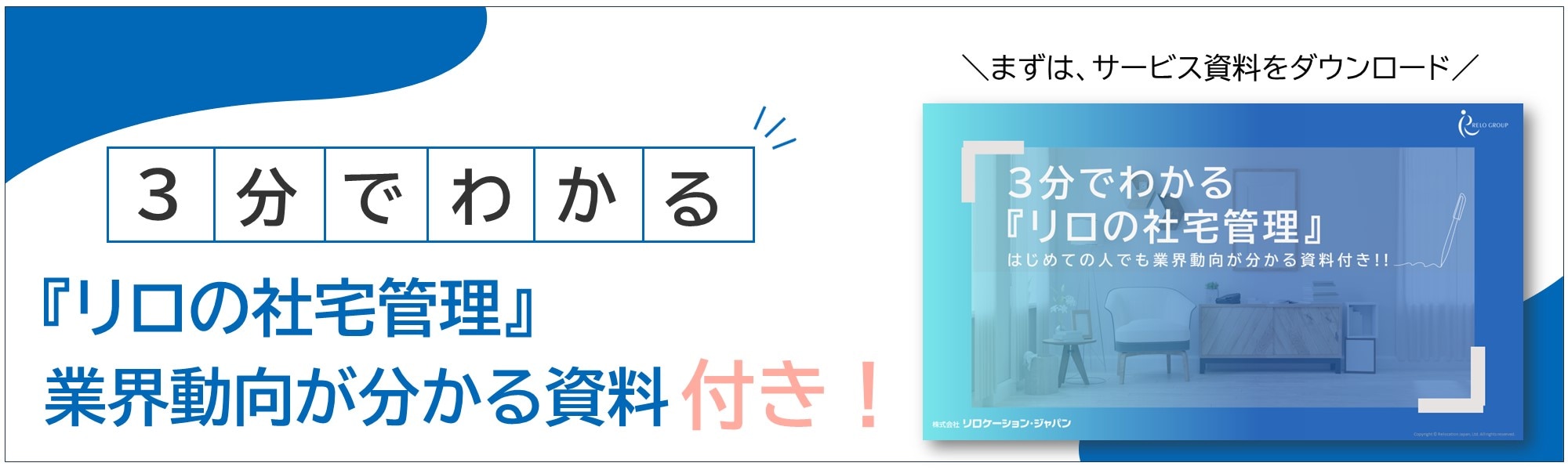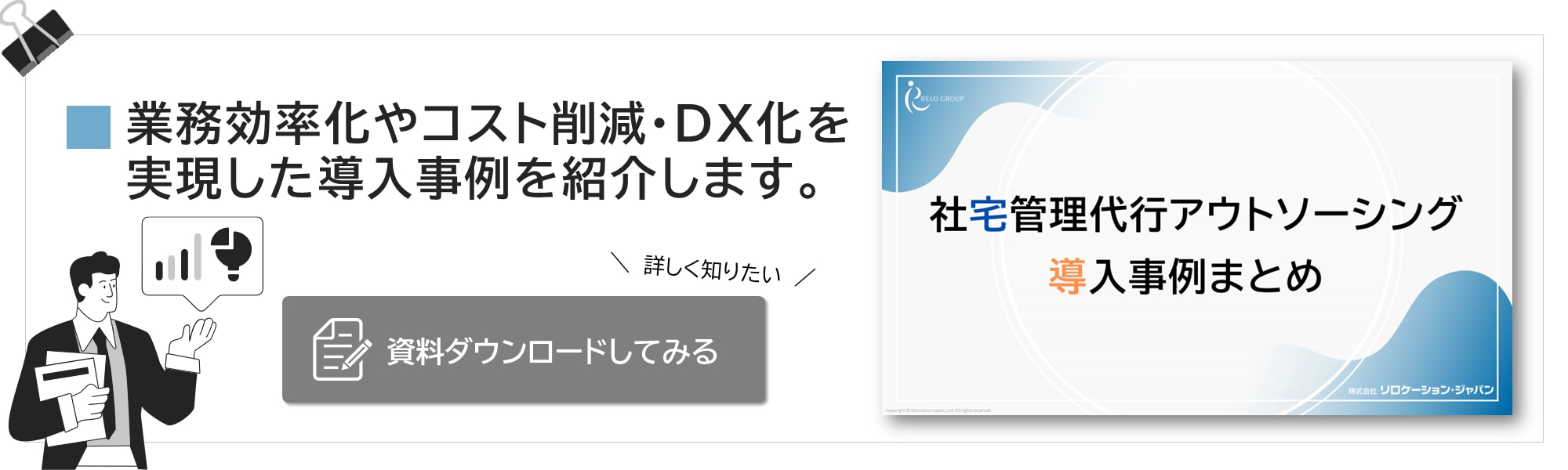借り上げ社宅の自己負担額は家賃の20~35%が相場。社宅使用料を決める際のポイントとは
借上社宅は、企業が賃貸物件を借り上げて従業員に貸与する制度です。福利厚生の満足度向上や転勤者への経済的支援などを目的として企業に導入されています。
借上社宅の運用においては、毎月の社宅使用料を設定する必要があります。人事総務部門のご担当者さまのなかには、「従業員側の自己負担額はどれぐらいに設定すればよいか」と疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。
この記事では、借上社宅における自己負担額の考え方や相場、従業員から徴収する社宅使用料の決め方とポイントについて解説します。
なお、福利厚生としての社宅制度と住宅手当のメリット・デメリットについては、こちらの資料で詳しく解説しています。併せてご覧ください。
目次[非表示]
借上社宅における自己負担額の考え方
借上社宅の自己負担額とは、従業員から毎月徴収する社宅使用料を指します。企業が物件の貸主に支払う家賃のうち、従業員の自己負担とする社宅使用料を設定します。
混同されやすい家賃と社宅使用料の考え方を整理すると、以下のようになります。
▼借上社宅における家賃と社宅使用料の考え方
項目 | 家賃 | 社宅使用料 |
意味 | 賃貸借契約で定められた家賃 | 従業員が社宅を使用する費用 |
支払者 | 企業(賃貸借契約の借主) | 社宅に入居する従業員 |
支払先 | 物件の貸主 | 企業 |
企業が設定した社宅使用料は、従業員に支払う毎月の給与から差し引くことによって徴収する仕組みになります。
→面倒な社宅管理業務をまるっとお任せしたい。サービス概要資料はこちら!
従業員から徴収する自己負担額の相場
借上社宅の運用で設定する従業員の自己負担額は、周辺地域の類似物件における家賃の20~35%程度(※)とされています。
人事院の『民間企業の勤務条件制度等調査 (令和4年調査結果)』によると、借上社宅での従業員負担額(平均月額使用料)は、物件の種別ごとに異なっています。
▼借上社宅の家賃と従業員負担額
物件種別 | 家賃 (企業の契約額) | 従業員負担額 (平均月額使用料) | |
独身用社宅 | 6万4,309円 | 1万8,184円 | |
世帯用社宅 | 55m2未満 | 8万5,786円 | 2万5,326円 |
55以上70m2未満 | 9万4,280円 | 2万9,208円 | |
70以上80m2未満 | 10万2,219円 | 3万2,220円 | |
80m2以上 | 11万1,051円 | 3万4,232円 | |
人事院『民間企業の勤務条件制度等調査 (令和4年調査結果)』を基に作成
独身用の物件では、従業員から徴収する平均月額使用料が1万8,184円となり、家賃の6万4,309円に対して約30%の負担額が設定されています。
世帯用物件では、面積によって平均月額使用料が異なるものの、家賃に対する負担額の割合は約30%前後となっていることが分かります。
なお、社有社宅や独身寮の課題と解決策はこちらの資料をご確認ください。
※非課税となる自己負担額の割合については税務署にご確認ください。
出典:人事院『民間企業の勤務条件制度等調査 (令和4年調査結果)』
従業員の自己負担とする社宅使用料の決め方
社宅使用料は、賃貸料相当額の50%以上を基準に設定します。
賃貸料相当額の50%以上を従業員から徴収することにより、企業負担分が給与として課税されなくなります。
▼社宅を貸与した際の源泉所得税について
使用人に対して社宅や寮などを貸与する場合には、使用人から1か月当たり一定額の家賃(賃貸料相当額の50パーセント以上)を受け取っていれば給与として課税されません。
引用元:国税庁『No.2597 使用人に社宅や寮などを貸したとき』
賃貸料相当額は、企業が貸主に支払う家賃と同じではありません。一般的に賃貸料相当額は家賃よりも低い金額となり、以下の1~3を合計して算出します。
▼賃貸料相当額の算出方法
- (その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%
- 12円×(その建物の総床面積(m2)/3.3(m2))
- (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%
例えば、賃貸料相当額が8万円の物件を貸与する場合、50%以上となる5万円の社宅使用料を従業員から徴収していれば、差額の3万円は課税対象になりません。
なお、賃貸料相当額の計算方法は、借上社宅にかかわらず企業が所有する社宅を貸与する場合でも同様となります。
出典:国税庁『No.2597 使用人に社宅や寮などを貸したとき』
借上社宅の自己負担額を決める際のポイント
借上社宅の自己負担額を決める際は、賃貸料相当額のほかにも着目するポイントがあります。
➀管理費・共益費の負担区分を明確にする
社宅使用料のなかに管理費・共益費を含めるのか、企業と従業員の負担区分を明確にしておく必要があります。
賃貸物件によって、管理費・共益費の扱いや費用が異なります。例えば、家賃と別で管理費・共益費が発生する物件と、家賃のなかに管理費・共益費が含まれている物件があります。
▼物件ごとに異なる管理費・共益費の扱い
家賃 | 管理費・共益費 | |
物件A | 8万円 | 6,000円 |
物件B | 8万円6,000円 | 0円 |
社宅使用料を決める際は、従業員とのトラブルが起きないように社宅規程や内規などで費用の負担区分を明文化しておくことが重要です。
社宅における管理費・共益費の扱いについてはこちらの記事をご確認ください。
②地域ごとの家賃相場を考慮する
同じ広さ・間取り・築年数の物件でも、地域によって家賃相場は異なります。
従業員の負担割合を一律に設定すると、家賃相場が高い地域では従業員が負担する社宅使用料が高くなることがあります。
地域による家賃相場の違いを考慮したうえで、従業員の不公平にならないように合理的な負担割合を設定することが重要です。
なお、物件の更新時に家賃が値上げされた場合の対応については、こちらの記事をご確認ください。
③目的や対象者に合わせて柔軟に負担割合を設定する
転勤の有無や入社年数、年齢など、社宅を貸与する目的・対象者に応じて柔軟に負担割合を設定することで、公平性に考慮した運用が可能になります。
負担割合を柔軟に設定する例として、以下が挙げられます。
▼負担割合の設定例
目的 | 設定例 |
若手人材の採用・定着を図りたい | 新入社員の負担割合を低く設定する 独身者を対象に負担割合を低く設定する |
働きやすさを向上したい | 朝勤・夜勤がある部署や急な出社が求められる職種の負担割合を低く設定する |
転勤の辞令を円滑に承諾してもらいたい | 転勤者の負担割合を低く設定する |
なお、社宅の入居条件について公平性のある制度設計を行うポイントは、こちらの記事で解説しています。
→【詳しく知りたい!】『リロの社宅管理』を導入・利用企業様の事例はこちら
まとめ
この記事では、借上社宅の自己負担額について以下の内容を解説しました。
- 借上社宅における自己負担額の考え方
- 従業員から徴収する自己負担額の相場
- 従業員の自己負担とする社宅使用料の決め方
- 借上社宅の自己負担額を決める際のポイント
社宅使用料として従業員から徴収する自己負担額は、企業が契約した家賃に対して20~35%程度が相場とされています。
また、借上社宅の自己負担額を決める際は、管理費・共益費の扱いを明確にするとともに、地域の家賃相場や制度の目的・対象者に合わせて柔軟に設定することがポイントです。
『リロケーション・ジャパン』では、包括転貸方式による借上社宅のフルアウトソーシングサービスを提供しています。日々の社宅管理業務のほか、社宅制度の構築から社内業務フローの設計までトータルサポートいたします。
詳しくは、こちらの資料をご確認ください。