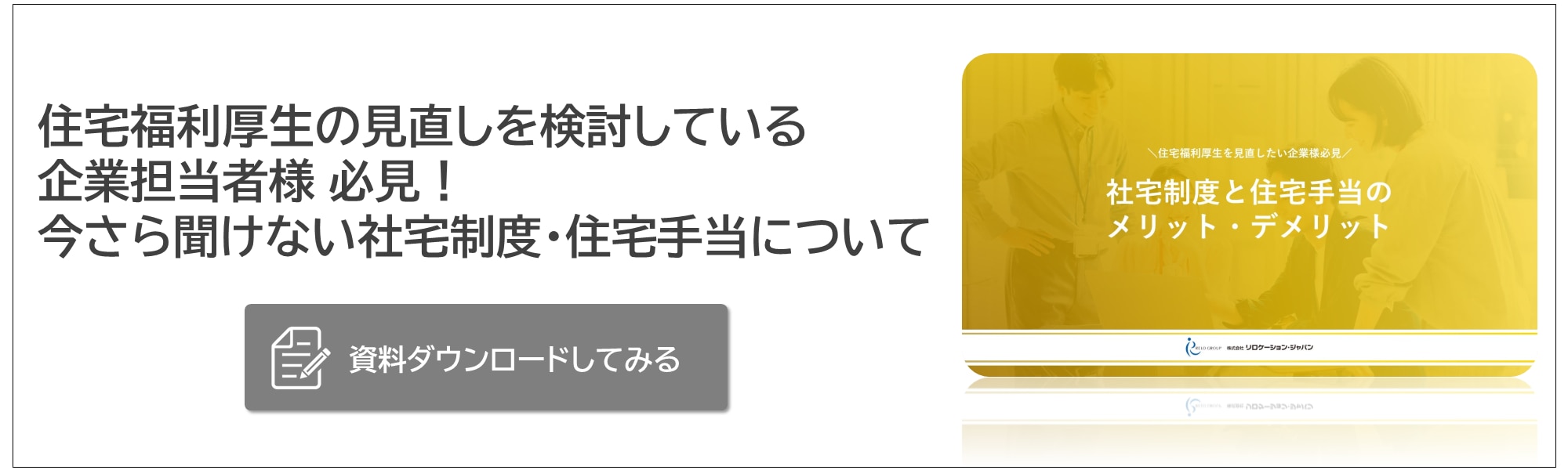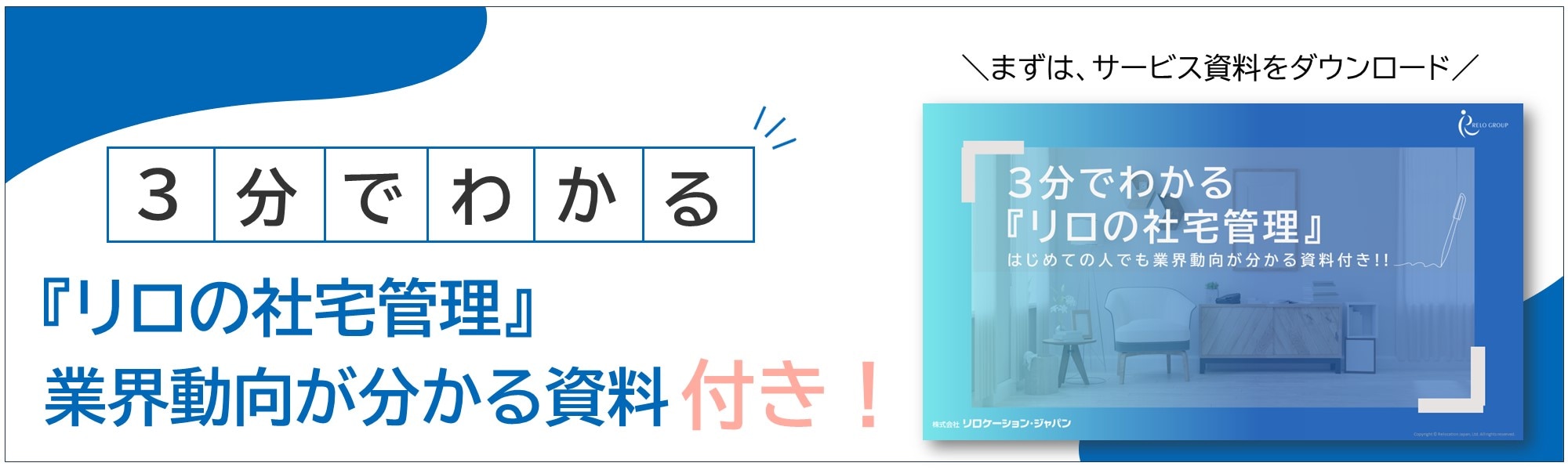社宅と住宅手当はどっちが得? 企業が導入する際の比較ポイント
住宅関連の福利厚生として代表的な制度に、社宅と住宅手当が挙げられます。
住居にかかる費用の一部を会社側が負担することにより、従業員の経済的な負担を抑えて安定した生活を支える目的があります。しかし、社宅と住宅手当については課税の仕組みや社会保険料への影響などが異なります。
人事総務部門のご担当者さまのなかには、従業員に喜ばれる福利厚生を導入するにあたって「社宅と住宅手当はどっちが得なのか?」と気になる方もいるのではないでしょうか。
この記事では、社宅と住宅手当の違いや比較のポイント、会社・従業員にとって金銭的に得といえる制度について解説します。
なお、住宅関連における福利厚生についてはこちらの資料をご確認ください。
目次[非表示]
→【おすすめ!】記事とあわせて読みたい「社宅制度と住宅手当のメリット・デメリット」
社宅と住宅手当の違い
社宅と住宅手当は、運用の仕組みに違いがあります。
▼社宅と住宅手当の違い
項目 | 社宅 | 住宅手当 |
提供方法 | 現物(住居) | 金銭 |
給与課税の有無 | 原則非課税 | 課税 |
物件の契約者(所有者) | 企業 | 従業員 |
物件の選択者 | 企業または従業員 | 従業員 |
社宅は、企業が所有または借り挙げた社宅を従業員に貸与して一定割合の使用料を徴収する制度です。企業が指定する物件のほか、社宅規程の範囲内で従業員が物件を選べるようにしている場合があります。
一方の住宅手当は、従業員が契約する賃貸物件の家賃や住宅ローンにおける毎月返済額の一部を手当として支給する制度です。物件は従業員が自由に選択でき、企業が定めた条件を適していれば支給の対象となります。
それぞれの違いについて、詳しくはこちらの記事で解説しています。併せてご確認ください。
社宅と住宅手当はどっちが得なのか。3つの比較ポイント
社宅と住宅手当の制度を比較する際には、従業員の税負担や社会保険料への影響、運用管理の負担について確認しておく必要があります。
➀従業員の税負担
社宅と住宅手当では、社宅のほうが従業員の税負担を抑えられます。
▼従業員の税負担に関する比較
社宅 | 住宅手当 |
所得税や住民税の負担を抑えられる | 給与所得になることで税負担が増える |
社宅を提供する場合は、従業員から1ヶ月当たり一定額の使用料(賃貸料相当額の50%以上)を徴収していれば所得税は非課税となります。会社側で負担する使用料の部分については税金がかかりません。
使用人に対して社宅や寮などを貸与する場合には、使用人から1か月当たり一定額の家賃(賃貸料相当額の50パーセント以上)を受け取っていれば給与として課税されません。
引用元:国税庁『No.2597 使用人に社宅や寮などを貸したとき』
また、社宅の使用料については従業員の給与から天引きします。課税対象となる所得が減るため、結果的に所得税・住民税の負担削減につながります。
一方の住宅手当は、税制上の給与所得として扱われます。課税対象となる所得が増えることにより、金額によっては所得税や住民税の金額が増加する可能性があります。
役員や使用人に支給する手当は、原則として給与所得となります。具体的には、残業手当や休日出勤手当、職務手当等のほか、地域手当、家族(扶養)手当、住宅手当なども給与所得となります。
引用元:国税庁『No.2508 給与所得となるもの』
賃貸料相当額の計算方法はこちらの記事をご確認ください。
出典:国税庁『No.2597 使用人に社宅や寮などを貸したとき』『No.2508 給与所得となるもの』
②社会保険料の負担額
社会保険料の負担額についても社宅のほうが抑えやすくなります。
▼社会保険料の負担額に関する比較
社宅 | 住宅手当 |
会社負担分が非課税になるため、社会保険料の算定に影響がない | 給与所得として扱われるため、社会保険料が増える可能性がある |
健康保険や厚生年金保険といった社会保険料は、毎月の給与所得(標準報酬月額)を基に算定され、原則として労使が折半する仕組みになっています。
健康保険・厚生年金保険の保険料は、給与を基に「標準報酬月額」を決定し、これに保険料率をかけて計算され、事業主と加入者本人が半分ずつ負担します。
引用元:日本年金機構『健康保険・厚生年金保険制度』
社宅の場合では、使用料の会社負担分が非課税となり、従業員負担分は給与からの天引きによって所得を減らせるため、社会保険料の負担も少なくなります。
一方の住宅手当は、支給した金額が給与所得として扱われ、社会保険料の算定基礎に含まれることから会社と従業員それぞれの負担が増える可能性があります。
出典:厚生労働省『社会保険加入のメリットや手取りの額の変化について』/日本年金機構『健康保険・厚生年金保険制度』
③運用管理の負担
福利厚生としての運用管理にかかる負担は、社宅と比較して住宅手当のほうが抑えやすいと考えられます。
▼運用管理の負担に関する比較
社宅 | 住宅手当 |
物件の契約や管理業務が発生する | 手当の支払い管理が主となる |
住宅手当では、毎月の給与とともに金銭で手当を支給する作業が発生しますが、物件に関する管理は不要なため、運用の負担は少ないと考えられます。
一方、借上社宅の運用には、賃貸借契約の手続きや入退去の管理、家賃の支払いなどの幅広い業務が発生します。社有社宅の場合は、建物の維持管理やメンテナンスなども会社側で対応する必要があり、社宅担当者の負担が増加しやすくなります。
社宅の運用管理にかかるリソースや労力に課題を持つ企業は、外部にアウトソーシングすることも一つの方法です。社宅代行サービスについては、こちらの記事をご確認ください。
なお、社宅と住宅手当のメリット・デメリットはこちらの資料にまとめています。
会社・従業員にとって金銭的に得なのは社宅制度
会社・従業員にとって金銭的な観点から得といえるのは、税負担や社会保険料を抑えられる社宅制度といえます。
近年、場所に縛られない多様な働き方の推進や、地方人材の獲得などを目的として、住宅手当から社宅制度へ切り替える企業が見られています。
▼社宅が導入されている業種
- 医療・介護福祉業(病院、診療所、老人ホーム)
- 児童福祉業(保育所、幼稚園、認定こども園)
- 宿泊業(ホテル、旅館)
- 建設業 など
特に地方人材の採用・定着化を図る医療法人や社会福祉法人では、入社志望者を集めるために社宅を導入しているところが見られます。また、転勤が多い職業では、従業員の引越し負担を抑えて離職を防ぐために社宅を導入する事業者もあります。
住宅関連の手厚い福利厚生によって従業員の満足度向上や人材の採用促進・定着化を図りたい方は、社宅の導入を検討されてはいかがでしょうか。
なお、住宅手当が廃止される背景や保育事業者の社宅については、こちらの記事で詳しく解説しています。
→面倒な社宅管理業務をまるっとお任せしたい。サービス概要資料はこちら!
まとめ
この記事では、社宅と住宅手当について以下の内容を解説しました。
- 社宅と住宅手当の違い
- 社宅と住宅手当に関する3つの比較ポイント
- 会社・従業員にとって得といえる制度について
社宅と住宅手当は、どちらも住居に関するサポートを行う福利厚生です。しかし、給与課税の扱いや提供方法が異なるため、所得税の課税有無、社会保険料への影響、運用管理の負担などが変わってきます。
税金や社会保険料などの金銭的な観点から見ると、会社・従業員にとって得といえるのは社宅制度といえるでしょう。社宅の運用管理に要するリソースに問題がある場合には、外部にアウトソーシングする選択肢があります。
『リロケーション・ジャパン』では、包括転貸方式による借上社宅のフルアウトソーシングや社有社宅の運用代行を承っております。社宅管理にかかる煩雑な業務をサポートして大幅な工数削減に貢献します。
詳しくは、こちらの資料をご覧ください。