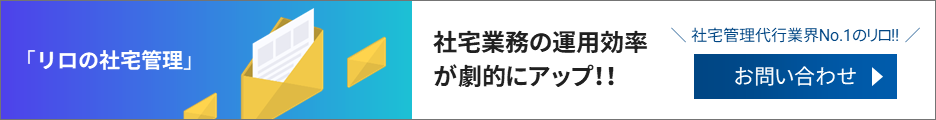社宅代行サービスとは。一般的なBPOサービスとの違いや利用の流れ
※2024年10月2日更新
社宅の運用には、賃貸借契約や入居・退去管理、家賃の徴収などさまざまな業務が発生します。「社宅の数が多く対応が追いつかない」「社宅担当者の業務負担が増えている」などの課題を抱えているケースも少なくありません。
このような場合には、社宅代行サービスを活用することも一つの方法です。社宅代行サービスは、社宅管理に関するさまざまな業務を委託できるため、社宅担当者の業務負担を削減できるメリットがあります。
また、快適で安心して暮らしやすい社宅環境を整えるためのきめ細かなフォローも可能となり、入居している従業員の満足度の向上につながることも期待できます。
社宅代行サービスを検討している人事総務部門のご担当者さまのなかには、「社宅代行サービスと一般的なBPOサービスは何が違うのか」「どのような流れで利用すればよいのか」などと情報収集を行っている方もいるのではないでしょうか。
この記事では、社宅代行サービスの特徴やBPOサービスとの違い、社宅代行サービスが求められる理由、利用の流れについて解説します。
→【おすすめ】記事とあわせて読みたい!『リロの社宅管理』サービス概要資料はこちら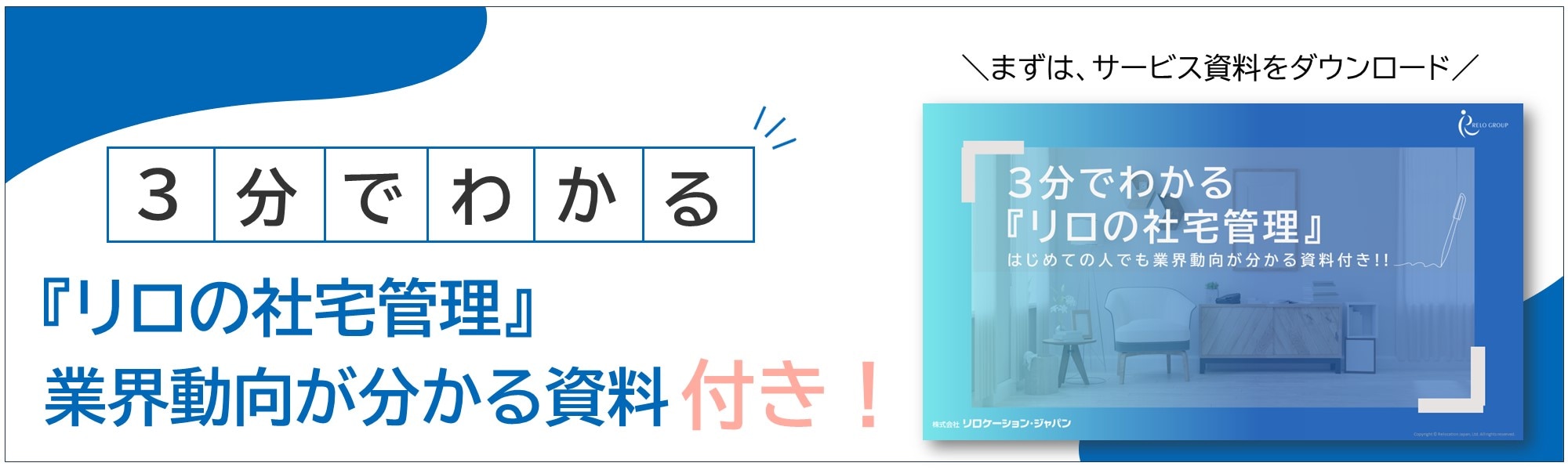
目次[非表示]
社宅代行サービスとは
社宅代行サービスとは、社宅の運用に必要な業務を外部に委託できるサービスです。
委託できる業務内容はサービスを提供する社宅代行事業者によって異なりますが、一般的に以下の業務を代行してもらえます。
▼委託できる業務範囲
社宅の種類 | 借上社宅 | 社有社宅 |
委託できる業務 |
|
|
社宅代行サービスの方式
社宅代行サービスの委託方式には、主に転貸方式と代行方式の2種類があります。
①転貸方式
転貸方式とは、社宅代行事業者が一括で借り上げている賃貸物件を企業に貸し出す方式です。企業が社宅代行事業者と包括転貸借契約を交わすことで、社宅管理に関する業務をフルアウトソーシングできます。
物件の賃貸借契約は、企業ではなく社宅代行事業者が交わすため、契約当事者(借主)しか対応できない業務でも委託できることが特徴です。
また、社宅代行事業者によっては、敷金の立替や原状回復精算の定額化などのオプションサービスを展開しているところもあります。
②代行方式
代行方式とは、企業が所有または借り上げている物件の管理を社宅代行事業者が代わりに行う方式を指します。
賃貸借契約書上の名義は企業のままで、契約や更新、解約などの業務を社宅代行事業者に委託して代わりに行ってもらえることが特徴です。
代行方式の場合、一部の社宅業務のみを委託できるサービスもあるため、予算やニーズに合わせて活用できます。
なお、転貸方式と代行方式についてはこちらの記事で詳しく解説しています。併せてご確認ください。
一般的なBPOサービスとの違い
BPOサービスとは、“Business Process Outsourcing”サービスの略で、企業の業務を委託できるサービス全般を指します。
社宅代行サービスもBPOサービスの一種に当たりますが、以下の点で違いがあります。
▼社宅代行サービスと一般的なBPOサービスの違い
サービスの種類 | 特徴 |
一般的なBPOサービス | 総務・経理・人事など幅広い業務に対応している |
社宅代行サービス | 社宅管理に関わる業務に特化している |
一般的なBPOサービスでは、自社業務のうち、ノンコア業務をプロセスごと委託できます。バックオフィス業務を委託できるだけでなく、業務フローの見直しや業務改善などを行い、業務効率化、組織力強化を図ることも可能です。
一方、社宅代行サービスは、社宅管理業務に特化したBPOサービスです。社宅代行サービスを活用することで、社宅管理に必要な専門知識・ノウハウを持つ事業者に社宅の運用管理を任せられます。
社宅代行サービスを利用するメリット
社宅代行サービスを利用すると、社宅管理業務で生じる担当者への負担やトラブルのリスクの軽減につながります。また、社宅の選択肢が広がって従業員満足度の向上も期待できます。
社宅管理業務の負担を軽減できる
社宅代行サービスを活用することで、社宅管理業務の負担を軽減できます。
社宅管理を自社で行う場合、物件探しや引越し手配、賃貸借契約を含む社内外の入居・退去の手続きなどのさまざまな業務が発生します。しかし、少子高齢化によって労働力人口が減少している今、人手不足で社宅担当者に十分なリソースを充てられないという企業も少なくありません。
限られた人員で社宅管理業務に対応すると、コア業務に配分できるリソースが圧迫されたり、担当者の業務負担が増加したりする可能性があります。
社宅代行サービスを活用して社宅管理業務を委託することで、コア業務にリソースを充てられるようになり、社宅担当者の負担を軽減できます。
リスクの回避につながる
社宅代行サービスによって、社宅管理業務において生じるさまざまなリスクの回避が期待できます。
▼自社で社宅管理で生じるリスクの例
- 不動産会社やオーナーの破綻などによる訴訟トラブル
- 敷金の未回収や退去時の原状回復費用をめぐるトラブル
- 法改正対応による業務負荷や未対応によるトラブル など
社宅代行サービスを活用すれば、代行事業者が不動産会社やオーナーとの賃貸借契約を交わすため、これらのリスクを回避・削減できます。
ただし、法改正への対応は特に業務負荷になりやすいため、サービス導入後もきちんと法改正に対応した運用の見直しを行っているか、過去の実績などを参考に確認することが重要です。
幅広い選択肢から社宅を選べる
社宅代行サービスでは、社宅代行事業者が持つさまざまな不動産会社とのつながりを活用して物件を選ぶことが可能です。そのため、自社で直接不動産会社とやり取りする場合と比較して社宅にする物件の選択肢が広くなりやすいといえます。
特に、全国の不動産会社とつながりがある社宅代行事業者であれば、単身赴任に伴う転勤の際にも柔軟な対応が期待できます。
従業員満足度の向上が図れる
社宅代行サービスを利用すると、従業員満足度の向上が図れます。部屋の選択肢が広がって従業員が生活しやすい社宅を提供しやすくなることに加えて、社宅で発生するトラブルに対しても円滑に対応できるようになるためです。
従業員満足度が向上すると、企業にとっても生産性の向上や離職率の低下などの効果が期待できます。
→【おすすめ】記事とあわせて読みたい!『リロの社宅管理』サービス概要資料はこちら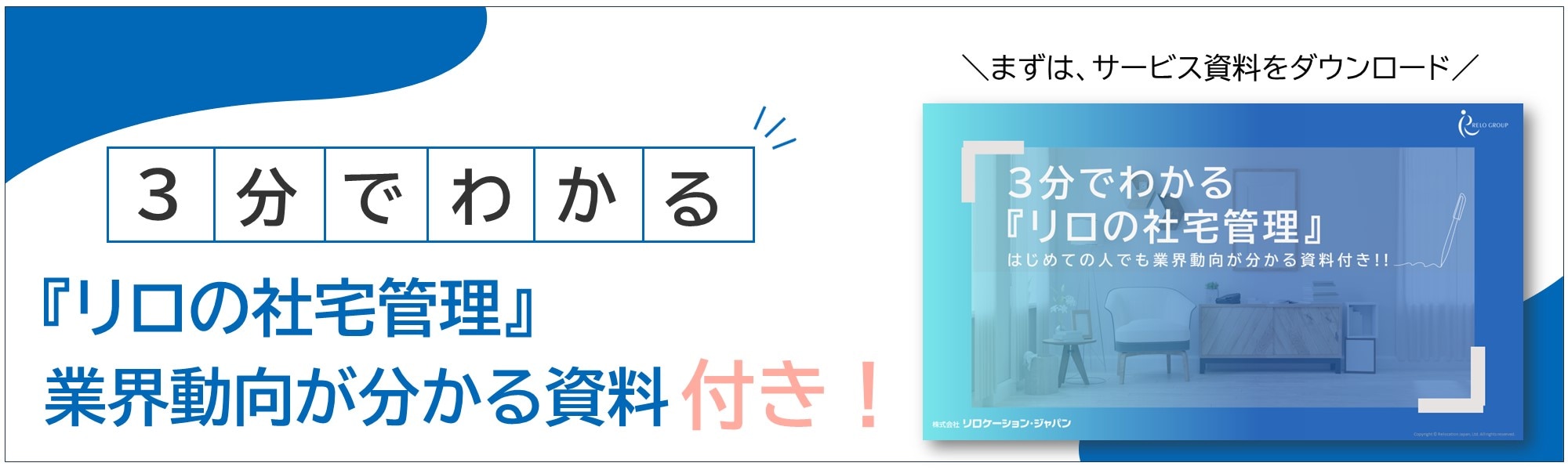
社宅代行サービスを利用する流れ
社宅代行サービスを利用する一般的な流れは、以下のとおりです。
▼利用の流れ
- 導入目的を明確にする
- 委託する業務を洗い出す
- 社宅代行サービスを選定する
- 社宅代行事業者に問い合わせる
- 複数の事業者と比較検討する
- 契約を締結する
社宅代行サービスを利用する際は、業務負担の軽減や管理品質の向上など目的を明確にする必要があります。
目的を明確にしたあとは、委託する業務の範囲や予算を策定します。この際、現状の社宅管理の課題を踏まえることが重要です。
委託範囲と予算が決まったら、社宅代行事業者を比較検討したうえで自社の条件に合う委託先と契約を締結します。
なお、社宅代行サービスを導入する流れについてはこちらの記事で詳しく解説しています。併せてご確認ください。
→【詳しく知りたい!】『リロの社宅管理』を導入・利用企業様の事例はこちら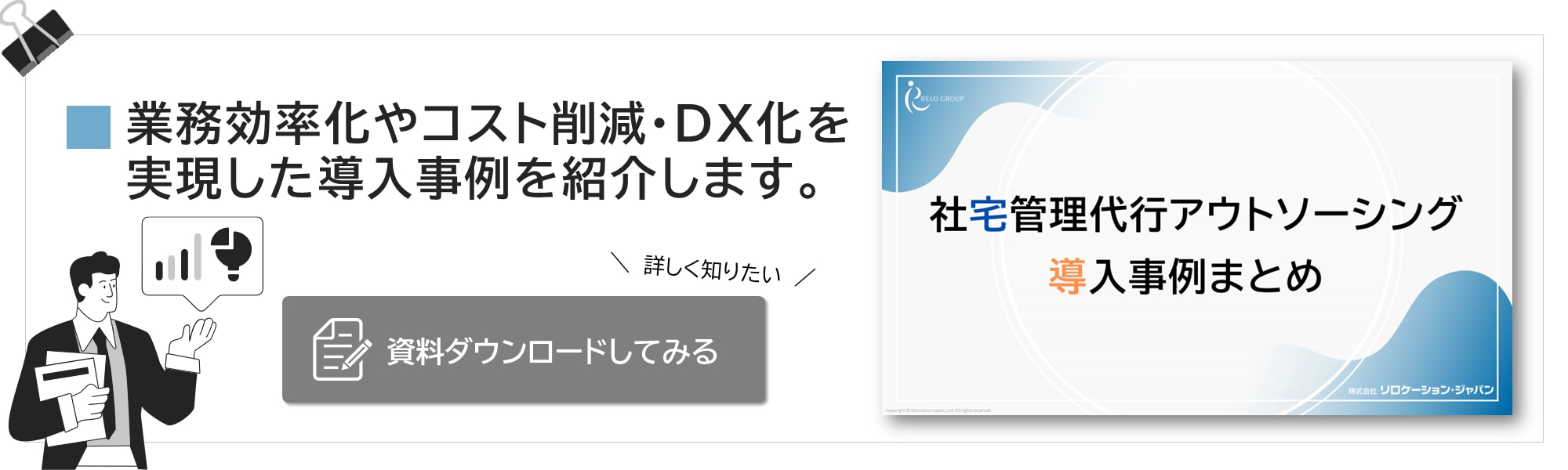
社宅代行サービスの選び方
社宅代行サービスを選ぶ際は、以下の項目を確認することが重要です。
▼社宅代行サービスを選定する際の確認項目
- 委託できる業務内容
- 委託方式(転貸・代行)
- 実績の豊富さ
- 管理戸数
- 導入時のサポート
事業者によってサービス内容は異なるため、自社が委託したい業務を明確にしたうえでサービスを選ぶ必要があります。委託方式によっても依頼できる業務内容は異なります。
また、社宅管理業務においては従業員の個人情報を取り扱うことから、信頼できる企業を選ぶことが重要です。実績が豊富な企業であれば信頼して任せやすいと考えられます。実績に関する指標の例としては、管理している社宅の戸数が挙げられます。
さらに、導入時のサポートが充実していると、より社宅担当者の負担を軽減しやすいと期待できます。
なお、社宅代行サービスの変更についてはこちらの記事で詳しく解説しています。併せてご確認ください。
まとめ
この記事では、社宅代行サービスについて以下の内容を解説しました。
- 社宅代行サービスの特徴
- 社宅代行サービスの方式
- 一般的なBPOサービスとの違い
- 社宅代行サービスを利用するメリット
- 社宅代行サービスを利用する流れ
- 社宅代行サービスの選び方
社宅代行サービスを利用することで、借上社宅や社有社宅に管理に関わるさまざまな業務を一括または一部委託できるようになります。社宅管理業務における担当者の負担やリスクの軽減につながるほか、社宅の選択肢が広がって従業員満足度の向上も期待できます。
委託方式には転貸方式と代行方式の2つがあり、それぞれ運用体制や委託できる業務範囲が異なるため、委託する目的・業務範囲を洗い出しておくことが重要です。
『リロケーション・ジャパン』では、借上社宅の転貸方式によるフルアウトソーシングのほか、代行方式による業務代行、社有社宅の運営管理などを行っています。
「人手不足で社宅管理の業務負担が大きくなっている」「トラブル対応をはじめとするリスクを回避したい」という方は、ぜひお気軽にご相談ください。