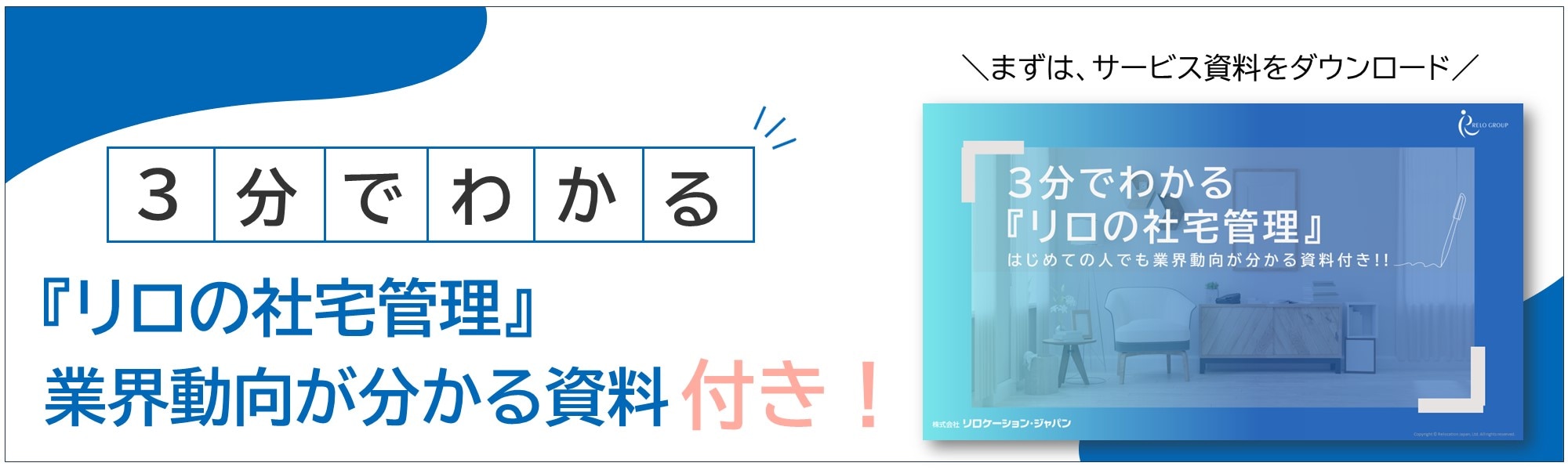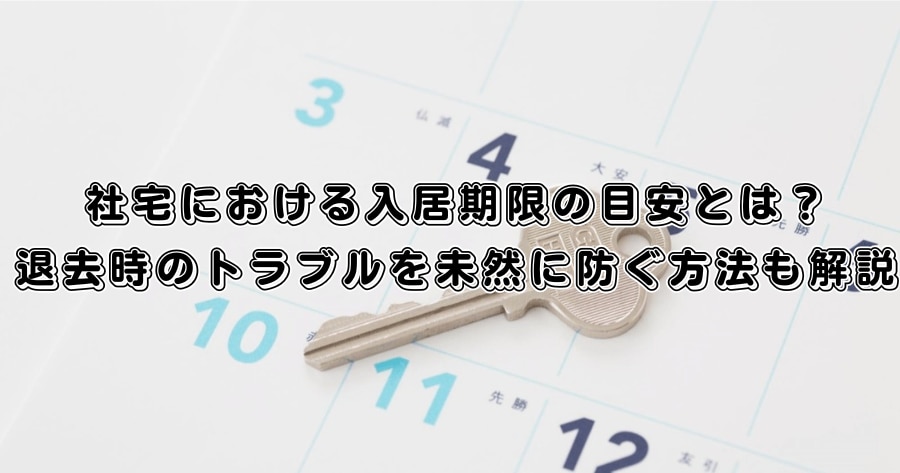
社宅における入居期限の目安とは? 退去時のトラブルを未然に防ぐ方法も解説
社宅は、従業員の経済的な負担を軽減できることから、満足度の向上につながりやすい福利厚生の一つです。全国・地方への転勤がある企業では、人材採用の強化や離職防止のために社宅制度の導入を検討している企業もあるのではないでしょうか。
社宅制度の導入にあたって取り決めておく事項の一つに、従業員の入居期限があります。借上社宅では、企業が家賃の一部を負担することから、入居者数が増えることによるコスト増加を防ぐために、一定の入居期限を設けているケースがあります。
社宅担当者は、円滑に社宅を運用するにあたって、入居期限の目安やそのほかの入居継続制限について理解を深めておくことが重要です。
この記事では、社宅における入居期限の目安をはじめ、そのほかの入居継続制限や退去時に起こりやすいトラブルを未然に防ぐ方法について解説します。
出典:人事院『令和3年 民間企業の勤務条件制度等調査結果の概要』
→【おすすめ】記事とあわせて読みたい!社員“個人”の契約でも利用できるサービス。
目次[非表示]
社宅における入居期限の目安
社宅では、一般的に5~10年の入居期限が設定されています。社宅制度は法定外福利厚生の一環となるため、入居期限は企業が任意で設定することが可能です。
人事院『令和3年 民間企業の勤務条件制度等調査結果の概要』によると、社宅制度を導入している企業のうち入居期限を定めている企業は39.4%となっています。
入居の期間が期限に達した際には入居者に退去を求められますが、子育てや配偶者の通勤などの事情から、同じ社宅に住み続けることを希望する従業員もいます。
継続入居を認める場合には、入居者本人が賃料を全額負担するよう求める企業が大半で、契約名義を個人契約に切り替えるケースが一般的です。ただし、家主・管理会社の意向や賃貸借契約書の契約内容によっては、個人契約への切り替えができない場合もございますので、その際は退去して別の物件を探すなどの対応が必要になります。
出典:人事院『令和3年 民間企業の勤務条件制度等調査結果の概要』
ほかの入居継続制限が設けられているケースもある
社宅の運用にあたって、入居期限ではなく対象者を限定したり、年齢制限を設けたりして入居の継続を制限しているケースもあります。
ここからは、人事院の『令和3年 民間企業の勤務条件制度等調査結果の概要』を基に、入居期限以外の入居継続制限について解説します。
入居対象者の限定
社宅における入居継続制限の一つに、社宅に入居できる対象者を限定する方法があります。
社宅の目的に合わせて入居対象者を絞ることで、本当に社宅が必要な従業員の住居を確保できるほか、社宅を利用しない従業員との不公平が生じるのを防げます。
対象者を設定する際は、社宅の入居理由や家族構成などの基準を設けて、条件を明確化しておくことが重要です。
入居対象者を設定する例には、以下が挙げられます。
▼入居対象者の設定例
- 転勤者
- 新規採用者や若年層従業員
- 通勤困難者(通勤時間が長い従業員)
- 独身・単身者(単身者向け社宅の場合)
- 新たに世帯を持った従業員(家族向け社宅の場合)
社宅を導入している企業のうち、入居対象者を限定している企業は82.2%です。そのうち、転勤者に限定している企業が72.2%と最も多く、次いで新卒採用者、独身・単身者の順となっています。
出典:人事院『令和3年 民間企業の勤務条件制度等調査結果の概要』
年齢の制限
所定の年齢までの従業員を入居対象とする“定年制”を導入しているケースもあります。
企業のなかには、社宅入居者に対して持ち家の購入を促すために、所定の年齢に達した際に退去してもらう規定を定めていることがあります。
年齢によって社宅の入居を制限している企業の割合は22.1%となっており、入居期限を定めるケースよりは少ないことが分かります。
出典:人事院『令和3年 民間企業の勤務条件制度等調査結果の概要』
役職の制限
従業員の役職に応じて社宅の入居を制限しているケースがあります。
非管理職のみ・幹部従業員のみといった役職を制限している企業の割合は5.0%で、ほかの入居継続制限よりも少ない割合となっています。
役職に応じて制限を設ける際は、一部の従業員・役員だけに社宅利用が優遇されないように合理的な基準を定めることが重要です。
出典:人事院『令和3年 民間企業の勤務条件制度等調査結果の概要』
社宅の退去をめぐるトラブルを未然に防ぐ方法
社宅の入居期限や制限を定めていても、退去が必要になった際にスムーズに退去してもらえないケースもあります。社宅入居者とのトラブルを未然に防ぐには、退去時の対応やルールを定めておくことが重要です。
①退去ルールを定める
社宅規程では、社宅の退去ルールを定めておく必要があります。
入居期限を過ぎた場合や、「転勤して勤務地が変わる」「入居できる年齢を過ぎた」など、入居対象者から外れた場合の退去手続きについて定めます。
退去ルールとして定める項目には、以下が挙げられます。
▼退去ルール
- 退去までの猶予期間
- 退去の申請方法
- 原状回復義務
- 退去事由(転勤、退職、結婚など)
また、社宅規程に違反した場合に、企業側から退去を求められるケースについても定めておくことで、入居者とのトラブルを防止できます。
なお、社宅の原状回復義務については、無料で資料をダウンロードしていただけます。ぜひご活用ください。
②個人契約の可否を定める
社宅の入居期限が過ぎたあと、入居者の個人契約に切り替えできるかどうかについても定めておくことが重要です。
入居者のなかには、「退職するけれど、子どもの学校の都合で同じ住宅に住み続けたい」というように、入居期限が過ぎたあとも継続して住み続けることを希望する人もいます。
社宅規程には、個人契約への切り替え可否と条件について定めるとともに、名義変更の手続きや必要書類についても共有しておく必要があります。
ただし、個人契約に切り替える際には新たに入居審査が行われるため、審査に通らなかった場合は退去が必要になる点には注意が必要です。
借上社宅を個人契約に変更する方法や注意点については、こちらの記事をご確認ください。
なお、リロケーション・ジャパンでは、社宅の入居期限到来後にもご利用いただける独自サービスをご提供しております。
→【おすすめ】記事とあわせて読みたい!社員“個人”の契約でも利用できるサービス。
まとめ
この記事では、社宅の入居期限について以下の内容を解説しました。
- 入居期限の目安
- そのほかの入居継続制限
- 退去時のトラブルを防ぐための対策法
社宅を従業員に貸し出す際、5~10年の入居期限を設けている企業が多くなっています。また、入居期限ではなく、転勤者や新卒採用者などの対象者、年齢、役職などによる入居制限を設けるケースもあります。
社宅を導入する目的に応じて入居制限を設けることで、企業側のコスト軽減や従業員の不公平感の解消につながり、円滑な社宅運用ができるようになります。
ただし、退去時にトラブルが起きる可能性があるため、退去や個人契約について定めた社宅規程を作成してトラブルを未然に防ぐことが重要です。
『リロケーション・ジャパン』の社宅管理サービスは、物件探しから制度の見直しまで、社宅管理をトータルサポートしております。入居制限に関するルールの策定・運用をサポートして、円滑な社宅運用を実現します。
なお、社宅管理のアウトソーシングや委託する際のメリットについては、以下の記事で詳しく解説しています。