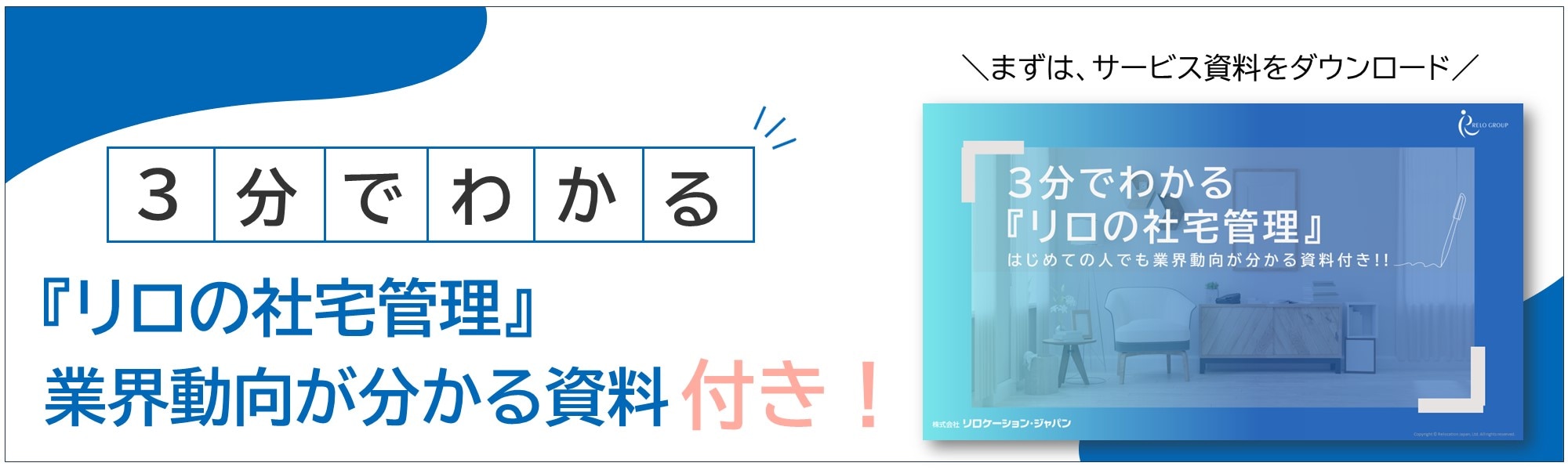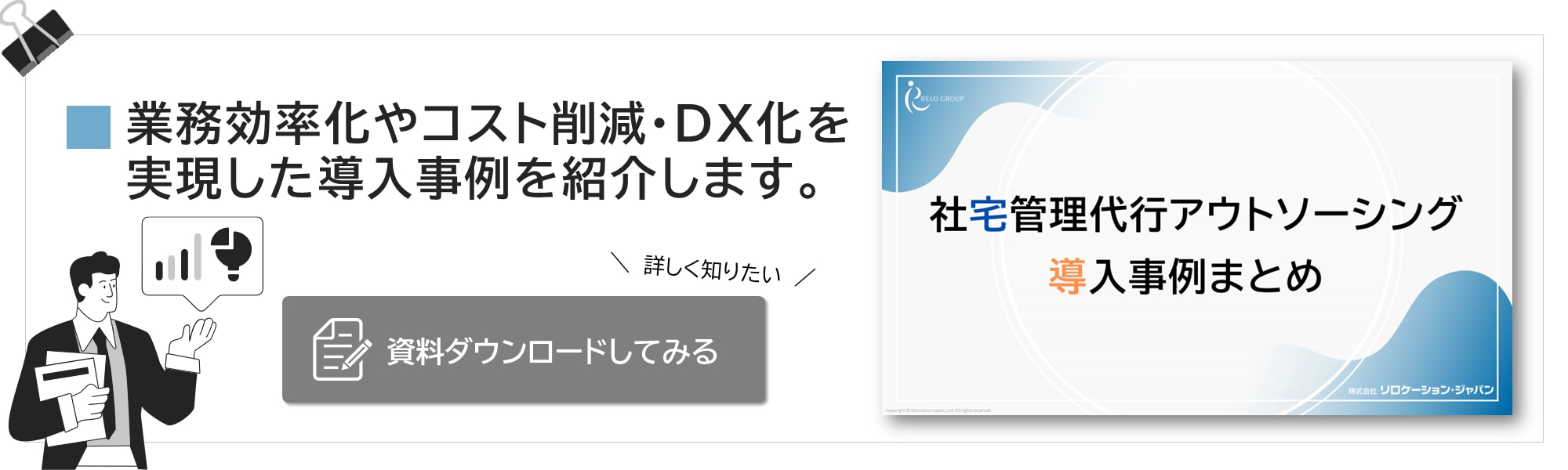社宅制度とは? 管理業務の課題はアウトソーシングの活用で解決!
社宅制度は従業員の経済的負担を軽減できることから、福利厚生の一環として導入する企業があります。従業員にとって喜ばれる社宅制度ですが、契約や更新手続き、入居者トラブルへの対応などのさまざまな業務が発生するため、社宅担当者の負担につながることも考えられます。
そこで検討したいのが、社宅管理のアウトソーシングです。人事総務部門のご担当者さまのなかには「どのような業務を委託できるのか」「自社に合ったアウトソーシングサービスをどのような基準で選ぶとよいのか」と気になる方もいるのではないでしょうか。
この記事では、社宅管理業務によくある課題やアウトソーシングを活用するメリット・デメリット、アウトソーシングサービスを選ぶときのポイントについて紹介します。社宅制度の導入を検討している担当者の方は、ぜひ参考にしてください。
目次[非表示]
→お客様にいちばん選ばれている『リロの社宅管理』サービス概要資料はこちら
社宅制度とは
社宅制度とは、従業員の住居に関する金銭的な負担を軽減することを目的に導入される法定外福利厚生の一種です。
社宅には、主に不動産管理会社や家主から賃貸物件を借りて従業員へ貸し出す“借上社宅”と、企業が所有する物件を従業員へ貸し出す“社有社宅”の2つがあります。
▼借上社宅と社有社宅の特徴
社宅の種類 | 特徴 |
借上社宅 | |
社有社宅 |
|
借上社宅の場合は、賃貸物件を借りてから従業員へ貸し出すため、物件探しや契約・更新手続きなどの業務が発生します。
社有社宅の場合は、不動産会社や家主とのやり取りはありませんが、物件の修繕・維持管理なども自社で対応する必要があります。
社宅管理に伴う主な業務には、以下が挙げられます。
▼主な社宅管理業務
これらの社宅管理業務には、専門知識が求められる業務もあるため、自社ですべての業務に対応するにはリソースやコストの負担が大きくなります。
なお、借上社宅と社有社宅の違いについてはこちらの記事で解説しています。併せてご確認ください。
社宅規程に記載する項目
社宅制度を運用する際は、社宅規程を作成する必要があります。社宅管理業務のなかでも、社宅規程を作成する業務は重要なプロセスといえます。
①入居資格
社宅制度を導入する際は、従業員間の不公平感を招かないように入居資格を明確に示すことが重要です。
一部の従業員だけが優遇されて条件のよい社宅を利用できる状態は、従業員の不満につながることがあります。合理的かつ公平な入居資格を設けることによって、統一した基準で運用できるようになります。
▼入居資格の例
- 転居を伴う転勤者
- 勤務先の近辺に自家を持たない従業員
- 独身の従業員 など
②賃貸料相当額と家賃
賃貸料相当額は、入居者から徴収する家賃(社宅使用料)に影響します。
従業員から物件に対する賃貸料相当額の50%以上に当たる家賃を徴収している場合には、賃貸料相当額と家賃の差額は非課税となります。賃貸料相当額は、以下の(1)から(3)の合計額から導き出せます。
▼賃貸料相当額を算出する項目
(1)(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2% (2)12円×(その建物の総床面積(m2)/3.3m2) (3)(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22% |
出典:国税庁『No.2597 使用人に社宅や寮などを貸したとき』
③費用負担区分
社宅制度を導入する際は、費用負担区分を明確に決めておくことが重要です。
例えば、町内会費や駐車場代などの家賃以外にかかる費用については、会社が負担するのか、入居者が負担するのかを定めておきます。すべて会社で負担するとなるとコストの負担が増えるほか、福利厚生制度としての公平性を欠くおそれがあるため、一定の基準を設けることが重要です。
また、定めた基準を超えた場合や、入居者による設備の汚損・破損があった場合など、追加で費用を徴収するケースについても定めておく必要があります。
なお、借上社宅について光熱費は従業員負担にすることが一般的ですが、社有社宅の光熱費の負担区分については、こちらの記事で解説しています。併せてご確認ください。
→【詳しく知りたい!】『リロの社宅管理』を導入・利用企業様の事例はこちら
社宅制度の管理業務によくある課題
社宅制度を運用するにあたって、次のような課題が生まれることがあります。
▼社宅制度の管理業務によくある課題
- 社宅戸数が多くなると、社宅担当者の負担が増える
- 借上社宅の場合、賃貸借契約や原状回復をめぐるトラブルが起こりやすくなる
- 通常業務のほかにも設備不良や近隣トラブルに関する対応が必要になる
管理する社宅の戸数が増えるほど、社宅担当者の負担も増え、通常業務に支障が出ることが懸念されます。
また、借上社宅の場合、賃貸借契約や退去時の原状回復をめぐって不動産会社または家主とのトラブルにつながるケースも考えられます。また、借上社宅・社有社宅ともに、室内の設備に関する不具合や近隣の入居者とのトラブルへの対応も求められます。
このような煩雑かつ負担になりやすい社宅制度の管理業務については、アウトソーシングで外部委託することも一つの方法です。
社宅管理業務の負担を軽減するアウトソーシングサービス
社宅管理業務は多岐にわたることから、社宅担当者の負担となるケースも少なくありません。社宅担当者の業務負担を削減する方法の一つに、社宅管理業務を代行するアウトソーシングサービスの活用が挙げられます。
社宅のアウトソーシングとは、自社で行っている社宅管理業務を外部の専門会社に委託することです。煩雑で負担の大きい社宅管理業務を外部に委託すると、社宅担当者がコア業務に専念しやすくなり、本来持っているリソースを最大限に生かせるようになります。
また、社宅の運用に関する知識・ノウハウを有する専門会社が対応することで、管理ミスや社宅担当者の退職による引き継ぎ不足などのリスクも防止できます。
▼アウトソースできる主な業務内容
アウトソース可能な業務 | 内容 |
物件探し |
|
契約業務 |
|
更新業務 |
|
解約業務 |
|
支払い業務 |
|
トラブル対応 |
|
社宅管理業務をアウトソースするメリット
社内で行ってきた社宅管理業務をアウトソースすることで、効率的かつ円滑に社宅制度を運用できるようになります。
①自社のコア業務に専念することができる
1つ目のメリットは、自社のコア業務に専念できることです。
社宅管理業務は多岐にわたり、戸数が増えるほど負担が大きくなり本来のコア業務を圧迫してしまう可能性があります。負担の大きい社宅管理業務をアウトソースすることで、業務負担が軽減されて自社のコア業務に専念することができます。
②不動産に関する専門知識を頼ることができる
2つ目のメリットは、不動産に関する専門知識を頼れることです。
社宅管理業務には、賃貸借契約や原状回復に関するトラブルへの対応などの専門知識が必要になる場面があります。アウトソーシングを活用すると、専門知識を持った事業者に対応してもらえるため、円滑な運用につながります。
③時期ごとの業務量の違いに対応できる
3つ目のメリットは、時期ごとの業務量の違いに対応できることです。
人事異動や新規入社の従業員が増えるタイミングで、社宅管理業務の業務量が増えることがあります。自社のみで対応する場合は、時期ごとの業務量に合わせて社宅担当者の人員を調整することが難しいこともあります。
社宅管理業務をアウトソースすれば、業務量が増える時期でも社内で人員を調整することなく、スムーズに社宅管理を行ってもらえます。
→【詳しく知りたい!】『リロの社宅管理』を導入・利用企業様の事例はこちら
社宅管理業務をアウトソースするデメリット
外部の事業者に社宅管理業務をアウトソースする際は、委託に関する費用や個人情報の取り扱いについて注意が必要です。
①アウトソーシングの委託費用が発生する
1つ目のデメリットは、委託費用が発生することです。
社宅管理業務を外部の事業者に委託する場合には、継続的に委託費用が発生します。アウトソーシングで社内業務を効率化することによるコストの削減効果と、事業者に支払うコストを比較したうえで判断する必要があります。
②個人情報漏えいのリスクがある
2つ目のデメリットは、個人情報漏えいのリスクがあることです。
社宅管理業務を委託する場合、社宅を利用する従業員の個人情報についてもアウトソーシングの事業者が管理することになります。個人情報が安全な環境で管理されていない場合には、自社の知らないところで情報漏えいが発生するリスクがあります。
アウトソーシングを活用する場合は、委託する事業者のセキュリティ管理やコンプライアンス管理の体制を事前に確認しておくことが重要です。
自社に合ったアウトソーシングサービスを選ぶポイント
アウトソーシングの事業者によって、委託形態や依頼できる業務の範囲などが異なります。自社の課題やリソースに応じて、社宅管理のアウトソーシングサービスを選ぶことがポイントです。
①業務の委託形態に応じて選ぶ
社宅管理のアウトソーシングサービスでは、委託形態に種類があります。運用する社宅の種類や委託したい業務の範囲などに応じて選択することが必要です。
▼業務の委託形態
社宅の種類 | 委託形態 | |
借上社宅 | 転貸方式 | アウトソーシング事業者と包括転貸借契約を交わして、借上社宅の管理運用に関する業務を一括で委託する方法 |
代行方式 | アウトソーシング事業者と業務委託契約を交わして、借上社宅の管理運用に関する業務の一部を代行してもらう方法 | |
社有社宅 | アウトソーシング事業者と業務委託契約を交わして、社有社宅の管理運用に関する業務の一部またはすべての代行を依頼する方法 | |
②社宅制度の設計から依頼できる事業者を選ぶ
社宅制度の運用を開始する際には、社宅規程の作成や運用体制の構築などの準備が必要になります。また、社宅の入居・退去に関する管理や社宅使用料の徴収などをスムーズに行える仕組みを整えることも必要です。
社宅制度の設計・構築や社宅規程の策定から支援可能なアウトソーシング事業者もあります。自社での制度設計が難しい場合には、社宅の管理業務以外のサポートがあるかどうかを確認しておくことがポイントです。
③効果が出なければリプレイスを行う
「すでにアウトソーシングを活用しているけれど、思うように効果が出ていない」という場合には、アウトソーシング事業者のリプレイス(切り替え)を検討することも一つの方法です。
以下のような問題が生じている場合には、アウトソーシング事業者のリプレイスを検討するほうがよいと考えられます。
▼リプレイスの検討が必要な問題の例
- 入居している従業員から社宅管理に関する苦情が寄せられる
- 物件探しから入居までに時間を要する
- 入居したい時期に間に合わない、対応が遅いなどのトラブルが多い
リプレイスを行う際は、複数の事業者を比較検討して自社の課題・ニーズに沿った対応をしてもらえるか、質の高い管理を行ってくれるかなどを確認することがポイントです。
アウトソーシング事業者のリプレイスについては、こちらの記事で詳しく解説しています。併せてご確認ください。
→お客様にいちばん選ばれている『リロの社宅管理』サービス概要資料はこちら
まとめ
この記事では、社宅制度と社宅管理業務のアウトソーシングについて、以下の内容を解説しました。
- 社宅制度の概要
- 社宅規程に記載する項目
- 社宅制度の管理業務によくある課題
- 社宅管理業務の負担を軽減するアウトソーシングサービス
- 社宅管理業務をアウトソースするメリット・デメリット
- 自社に合ったアウトソーシングサービスを選ぶポイント
社宅制度の運用にあたっては、物件探しや契約手続き、入居・退去に関する管理、支払い管理などのさまざまな業務が発生します。煩雑化しやすい社宅管理業務の負担を削減して、コア業務に専念するには、アウトソーシングサービスを活用することが有効です。
ただし、アウトソーシングサービスによって委託形態や対応できる業務の範囲、管理の品質などが異なります。導入する際は、複数の事業者を比較検討したうえで自社の課題・ニーズに沿った運用ができるサービスを選ぶことがポイントです。
『リロケーション・ジャパン』の社宅管理サービスは、借上社宅の転貸方式によるフルアウトソーシングや社有社宅の運用代行に対応しています。社宅管理業界でのトップクラスの実績を基に、貴社の課題に応じたサポートを行います。
「社内のリソースだけでは社宅の管理が大変」「円滑な社宅運用で従業員の満足度を高めたい」という方は、こちらからお問い合わせください。