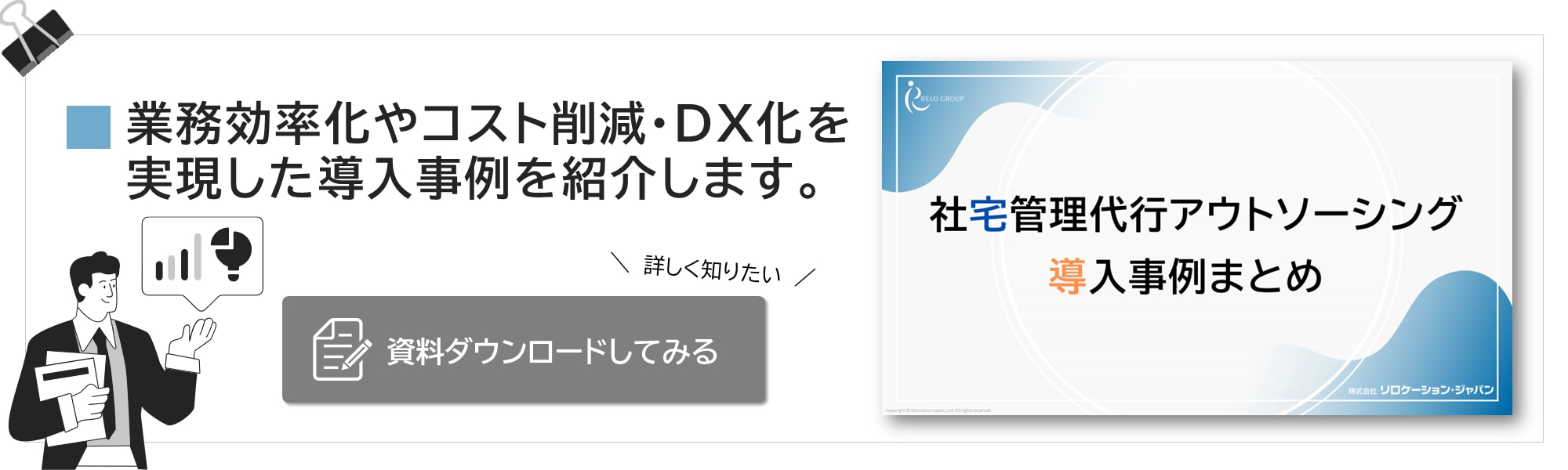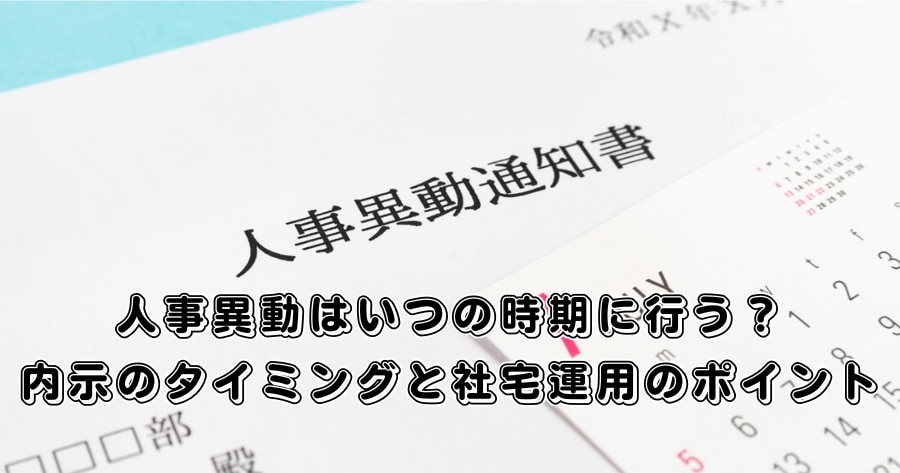
人事異動はいつの時期に行う? 内示のタイミングと社宅運用のポイント
従業員の人事異動が決まると、後任者への引き継ぎや関係者への連絡などのさまざまな業務手続きが必要になるほか、転居を伴う場合には新居と引越しの準備も進める必要があります。
社宅制度を導入している場合は、従業員が転居先の社宅へとスムーズに引越しできるように、手続きやサポートを行うことが求められます。
人事総務部門のご担当者さまのなかには、「人事異動の内示はどのタイミングで行えばよいのか」「社宅への転居をスムーズに進めるために何をすればよいのか」と気になる方もいるのではないでしょうか。
この記事では、一般的な人事異動の時期と内示のタイミング、社宅への転居をスムーズに進めるポイントについて解説します。
→【おすすめ!】借上げ社宅管理の業務改善方法とは?詳しく知りたい。
目次[非表示]
人事異動とは
人事異動とは、企業が従業員の職務内容、勤務地、役職などを計画的に変更することを指します。適材適所の原則に基づき、従業員の能力や適性、そして組織が求めるスキルを合致させることで、企業全体の生産性向上を目指します。
主な人事異動の種類には、配置転換、昇進・降格、そして出向・転籍などがあります。これらの異動は、組織の成長段階や事業計画の変更に合わせて戦略的に実行されます。
特に転勤を伴う異動は、従業員の生活環境に大きな影響を与えるため、企業には労働契約法や就業規則に基づいた、十分な配慮と手続きが求められます。
人事異動が多い時期はいつ?
人事異動は、会社の決算時期に合わせて行われることが一般的です。民間企業において人事異動が最も多く実施される時期は、一般的に4月と10月の年2回とされています。この時期に集中する背景には、企業の事業計画や会計年度の区切りが深く関わっています。
4月は多くの企業で新年度が始まるタイミングであり、新卒入社の従業員を組織に迎え入れるとともに、前年度の実績に基づいた大規模な組織改編や事業戦略の変更が行われます。これに伴い、昇進・昇格や配置転換なども集中し、全社的な異動が多く発生する傾向にあります。
一方、10月は企業の多くで下半期が始まるタイミングであり、上半期の実績を踏まえた事業計画の微調整や、急な欠員補充、新たなプロジェクトの発足などに合わせて中規模な異動が実施されることが一般的です。
なお、不動産会社の繁忙期・閑散期についてはこちらの記事をご確認ください。
公務員の人事異動の時期と特徴
公務員の人事異動も民間企業と同様に4月が最も多い時期とされています。これは、国の行政機関や地方自治体の年度初めが4月であり、予算編成や組織体制が刷新される時期と一致するためです。
公務員の人事異動の大きな特徴は、定期的なローテーションがルール化されている場合が多い点です。多くの自治体や機関では、概ね2~4年といったスパンで部署やポストを異動する仕組みが確立されています。
人事担当者は、このローテーションのルールに基づき、各職員のキャリアパスを考慮しながら異動計画を策定します。
人事異動の内示を行うタイミングと注意点
人事異動の内示は、正式な発令に先立ち、異動対象者へ事前に事実を伝える重要なプロセスです。
この内示のタイミングは、従業員が準備する時間を確保し、不安を軽減するうえで大きな役割を果たします。
内示の一般的な通知タイミング
内示は、一般的に異動発令日の1ヶ月前に通知する企業が多いとされています。これは、労働契約法や就業規則において、従業員に不利益を与えないよう、業務の引き継ぎや私的な準備のための合理的な期間を確保することが求められるためです。
しかし、引越しを伴う転勤の場合は、1ヶ月前の通知では準備期間として不十分になるケースがほとんどです。新居の選定、引越し会社の手配、子どもがいる場合は転校手続きなど、従業員とその家族が行う作業は多岐にわたります。そのため、転勤を伴う内示については、発令日の1ヶ月半〜2ヶ月前を目安に通知することが望ましいです。
内示を受ける従業員側の気持ちと企業が配慮すべきこと
内示を受けた従業員は「新たなチャレンジへの期待」と「環境変化への不安」という二つの相反する感情を抱えます。期待感がある一方で、新しい環境への適応、業務内容の変化、そして大きな不安として、転居を伴う場合は生活環境の激変に対するストレスを感じやすいものです。この不安やストレスが、内示に対する拒否感やモチベーション低下の原因となります。
企業は、以下の点についてきめ細やかな配慮を行うことで、従業員の不安を軽減し、異動を円滑に進めることができます。
まず、内示の際には、なぜその異動が必要なのかという目的を従業員個人に対して丁寧に説明することが不可欠です。次に、不安を具体的に解消するため、異動先の上司との面談機会の設定や、住宅・引越しに関するサポート体制(社宅制度の詳細、引越し費用の補助範囲など)を明確に提示することが求められます。
人事異動による社宅への転居をスムーズに進めるポイント
転居先で社宅の利用を希望する場合には、従業員の時間と経済的な負担を配慮して手続きを進めることが重要です。
①転勤に伴う従業員の大きな負担(時間的・精神的)
転勤が決まった従業員は、通常の業務の引き継ぎに加え、引越し先での生活基盤を短期間で構築しなければなりません。
具体的には、引越し会社や新居の手配、役所への転出・転入手続き、金融機関や各種保険の住所変更、子どもの転校・転園手続きなど、多岐にわたる煩雑な作業を限られた期間で行う必要があります。
また、転勤に伴う生活環境の変化は、従業員本人だけでなく家族にも大きなストレスを与えることが指摘されています。企業はこれらの時間的・精神的な負担を最小限に抑えるため、社宅関連業務のサポートを徹底し、従業員がコア業務の引き継ぎに集中できる環境を整える必要があります。
②社宅利用のフローを共有する
人事異動が決まった従業員に対して、社宅の利用に関する手続きのフローをマニュアルや社内ポータルサイトなどで共有しておく必要があります。社宅に入居するまでの手続きについては、社有社宅と借上社宅で異なります。
▼社有社宅
- 従業員が人事総務部門へ社宅利用の申請を行う
- 社宅担当者が申請内容を確認して、入居条件を満たす場合に承認を行う
- 社宅の費用負担や社宅規定などを記載した社宅使用誓約書を従業員と締結する
- 入居開始日までに鍵を受け取り引越しを行う
▼借上社宅
- 従業員が人事総務部門へ社宅利用の申請を行う
- 社宅担当者または従業員が入居条件を満たす賃貸物件を探す
- 社宅の費用負担や社宅規定などを記載した社宅使用誓約書を従業員と締結する
- 不動産会社で賃貸物件の内見と申し込みを行う
- 賃貸物件の審査に通過したら、賃貸借契約書を締結する
- 入居開始日までに鍵を受け取り引越しを行う
借上社宅の物件探しについては、社宅担当者が行う場合のほか、従業員自身が賃貸物件を探して入居条件を満たす際に企業が承認を行う場合があります。
また、賃貸物件の内見は、現地に足を運んで確認する方法だけでなく、オンラインで実施する、または実施しない場合もあります。
借上社宅の社内申請フローや社宅使用誓約書の内容については、こちらの記事で解説しています。
賃貸物件の内見ができない場合の対処方法については、こちらの記事をご確認ください。
③住所変更に伴う手続きのマニュアルを作成する
社宅の利用に関するフローに加えて、住所変更に伴って従業員側で行う必要がある手続きについても、マニュアルを作成・共有しておくことが重要です。
いつまでに何をするかをマニュアルにまとめておくと、従業員が計画的に転居の準備を進めやすくなります。
▼住所変更に伴う主な手続き
- 役所への住民異動届の提出
- 公的証明書・資格証などの住所変更(マイナンバーカード、運転免許証、車庫証明書、介護保険被保険者証、国民健康保険証、パスポート など)
- 子どもがいる場合、転園・転校の手続き
- 現住居での退去通知(賃貸物件の場合)
- 引越し日までの不良品の処分と荷造りの準備
住所変更の手続きや引越しが決まったときにやることについては、こちらの記事でまとめています。
④引越し会社の手配や家具・家電の準備をサポートする
人事異動に伴う転居については従業員の負担となるため、企業が引越し会社の手配や家具の準備などをサポートすることも見当が必要です。
引越し会社の手配を代わりに行ったり、費用を一部または全部負担したりすることで、従業員側の労力や金銭的な負担を抑えられます。
また、転居先で新たに一人暮らしを始める従業員もいます。生活に必要な家具・家電を購入する際には、20〜30万円ほどの費用がかかります。企業で社宅の家具・家電を用意することで、従業員の金銭的な負担が削減されて満足度の向上にもつながると考えられます。
なお、引越し費用の負担割合や家具・家電つき社宅のメリット・デメリットについては、こちらの記事で解説しています。
→【おすすめ!】記事とあわせて読みたい「家具・家電付き社宅の導入メリットとは」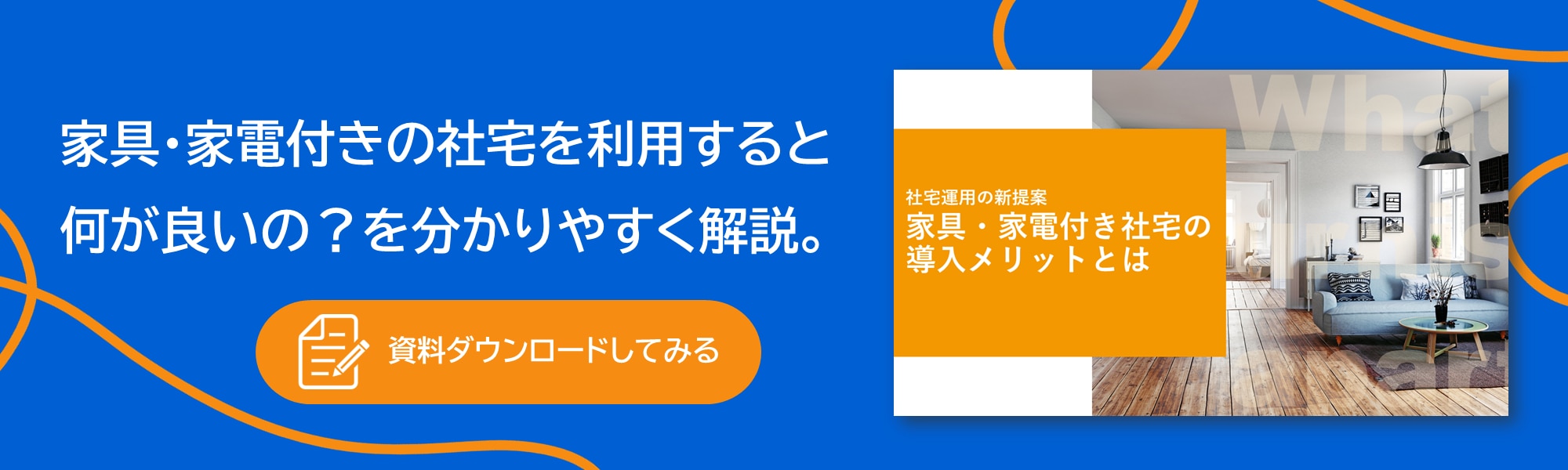
転勤・社宅手続きの煩雑さを解消する「社宅管理代行サービス」
人事異動に伴う煩雑さを解消し、より戦略的な人事管理を実現するための有効な解決策が「社宅管理代行サービス」の利用です。
社宅業務における人事業務担当者の課題
人事異動の集中する時期、人事・総務担当者は通常の採用や研修といったルーティン業務に加え、社宅関連の大量かつ専門的な事務作業に追われます。煩雑な業務に担当者が多くの時間を割かれることで、本来注力すべき人材育成や人事戦略の立案といったコア業務が疎かになってしまうという本質的な問題が生じています。
▼主な課題
- 社宅物件の探索、不動産会社との契約交渉など、専門的な事務作業の集中
- 法令の改訂に沿った社宅規定のアップデートと適切な運用
- ガバナンスとコンプライアンスの強化の管理体制構築
社宅管理代行サービスが解決できること
社宅管理代行サービスは、人事・総務担当者が抱えるこれらの課題を一挙に解決するアウトソーシングの仕組みです。代行会社は、社宅関連業務の専門知識とノウハウを活用し、企業に代わって一連の業務を遂行します。
- 入居・退去時の手続き、賃料精算、修繕対応といった業務負担の軽減
- 契約内容の適正化によるコンプライアンスの徹底
- 退去時の原状回復費用交渉によるコスト削減
社宅制度を従業員満足度向上に活かす方法
社宅制度は、単なる住宅補助ではなく、優秀な人材の確保や定着に直結する重要な福利厚生です。社宅管理代行サービスを導入することは、この社宅制度の価値を最大限に高めることにつながります。
代行サービスを利用することで、従業員は自分で物件を探したり、煩雑な契約手続きに時間を費やす必要がなくなり、手間なくスムーズに新居に入居できるようになります。結果として、転勤に伴う精神的・時間的なストレスを軽減でき、企業へのエンゲージメント向上に直結します。
まとめ
この記事では、人事異動に伴う社宅への転居について以下の内容を解説しました。
- 人事異動とは
- 人事異動が多い時期
- 公務員の人事異動の時期と特徴
- 人事異動の内示を行うタイミングと注意点
- 人事異動による社宅への転居をスムーズに進めるポイント
- 転勤・社宅手続きの煩雑さを解消する「社宅管理代行サービス」
人事異動は、3月と9月の決算時期に合わせて行われることが多く、異動の2週間〜1ヶ月前に対象の従業員へ内示することが一般的とされています。
従業員が人事異動に伴い社宅を利用する場合には、社宅申請のフローや住所変更に伴う手続きのマニュアルを作成・共有するとともに、引越し会社の手配や、家具・家電の準備をサポートすることがポイントです。
『リロケーション・ジャパン』の社宅管理サービスでは、包括転貸方式による社宅運用のフルアウトソーシングを行っています。転勤先での物件探しや賃貸借契約、引越し会社の手配、家具家電の貸与など、幅広い業務についてトータルサポートしています。
サービスの詳細については、こちらからお問い合わせください。