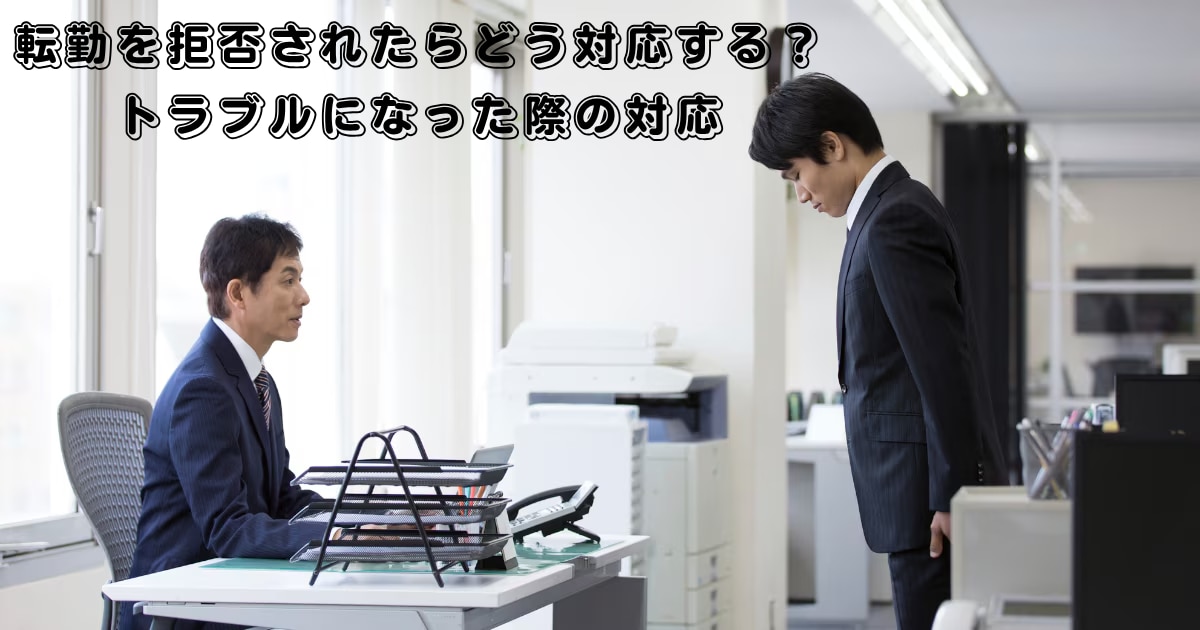
転勤を拒否されたらどう対応する? トラブルになった際の対応
※2025年9月18日更新
転勤制度は、人材の育成や従業員の適性・能力を発揮できる人材配置を行い、組織力の強化を図るためにさまざまな企業で取り入れられています。
しかし、勤務場所や居住地が変わることへの不安、育児・介護といった家庭の事情などにより、転勤の辞令を拒否する従業員もいると考えられます。
人事総務部門のご担当者さまのなかには「転勤を拒否されたらどうすればよいのか」「トラブルを防ぐためにできることはあるか」と悩まれている方もいるのではないでしょうか。
この記事では、転勤を拒否する従業員への対応方法や辞令を出す際の注意点について解説します。
なお、転勤のスケジュールについてはこちらの記事で解説しています。
→面倒な社宅管理業務をまるっとお任せしたい。サービス概要資料はこちら!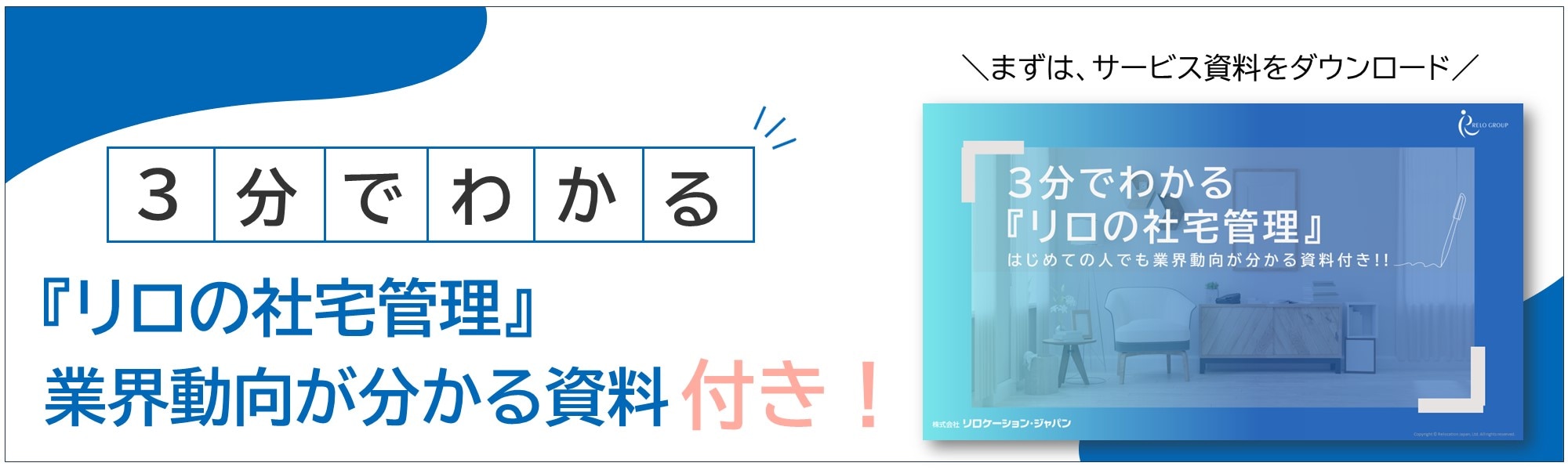
目次[非表示]
- 1.転勤命令に関する原則
- 2.従業員による転勤の拒否が認められるケース
- 2.1.雇用契約書や就業規則に転勤命令の規定がない
- 2.2.雇用契約において勤務地が限定されている
- 2.3.転勤に業務上の必要性がない
- 2.4.不当な動機・目的で転勤命令を濫用している
- 2.5.従業員の持病に悪影響をおよぼす可能性がある
- 2.6.重度の病気・障がいを持つ家族の看病・介護を行う必要がある
- 3.転勤命令に伴うトラブルにつながりやすいケース
- 3.1.単身赴任が発生する
- 3.2.通勤時間が長くなる
- 3.3.転勤する従業員が持ち家を所有している
- 4.転勤の拒否に対する懲戒解雇の可否
- 5.転勤を拒否する従業員への対応
- 5.1.➀転勤の理由を説明する
- 5.2.②転勤によるメリットを伝える
- 5.3.③転勤を拒否する理由の解消方法を探る
- 5.4.④物件探しや引越しをサポートする制度を設ける
- 5.5.⑤勤務地限定の従業員として雇用契約を結び直す
- 6.転勤の辞令に関する注意点
- 6.1.労働契約や就業規則を確認する
- 6.2.適切な期間を定めて内示を行う
- 6.3.個別の事情に配慮する
- 7.まとめ
転勤命令に関する原則
日本の多くの企業では、就業規則や雇用契約書に「会社の業務上の必要があれば転勤を命じることができる」といった規定が設けられています。
この場合、従業員は原則として転勤命令に従う義務があります。
しかし、すべての転勤命令が無条件に有効というわけではありません。判例では、転勤命令が権利の濫用にあたる場合や、従業員の個別事情を無視した場合には、無効とされることもあります。
転勤命令の有効性は、雇用契約や就業規則の内容、転勤の必要性、従業員の事情などを総合的に判断して決まります。
出典:厚生労働省『配置転換』
従業員による転勤の拒否が認められるケース
従業員が転勤命令を拒否できるのは、法律や判例で認められた特別な事情がある場合に限られます。
例えば、雇用契約や就業規則に転勤に関する明確な規定がない場合や、勤務地が限定されている場合、または転勤命令が業務上の必要性を欠いていたり、不当な目的で発令された場合などです。
さらに、従業員やその家族の健康や生活に重大な影響が及ぶ場合も、転勤拒否が認められることがあります。
雇用契約書や就業規則に転勤命令の規定がない
雇用契約書や就業規則に転勤命令に関する明確な規定がない場合、会社は従業員に一方的に転勤を命じることができません。
このような場合、従業員が転勤を拒否しても、就業規則違反や契約違反にはなりません。
会社側は、転勤命令の根拠となる規定を示す必要があり、規定がなければ転勤命令自体が無効となる可能性が高いです。
従業員は、自分の雇用契約書や就業規則を確認し、転勤に関する条項があるかどうかをチェックしましょう。
雇用契約において勤務地が限定されている
雇用契約書に「勤務地は○○支店に限定する」など、勤務地が明確に限定されている場合、会社は原則としてその従業員に対して他の勤務地への転勤を命じることはできません。
このような契約内容がある場合、従業員が転勤を拒否しても、契約違反にはなりません。
勤務地限定の契約は、特に地域限定社員や家庭の事情を考慮した雇用形態で多く見られます。また、会社側が転勤を命じる場合は、従業員の同意が必要となるため、無理に転勤を強要することはできません。
転勤に業務上の必要性がない
転勤命令には、業務上の合理的な必要性が求められます。例えば、単なる人員整理や嫌がらせ目的での転勤命令は、権利の濫用とみなされる可能性があります。
また、業務内容がほとんど変わらないのに遠方への転勤を命じる場合なども、業務上の必要性が認められないケースがあります。
このような場合、従業員は転勤命令を拒否できる可能性が高いため、会社側は、転勤の目的や必要性を明確に説明する責任があります。
不当な動機・目的で転勤命令を濫用している
転勤命令がパワハラや退職強要、特定の従業員を排除する目的など、不当な動機や目的で発令された場合は権利の濫用として無効となります。
判例でも、会社が従業員に不利益を与えるためだけに転勤を命じた場合、その命令は認められないとされています。従業員は、転勤命令の背景や理由に不審な点がある場合、会社に説明を求めたり、労働組合や労働基準監督署に相談することが重要です。
出典:厚生労働省『転勤に関する裁判例』
従業員の持病に悪影響をおよぼす可能性がある
従業員が持病を抱えており、転勤先での生活や業務が健康に重大な悪影響を及ぼす場合、転勤命令を拒否できる可能性があります。
例えば、特定の医療機関での治療が必要な場合や、気候や環境の変化が健康に悪影響を与える場合などです。
このような事情がある場合は、医師の診断書などを提出し、会社に配慮を求めることが大切です。会社側も、従業員の健康状態を十分に考慮しなければなりません。
重度の病気・障がいを持つ家族の看病・介護を行う必要がある
家族に重度の病気や障がいを持つ方がいて、看病や介護が必要な場合も、転勤命令を拒否できる可能性があります。
家庭の事情によっては、転勤によって家族の生活や健康に深刻な影響が及ぶことがあるため、判例でも一定の配慮が求められています。
会社に事情を説明し、必要に応じて証明書類を提出することで、転勤命令の見直しや配慮を求めることができます。
転勤命令に伴うトラブルにつながりやすいケース
転勤命令は、従業員の生活や家族に大きな影響を与えるため、さまざまなトラブルの原因となることがあります。
特に、単身赴任や通勤時間の大幅な増加、持ち家の問題など、従業員の生活基盤に関わるケースでは、転勤命令に対する不満や拒否が生じやすくなります。
会社側は、こうしたトラブルを未然に防ぐためにも、従業員の個別事情に十分配慮し、丁寧な説明やサポートを行うことが重要です。以下に、トラブルにつながりやすい代表的なケースを紹介します。
トラブルの要因 | 主な影響 |
単身赴任 | 家族分離・精神的負担 |
通勤時間の増加 | 健康・家庭生活への悪影響 |
持ち家の所有 | 住宅ローン・家族の生活への影響 |
単身赴任が発生する
転勤によって家族と離れて単身赴任を余儀なくされる場合、従業員やその家族に大きな負担がかかります。
特に小さな子どもがいる家庭や、配偶者が仕事をしている場合は、家族の生活に深刻な影響を及ぼすことがあります。
また、単身赴任では二重生活による経済的負担も問題となります。家族の生活費に加え、赴任先での住居費・光熱費・食費などが発生し、家計を圧迫するケースも少なくありません。
会社は、単身赴任手当や帰省旅費の支給、家族帯同の選択肢など、従業員の負担を軽減するための制度を整えることが求められます。
単身赴任者へのフォローについてはこちらの記事をご確認ください。
→【おすすめ!】記事と合わせて読みたい。物流業界の今!社宅引越しに与える影響について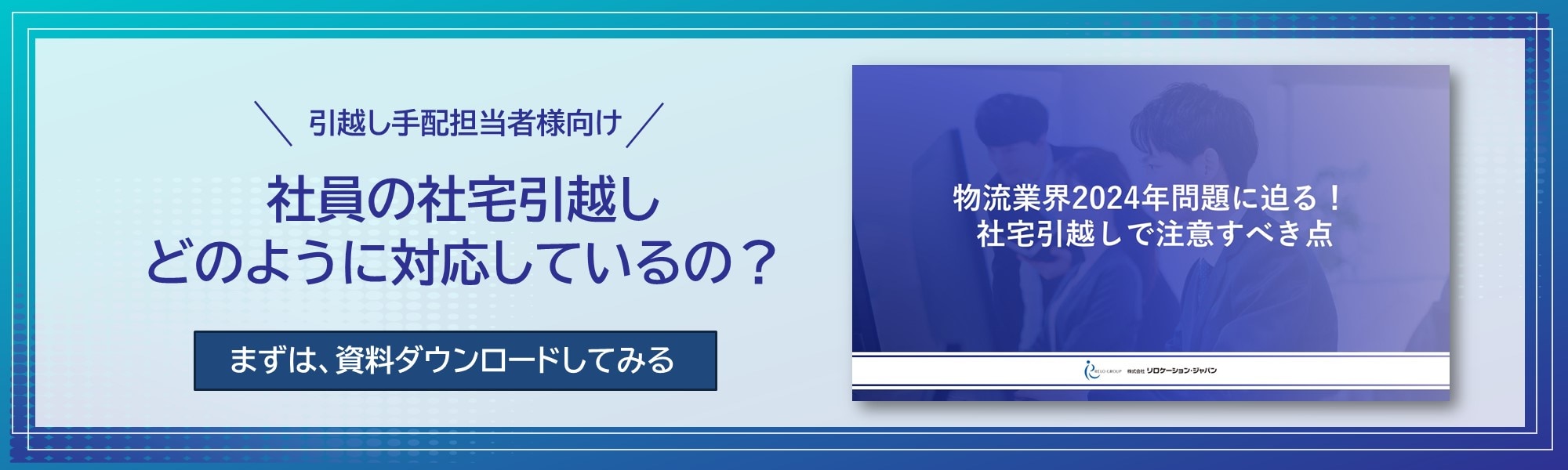
通勤時間が長くなる
転勤によって通勤時間が大幅に長くなる場合、従業員のワークライフバランスが崩れ、健康や家庭生活に悪影響を及ぼすことがあります。
特に、公共交通機関の便が悪い地域や、長距離通勤を強いられる場合は、転勤命令に対する不満が高まりやすいです。
会社は、通勤手当の増額やフレックスタイム制度の導入、在宅勤務の活用など、従業員の負担を軽減するための配慮が必要です。
転勤する従業員が持ち家を所有している
転勤対象の従業員が持ち家を所有している場合、転勤によって住宅ローンや家の管理、家族の生活などに大きな影響が出ます。
特に、ローン残高がある場合や、子どもの進学・親の介護など家庭事情を抱えている場合は、転居を伴う転勤に強い抵抗感を持つ従業員も少なくありません。
持ち家を手放すか、家族を残して単身赴任するかなど、経済的・精神的に大きな負担を伴う選択を迫られることになり、企業とのトラブルにつながるリスクもあります。
このような場合、会社は住宅手当や転居費用の補助、持ち家の賃貸サポートなど、従業員の負担を軽減するための支援策を検討することが重要です。
マイホームを持つ転勤者へのサポートについてはこちらの資料をご確認ください。
→【チェック!】マイホームを持つ社員向け転勤者サポートサービスについて知りたい。 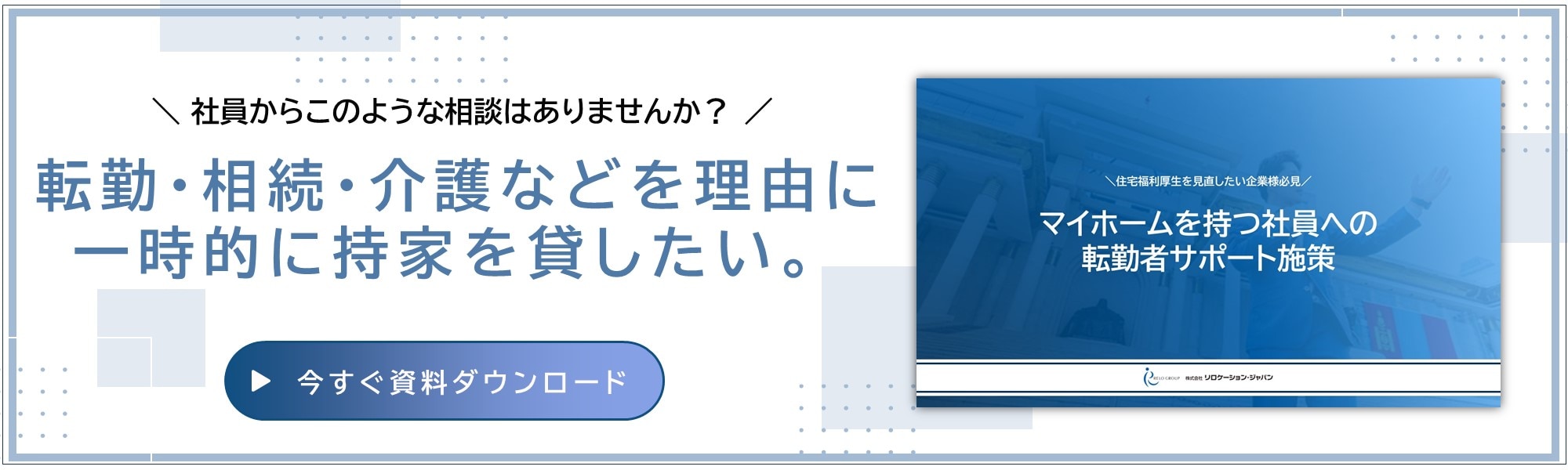
転勤の拒否に対する懲戒解雇の可否
転勤命令を正当な理由なく拒否した場合、会社は懲戒処分や最終的には懲戒解雇を検討することがあります。
ただし、懲戒解雇が認められるのは、就業規則や雇用契約に転勤命令の根拠があり、かつ従業員が正当な理由なく命令に従わなかった場合に限られます。また、懲戒解雇は労働者にとって非常に重い処分であるため、裁判所でも厳格に判断されます。
会社は、転勤命令の必要性や従業員の事情を十分に考慮し、段階的な対応を行うことが求められます。
一方、従業員側も拒否の理由が正当かどうかを冷静に判断し、必要に応じて専門家に相談することが重要です。
状況 | 懲戒解雇の可否 |
正当な理由なく転勤拒否 | 可能性あり |
正当な理由あり | 不可 |
転勤を拒否する従業員への対応
転勤は、使用者の人事権に基づいて行われるため、正当な理由がない限り従業員が辞令を拒否することはできないとされています。
従業員が転勤を拒否する場合には、「基本的に拒否はできない」旨を伝えるとともに、人事異動の不満・不安を取り除くためのフォローを行うことが求められます。
対応策 | 期待できる効果 |
転勤理由の説明 転勤の背景や目的を具体的に伝え、従業員が納得できる情報を提供する | 納得感の向上 人事異動の意図を理解することで、前向きに受け入れやすくなる |
メリットの提示 給与・役職・キャリア形成などの利点を明確に示す | モチベーション向上 将来の成長や待遇改善を実感でき、転勤意欲が高まる |
転勤拒否の理由解消 家族・介護・プロジェクト事情などを把握し、解決策を一緒に検討する | 不安・懸念点の解消 個別の事情を尊重し、安心感を得ることで受け入れやすくなる |
サポート制度 社宅貸与や費用補助、引越し・転園などを制度として用意する | 不安・負担の軽減 経済的・時間的負担が減り、転勤に前向きになれる |
勤務地限定契約 どうしても難しい場合は勤務地を限定した契約に切り替える | 定着率の向上 生活環境を守りつつ、人材を活かし続けられるため定着率が向上する |
➀転勤の理由を説明する
従業員への内示・辞令を行う際は、「なぜ転勤をしてもらいたいのか」といった理由を具体的に説明する必要があります。
▼転勤理由の例
- 現在と異なる現場でスキルを磨いてほしい
- これまでの経験や能力を生かして新規事業のリーダーになってほしい
- 事業拡大に伴ってエリアでの人員を増やしたい など
転勤の対象者に選んだ背景や新たな職場での役割、期待していることなどを説明することで、従業員が人事異動を前向きに捉えられるようになります。
その結果、拒否していた従業員に転勤を受け入れてもらえることが期待できます。
②転勤によるメリットを伝える
転勤によるメリットを伝えることも重要といえます。従業員のなかには「転勤しても大変なだけではないのか」と不安を持つ人もいます。
従業員のモチベーションを高めるメリットを提示することで、円満に転勤を受け入れてもらいやすくなります。
▼転勤によるメリットの例
- 給与・賞与の増額
- 役職手当の付与
- キャリア形成に役立つスキルの習得
- 転勤者を対象とした福利厚生の利用 など
③転勤を拒否する理由の解消方法を探る
転勤を拒否する従業員には、「なぜ拒否するのか」といった理由を聞き、懸念点を解消できる方法はないか一緒に探ることも重要です。
▼従業員が転勤を拒否する理由と解決策の提案例
転勤を拒否する理由 | 解決策の提案例 |
子どもが小さく、家族と離れて暮らすのが難しい | 家族で入居できる社宅を提供して、入園手続きをサポートする |
現在着手中のプロジェクトがあり、自分の手で最後までやり遂げたい | 転勤の時期を調整する |
親の介護をしており、実家から離れられない | 要介護認定の手続きや、通所型または入居型の介護施設を利用する選択肢について伝える |
従業員が抱える不安や懸念点を解消できれば、転勤に納得してもらえることが期待できます。
④物件探しや引越しをサポートする制度を設ける
転勤先での物件探しや引越しをサポートする制度を設ける方法があります。
転居を伴う転勤では、現在の職場で引き継ぎをしながら物件探しや引越しの手続きを進める必要があり、従業員の負担になります。
「時間や金銭的な理由で転勤したくない」と考える人もいるため、できる限り負担を抑えられるように企業がサポートすることが必要です。
▼転勤をサポートする制度の例
- 社宅の貸与
- 家賃補助の支給
- 引越し費用の補助
- 赴任旅費の支給
- 帰省手当の支給
- 転園・転学費用の補助 など
なお、転勤時に必要な手続きや手当についてはこちらの記事で解説しています。
⑤勤務地限定の従業員として雇用契約を結び直す
どうしても転勤が難しい従業員に対しては、勤務地限定の雇用契約に切り替えることも一つの方法です。
この場合、昇進や給与などの処遇に違いが生じることもありますが、従業員の生活や家庭の事情を尊重した柔軟な対応が可能となります。また、勤務地を固定することで通勤や生活環境が安定し、従業員のモチベーションや定着率向上にもつながります。
さらに、企業にとっても、経験やスキルを持つ人材を活かし続けられるため、人材流出のリスクを抑えられるというメリットがあります。
特に、育児・介護・配偶者の転勤など、ライフステージに応じた柔軟な働き方を求める従業員が増えているなかで、勤務地限定の雇用契約は有効な選択肢といえます。
▼従業員と企業のメリット
対象 | メリット |
従業員 |
|
企業 |
|
会社と従業員が合意の上で契約内容を見直すことで、双方にとって納得のいく解決策を見つけることができます。
転勤の辞令に関する注意点
転勤の辞令を出す際は、法令を遵守できているかを確認するとともに、従業員の事情を踏まえて内示や個別対応を行うことが重要です。
労働契約や就業規則を確認する
使用者の人事権として転勤の辞令を出すには、労働契約や就業規則に転勤に関する規定を定めている必要があります。転勤の辞令が認められないケースには、以下が挙げられます。
▼転勤の辞令が認められないケース
- 労働契約や就業規則に転勤についての記載がない
- 職種・勤務地を限定する規定があり、その範囲外で転勤の辞令を出す など
人事異動の目的が不当な場合や、業務において必要性がない転勤についても認められない可能性があるため、注意が必要です。
なお、2024年4月からは労働条件の明示に関する制度が改正されており、新たに追加された明示事項の一つに“就業場所・業務の変更範囲”が含まれています。
出典:厚生労働省『2024年4月から労働条件明示のルールが変わりました』
適切な期間を定めて内示を行う
転勤の対象となる従業員には、転勤までの時間に余裕を持ち、適切な期間を定めて内示を行います。
転居を伴う転勤では、物件探しや引越しの手配、子どもの転園・転学申請などのさまざまな手続きが発生します。
従業員の負担が増えないように、転勤の1ヶ月前くらいには内示を行うことが必要です。特に家族と一緒に引越しをする場合には、1〜6ヶ月前に余裕をもって内示を行うことが望ましいといえます。
なお、転勤の時期や内示のタイミングについてはこちらの記事で解説しています。
個別の事情に配慮する
転勤の辞令を出す際は、個別の事情に配慮することが求められます。
出産や育児、介護、療養中の病気などの関係でどうしても転居が難しい場合には、事情に応じて以下の対応を検討します。
▼転勤が難しい場合の対応例
- 企業が保育・介護・医療サービスの使用料を補助する
- 転勤の時期をずらす
- 現住居から通勤可能な範囲での異動で代替する
- 配偶者の転勤先を考慮して勤務地を調整する など
また、定期的に従業員へのヒアリングを行い、転勤の支障となる事情がないかを確認しておくと、候補者の選定や転勤の時期・場所の調整を行いやすくなります。
加えて、『育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(育児・介護休業法)』第26条では、事業主は従業員からの申出があった場合、育児や家族介護に支障を及ぼす配置転換(転勤等)について、その実施に配慮する義務があると定められています。
▼育児・介護休業法 第26条
(労働者の配置に関する配慮)第二十六条 事業主は、その雇用する労働者の配置の変更で就業の場所の変更を伴うものをしようとする場合において、その就業の場所の変更により就業しつつその子の養育又は家族の介護を行うことが困難となることとなる労働者がいるときは、当該労働者の子の養育又は家族の介護の状況に配慮しなければならない。
引用元:e-Gov 法令検索『育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律』
このため企業は、単なる福利厚生的な配慮にとどまらず、法的義務としても従業員の家庭事情に十分配慮した人事運用を行う必要があります。
なお、転勤による単身赴任の注意点についてはこちらの記事をご確認ください。
出典:e-Gov 法令検索『育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律』
→【チェック!】マイホームを持つ社員向け転勤者サポートサービスについて知りたい。 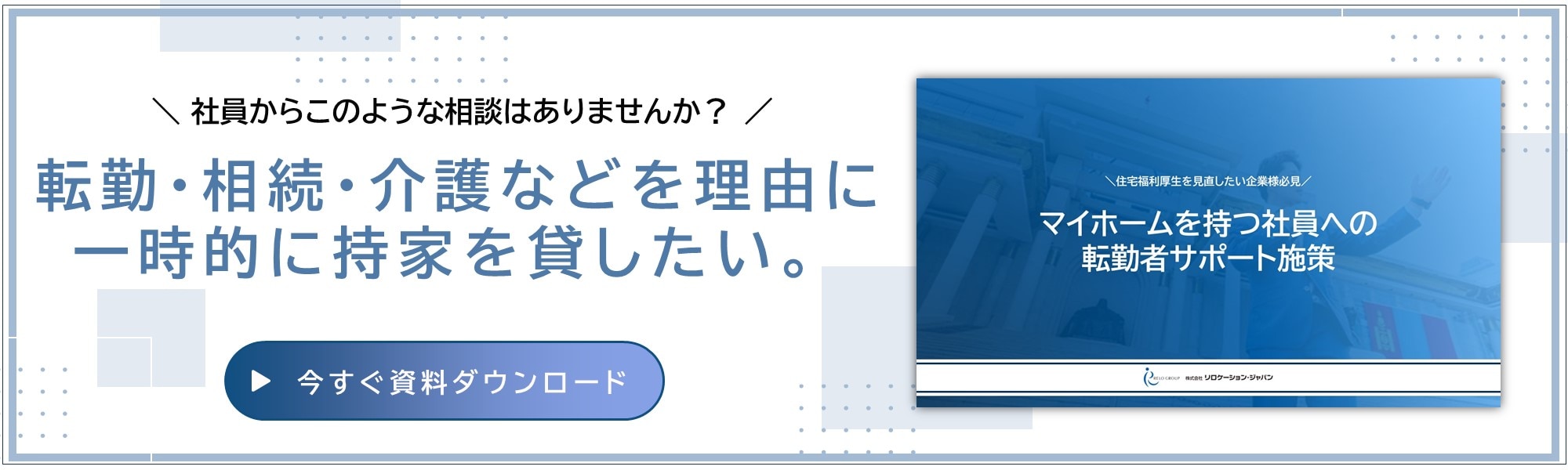
まとめ
この記事では、転勤の辞令について以下の内容を解説しました。
- 転勤命令に関する原則
- 従業員による転勤の拒否が認められるケース
- 転勤命令に伴うトラブルにつながりやすいケース
- 転勤の拒否に対する懲戒解雇の可否
- 転勤を拒否する従業員への対応
- 転勤の辞令に関する注意点
転勤は、勤務地や生活環境が変わることによってさまざまな不安・不満が生まれるほか、時間的・金銭的な負担も伴います。
従業員に納得してもらうには、転職の理由・メリットを丁寧に伝えるとともに、懸念点や個別の事情を踏まえて負担を減らすためのフォローを行うことが重要です。
なかでも転居先での住居に関する費用は、従業員の負担も大きくなりがちです。社宅を提供すると、従業員自身で賃貸住宅を契約する必要がないほか、毎月の住居費を抑えられるようになり、負担の削減につながります。
マイホームを持つ転勤者へのサポートについてはこちらの資料をご確認ください。
『リロケーション・ジャパン』の社宅管理サービスでは、転勤者に対する社宅の運用をトータルサポートしております。賃貸物件の契約や引越しの手配、各種手続きに至るまで一括で代行しているため、スムーズな入居が可能です。
詳しくは、こちらの資料をご確認ください。





