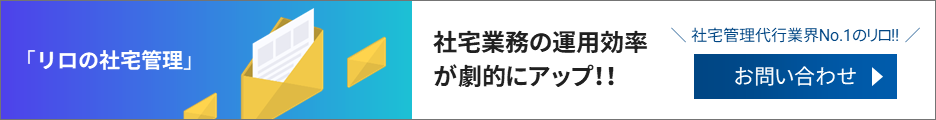【社宅管理】転勤が決まったあとに必要な手続きと流れ
転勤は、新たな職場への適応や不慣れな土地での物件探しなど、なにかと労力がかかり大変です。しかし、企業が社宅を用意することで、環境が大きく変化する従業員の労力や経済的な負担、ストレスの軽減に貢献できます。
人事・総務部で「転勤者のために社宅の導入を検討している」「社宅の手配をどのような流れで進めればよいか知りたい」という担当者の方もいるのではないでしょうか。
この記事では、転勤者向けに社宅を手配する際の流れについて解説します。
→【気になる!】借上げ社宅管理の業務改善方法とは?詳しく知りたい。 
目次[非表示]
- 1.転勤が決まったあとに必要な手続き
- 1.1.社宅の手配に必要な手続きの流れ
- 1.1.1.①社内手続きを行う
- 1.1.2.②条件を決めて物件を探す
- 1.2.③物件を決めて契約手続きを行う
- 1.3.社宅の手配以外に必要な手続きの流れ
- 1.3.1.①現住居の退去手続きを行う
- 1.3.2.②引越し事業者を手配する
- 1.3.3.③入居先のライフラインを整備する
- 1.3.4.④役所への届け出を行う
- 2.まとめ
転勤が決まったあとに必要な手続き
転勤が決まったあとは、社宅の手配や現住居の退去など、企業側・従業員側でさまざまな手続きを行う必要があります。
実際の手続きの流れは企業ごとに異なるため、ここからは社宅制度がある企業における企業側・従業員側で行う手続きの一般例を紹介します。
社宅の手配に必要な手続きの流れ
社宅の手配業務は社内外にわたって、企業側・従業員側でそれぞれ手続きを行います。社宅の手配を行う際の流れは、以下で詳しく紹介します。
①社内手続きを行う
社宅を利用する場合は、物件を探す前後に社内申請手続きを行います。
通常、社宅は全従業員が無条件で使用できる制度ではないため、定められた手順に沿いながら社内で手続きを行う必要があります。
社内手続きの内容は企業によって異なりますが、物件を探す前後に社宅利用申請や誓約書などを提出するのが一般的です。
企業側は、申請内容の確認・承認を行い、場合によっては従業員の代理で申請手続きを進めるケースもあります。
②条件を決めて物件を探す
社宅を手配する際は、社宅規程に合致する範囲内で、あらかじめ希望条件を決めてから物件を探すことが望ましいです。
物件の希望条件は、建物の構造・築年数・間取りなど、個人が賃貸物件を探す際と同様の条件が挙げられます。
従業員の自己負担費用が物件ごとに変動する借上社宅制度の場合は、従業員側が物件を探す傾向がやや多く見られますが、企業側で探す運用も一般的です。
企業側は、社宅規程で定められた条件に加えて、予算・必要な部屋の数・事業所との距離などを事前に想定して考慮する必要があります。
③物件を決めて契約手続きを行う
条件に沿った物件が見つかったあとは内見を行い、企業側にて契約手続きを行います。
内見の際は、居住スペースのほか、災害警戒区域情報(ハザードマップ)や、周辺施設(病院、スーパー、コンビニなど)を確認しておくことが望ましいです。
物件が納得できる内容であれば、入居の申し込みを行って、社宅規程との適合確認をしながら賃貸借契約の手続きを行います。
内見や入居申し込みは従業員側で対応する場合が多いですが、社宅は法人契約になるため、契約手続きは企業側が行う必要があります。
社宅の手配以外に必要な手続きの流れ
企業側で行う手続きのほか、従業員側が行う手続きもあります。ここからは、転勤の際に発生する手続きのうち、社宅の手配以外に必要なものを紹介します。
①現住居の退去手続きを行う
転勤が決まり社宅へ引越す際は、現住居の退去手続きを行う必要があります。
転勤が決まったあとは、まず現住居の管理会社または大家へ退去の旨を伝えます。現住居が社宅の場合は、企業側から退去の連絡をする場合もあります。
契約内容により異なりますが、退去の1ヶ月前までには連絡するよう定められているケースが多いため、余分な費用の発生を抑えるためにも遅れがないようにすることが望ましいです。
管理会社や大家への連絡のほかには、火災保険、ライフライン(電気、ガス、水道)、インターネットなどの解約・移転手続きも漏れなく行う必要があります。
また、退去時は管理会社や大家との立会いがあるため、部屋は可能な限りきれいな状態にしておくことを推奨します。
②引越し事業者を手配する
転勤が決まったあとは、社宅規程や引越し規程に沿いながら、企業または従業員が引越しの手続きを行います。
一般的には、転勤の引越し費用は企業負担としている場合が多いですが、大型の家具・家電など、一部の引越し費用を個人負担としているケースもあります。
転勤が多い企業の場合は、指定の引越し事業者と契約したうえで依頼をする選択肢もあります。
企業側が指定する引越し事業者がなく、従業員自身で手配する場合は、引越し費用の支払者が従業員と企業のどちらになるかを事前に確認しておくとよいでしょう。
また、企業負担の引越し費用を従業員自身が立替で支払った場合は、見積もりや請求書は会社に提出する必要があるため、保管しておくことが望ましいです。
なお、こちらの記事では、従業員の転勤に伴う引越し費用や、その前後で発生する費用の、一般的な負担区分と、転勤時に必要な手続きについて解説しています。併せてご覧ください。
→【あわせて読みたい!】物流業界の今!社宅引越しに与える影響について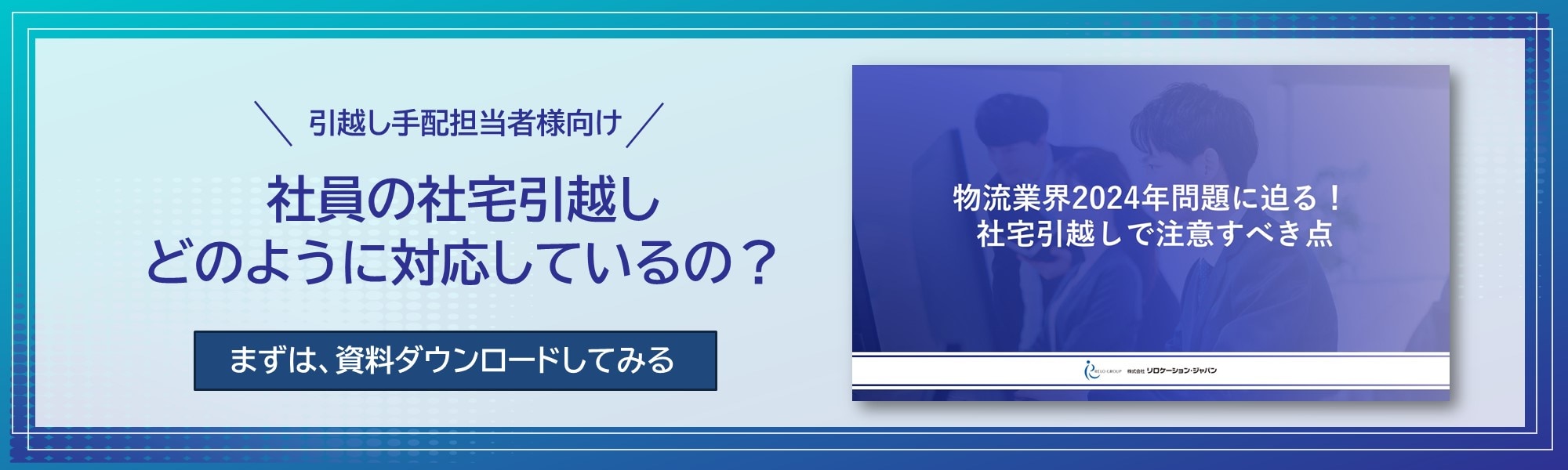
③入居先のライフラインを整備する
入居後にすぐ生活が始められるようにするために、ライフライン(電気、ガス、水道、インターネットなど)の整備は早めに済ませることが望ましいです。
ライフラインは即日利用できるケースが少ないため、事前に電話やインターネットで各担当事業者へ連絡します。
また、ガスやインターネットについては、立会いや工事が発生するケースがあるため、日程調整が必要な可能性があります。
引越しの繁忙期である2~3月、9~10月などは、希望どおりに手続きが進まないことが想定されるため、早めの連絡が重要です。
こちらの記事では、社宅におけるライフラインの手続きや光熱費について詳しく解説しています。併せてご覧ください。
④役所への届け出を行う
引越しをする際は、住民票の住所変更の届け出が法律上で義務づけられており、正当な理由がなく手続きが遅れた場合は、5万円以下の過料といった罰則が科せられる恐れがあります。届け出は、引越しの前後どちらでも提出可能です。
提出する届け出の書類は、引越し先が前住所と同じ市区町村であるか否かで変わります。
▼引越し先住所による役所での手続き例
同じ市区町村 | 住民異動届の転居届にチェックを入れ、必要事項を記入し役所に提出する |
違う市区町村 | 前住所を管轄する役所で転出届を提出後、発行される転出証明書とともに住民異動届を役所に提出する |
マイナンバーや国民健康保険などの住所変更は、引越し後14日以内に手続きするように定められているため、早めの手続きが望ましいです。
また、こちらの記事では、単身赴任時における住民票の取扱いをはじめ、会社側で必要になる住所変更の手続きについて解説しています。併せてご覧ください。
まとめ
この記事では、転勤が決まったあとに必要な手続きと流れについて、以下の内容で解説しました。
- 転勤が決まった後に必要な手続き
- 社宅の手配に必要な手続き
- 社宅の手配以外に必要な手続き
転勤が決まったあとは、社宅や引越し事業者の手配、ライフラインの整備など、さまざまな手続きが発生します。
上記で紹介した手続き以外にも、転園・転校の手続きや、一部ペットの登録住所の変更手続きなど、従業員の家庭状況に応じて必要な手続きが存在します。
そのため、企業が社宅を用意することで、転勤に伴う従業員の経済的負担やストレスの軽減を図ることができます。
リロケーション・ジャパンの社宅管理サービスは、物件探し・引越しの見積もり依頼・適切なライフラインの案内・制度の見直しなどをとおして、手厚くサポートします。
また、社宅にかかる管理業務をフルアウトソーシングできるため、クライアントさまの工数削減を実現することが可能です。
詳しくはお気軽にお問い合わせください。
→【詳しく知りたい!】『リロの社宅管理』を導入・利用企業様の事例はこちら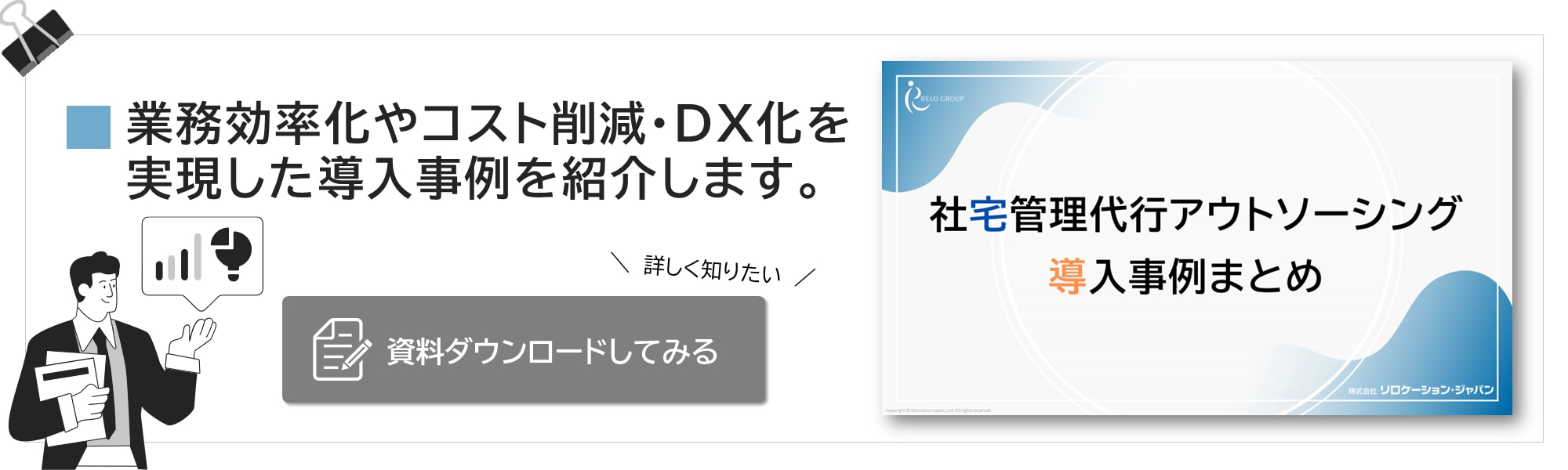
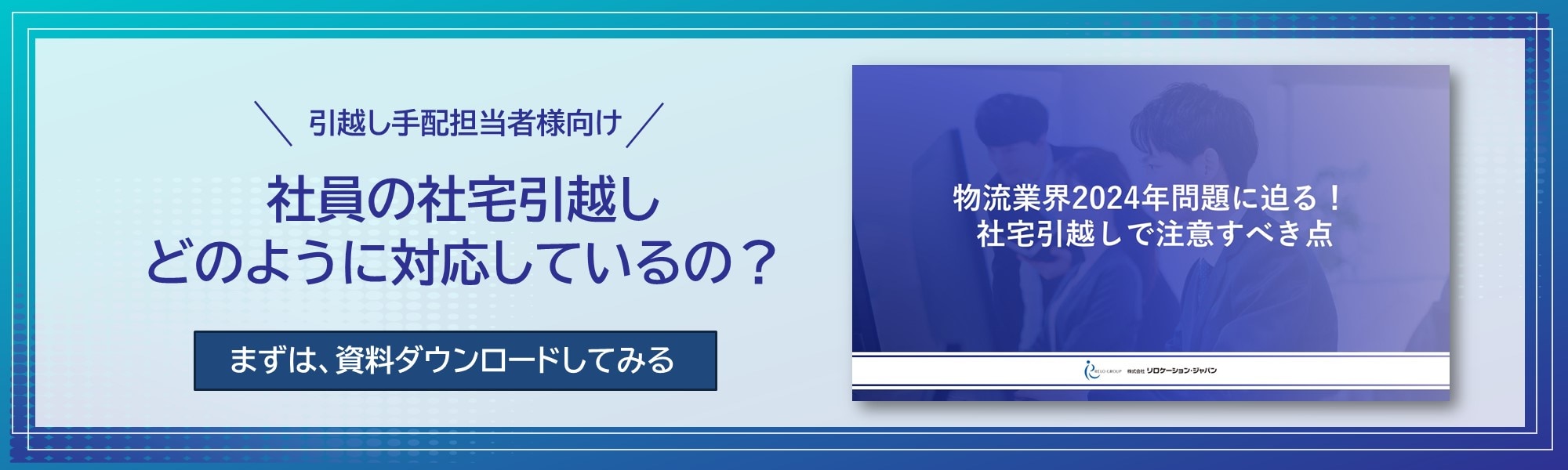
こちらの記事では、社宅管理代行サービスを導入する流れを解説しています。併せてご覧ください。