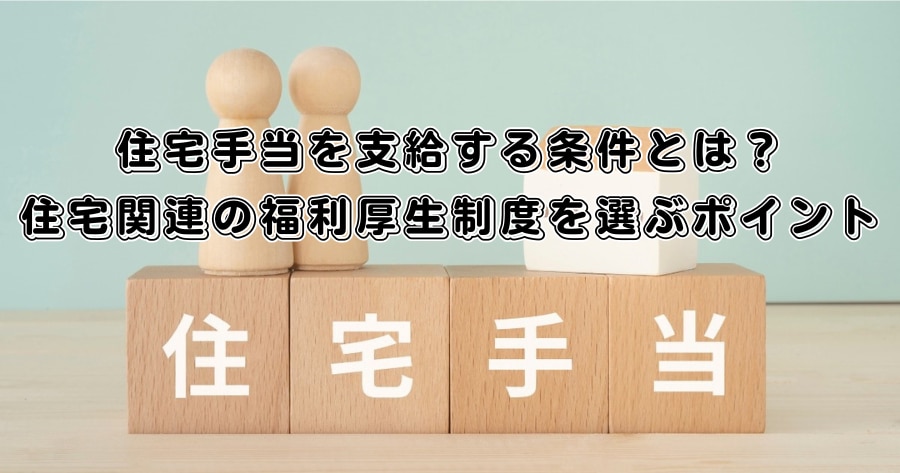
住宅手当を支給する条件とは? 住宅関連の福利厚生制度を選ぶポイント
※2025年5月22日更新
従業員の生活費に関する負担を軽減する福利厚生の一つに“住宅手当”があります。住宅手当とは、従業員が暮らす賃貸物件の家賃や持ち家の住宅ローンに関する費用の一部を企業が補助する制度です。
人事総務部門のご担当者さまのなかには、「住宅手当の支給条件をどのように定めればよいのか」「ほかの住宅関連の福利厚生制度とどちらを選べばよいのか」と疑問を持つ方もいるのではないでしょうか。
この記事では、住宅手当の基本的な支給条件と住宅関連の福利厚生制度を選ぶポイントについて解説します。
→【おすすめ】記事と合わせて読みたい「社宅制度と住宅手当のメリット・デメリット」 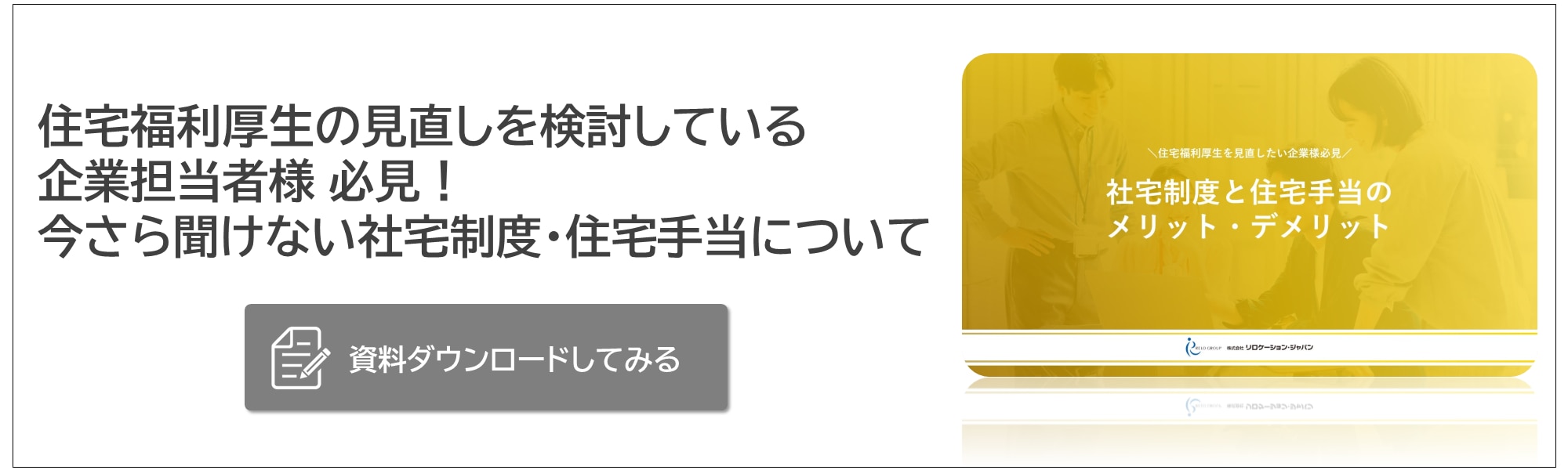
目次[非表示]
住宅手当とは
住宅手当は、従業員が支払っている住居費の一部を企業が支給する制度です。企業によって対象となる費用は異なりますが、主に以下の2種類があります。
▼住宅手当の対象となる費用
- 従業員が借りている賃貸物件の家賃
- 持ち家の住宅ローンにおける毎月の返済分
企業が独自に導入できる法定外福利厚生に位置づけられており、賃貸物件の家賃を対象とする場合には制度の名称を“家賃補助”としている場合もあります。
住宅手当を支給する目的は、生活費の多くを占める住居費の負担を抑えて、従業員の安定かつゆとりのある生活を支援することです。
毎月の給与に加えて金銭で一定の金額を支給する仕組みとなっており、手当は給与所得として扱われます。
出典:国税庁『No.2508 給与所得となるもの』
住宅手当における支給条件の決め方
住宅手当を支給する条件や金額は法律による決まりはないため、企業側が任意で定めることが可能です。住宅の種別や家族構成などに応じて、柔軟に支給条件を設定している企業もあります。
一般的な支給条件の決め方には、以下が挙げられます。
雇用形態
正社員か非正規社員かによって住宅手当の支給条件を決めることがあります。
▼支給条件の例
- 転勤がある正社員に住宅手当を支給する
- 転勤がない非正規社員は住宅手当の対象外とする
ただし、日本ではパートタイム・有期雇用労働法に基づく“同一労働同一賃金”が定められており、正社員と非正規社員との間で不合理な待遇差を設けることは禁止されています。福利厚生の一種となる住宅手当についても、不合理な待遇差を設けてはならないとされます。
一概に雇用形態で区別するのではなく、従業員一人ひとりの働き方や役割などの違いを踏まえて見合った福利厚生の待遇を設定することが重要です。
出典:厚生労働省『同一労働同一賃金ガイドライン』
住宅の種別
賃貸物件か持ち家かによって住宅手当の支給条件を決める方法があります。
▼支給条件の例
- 賃貸物件での家賃の一部を支給する
- 持ち家での住宅ローン返済額の一部を支給する
賃貸物件の場合は、従業員への生活支援が目的となります。持ち家の場合は、従業員に住宅の購入を支援して、生活基盤の安定化をサポートすることが目的となります。
持ち家では、住宅ローンを返済すると従業員の資産となりますが、賃貸物件は将来的な資産にはなりません。そのため、賃貸物件のみを対象に住宅手当を支給している企業も見られます。
従業員に対して公平な手当として支給する場合には、住宅の種別にかかわらず一律の金額を支給する場合もあります。
扶養家族の有無
住宅手当の支給条件に扶養家族の有無を定めることがあります。
▼支給条件の例
- 従業員本人が世帯主となる場合に支給する
- 従業員が世帯主で扶養家族がいる場合に支給する
- 20歳未満の子どもを養育している従業員に支給する
企業によっては扶養家族の有無や人数に応じて住宅手当の支給額を柔軟に設定している場合もあります。親や配偶者の扶養に入っている従業員に対しては、住宅手当の対象外とすることが一般的です。
会社までの距離
住宅から会社までの距離を住宅手当の支給条件として定める場合があります。
▼支給条件の例
会社の最寄り駅から2〜3駅圏内に住む従業員に支給する
会社から一定距離以内の条件を定めることによって、通勤手当や通勤によるストレスを減らす目的があります。
住宅手当の支給額相場
厚生労働省がまとめた『令和2年就労条件総合調査の概況』によると、調査した企業全体の47.2%が住宅手当を導入しており、従業員一人当たりの平均支給額は1万7,800円となっています。
また、企業規模による住宅手当の平均支給額は以下のとおりです。
▼【企業規模別】住宅手当の平均支給額
企業規模 | 従業員一人当たりの平均支給額 |
1,000人以上 | 2万1,300円 |
300~999人 | 1万7,000円 |
100~299人 | 1万6,400円 |
30~99人 | 1万4,200 |
厚生労働省『令和2年就労条件総合調査の概況』を基に作成
従業員数が1,000人以上の企業では、平均支給額が2万1,300円と全体平均よりも高くなっています。企業規模が大きいほど支給金額が高いことが分かります。
出典:厚生労働省『令和2年就労条件総合調査の概況』
住宅手当のメリット・デメリット
住宅手当は、従業員の生活を支援して働きやすい職場を提供するために役立てられます。ただし、制度の運用によって負担につながる可能性があるため、メリット・デメリットを把握しておくことが重要です。
メリット
住宅手当を支給すると、次のメリットが期待できます。
▼メリット
- 従業員の満足度向上
- 定着率の向上
- 人材採用の促進
生活費に含まれる住宅の費用を給与に上乗せして支給することで、従業員の家計負担が削減されて手取り額が増加します。生活にゆとりが生まれることによって、従業員の満足度や定着率の向上につながると期待できます。
また、住宅手当で従業員の生活を支援することで、福利厚生が充実している企業として競合他社との差別化を図れます。採用活動の際にアピールすると、遠方に住む人や初めて一人暮らしをする人の入社を促進できる可能性が期待できます。
デメリット
住宅手当には、デメリットも存在します。
▼デメリット
- 運用コストの増加
- 税金・社会保険料の増額
住宅手当を支給する際は、従業員によって不公平な制度設計にならないように条件や対象者を設定する必要があるため、運用の負担につながりやすくなります。
また、住宅手当は一般的に給与所得として取り扱われます。手当額に応じて所得税が課税されることに加え、企業・従業員双方の社会保険料負担が増えることもあります。
住宅手当以外の住宅に関する福利厚生
住宅に関する福利厚生には、住宅手当のほかにもさまざまな種類があります。代表的な制度を3つ紹介します。
➀社宅制度
社宅制度は、従業員が居住する住宅を企業が提供する制度です。提供する住宅の種別は、大きく2つに分けられます。
▼社宅の種別
種別 | 概要 |
借上社宅 | 企業が賃貸物件を契約して従業員に貸与する社宅 |
社有社宅 | 企業が保有する物件を従業員に提供する社宅 |
住宅手当では給与として金銭で手当を支給しますが、社宅制度は住宅そのものを提供します。従業員の給与から一定割合以上の社宅使用料を徴収することにより、会社負担分が非課税になります。
新入社員や転勤者、単身赴任者などを対象に社宅を提供することで、従業員のスムーズな住居探しと引越しが可能になります。
社宅の種類や住宅手当との違いについては、こちらの記事をご確認ください。
出典:国税庁『No.2597 使用人に社宅や寮などを貸したとき』
②持ち家支援制度(住宅資金支援制度)
持ち家支援制度(住宅資金支援制度)は、従業員が土地・住宅を購入するための資金を融資する制度です。融資の方法には、主に2つのパターンがあります。
▼持ち家支援制度による融資の方法
- 企業が従業員へ直接融資する
- 金融機関と提携して一般の住宅ローンよりも有利な条件で融資する
住宅の購入にあたっては一般的に住宅ローンが利用されます。持ち家支援制度を設けることで、従業員が金融機関と直接契約するよりも低い金利で融資を受けられるようになり持ち家購入を促進できます。これにより、生活の安定化や満足度の向上が期待されます。
→【チェック!】マイホームを持つ社員向け転勤者サポートサービスについて知りたい。 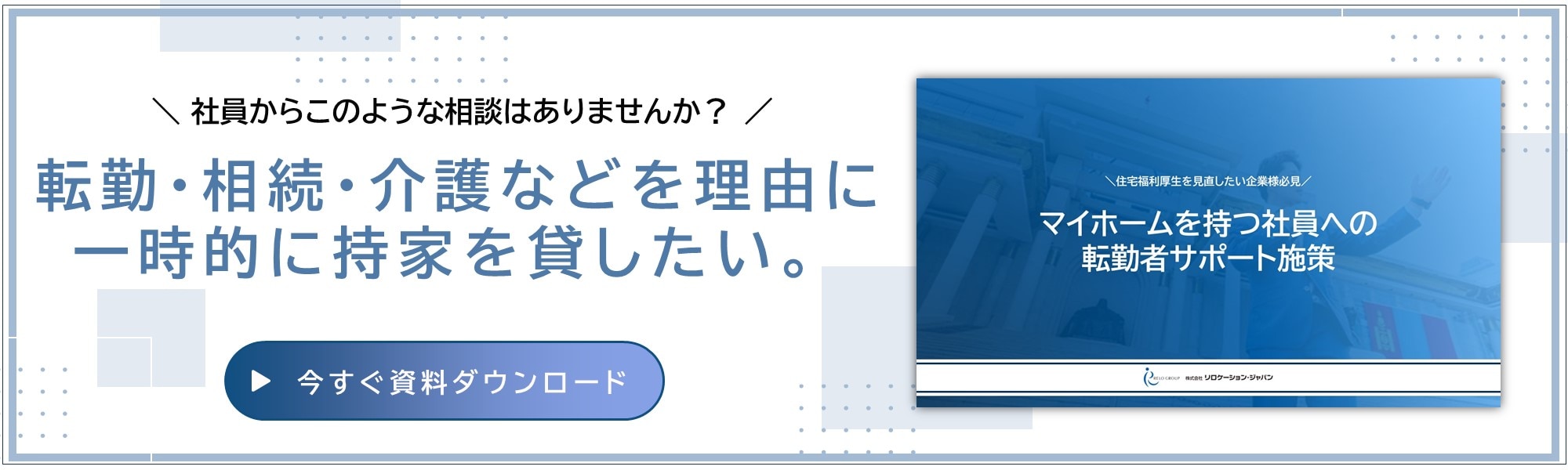
③引越し手当
引越し手当は、入社や転勤の際に発生する引越し費用を企業が支給する制度です。支給条件は企業によって異なりますが、主に以下の従業員が対象となります。
▼引越し手当の対象者
- 遠方から新たに入社する従業員
- 転勤者や単身赴任者
- 現住居から社宅に引越しする従業員 など
引越し手当の支給によって、転勤や単身赴任者の経済的な負担を軽減できるほか、遠方からの人材採用を促進することが可能です。
企業が支給する引越し費用の負担区分については、こちらの記事で詳しく解説しています。併せてご確認ください。
住宅関連の福利厚生制度を選ぶポイント
住宅関連の福利厚生制度にはさまざまな種類があります。企業がどのような目的で導入するのか明確にしたうえで制度を選定することがポイントです。
▼住宅関連の福利厚生を導入する目的
- 入社して間もない従業員や、若い世代の従業員の家計負担を軽減する
- 持ち家の取得を支援して、生活の安定化と定着率の向上を図る
- 転勤に伴う転居の負担を軽減する
- 福利厚生を充実させて、従業員の満足度を高める など
近年では、テレワークによる働き方の多様化や働き方改革における同一労働同一賃金の推進、運用コストの負担増加などを背景に住宅手当を廃止する企業も見られています。
住宅手当に限定することなく、社宅制度や持ち家支援制度、引越し手当などの従業員のニーズに応じた福利厚生を柔軟に導入することが重要です。住宅手当が廃止される背景や代替施策についてはこちらの記事をご確認ください。
また、リロケーション・ジャパンでは、住宅手当の支給対象者に対して賃貸物件の契約手続きや初期費用を抑えられる『個人版転貸サービス』を用意しております。従業員さまに代わって家主と賃貸借契約を結ぶことで、入社や転勤時などの入居手続きをサポートできます。
まとめ
この記事では、住宅手当について以下の内容を解説しました。
- 住宅手当の仕組み
- 支給条件の決め方
- 住宅手当の金額相場
- 住宅手当のメリット・デメリット
- 住宅手当以外の住宅に関する福利厚生
- 住宅関連の福利厚生制度を選ぶポイント
住宅手当の支給条件は、住宅の種別や家族構成、会社までの距離などを基に決定されます。従業員間で待遇の差が生じないように、公平かつ柔軟に支給額や対象者を決めることが重要です。
また、住宅に関する福利厚生は住宅手当だけではありません。「住宅に関する福利厚生を何のために導入するのか」「どのような制度が喜ばれるのか」といった目的・ニーズに応じて制度を導入することがポイントです。
『リロケーション・ジャパン』では、社有社宅や借上社宅の運用をサポートしております。「社宅制度の運用負担を削減したい」「社宅制度を見直して従業員の満足度を高めたい」といった課題を解決します。
サービスの詳しい内容やメリット・デメリットはこちらの資料をご確認ください。






