
借上社宅は自由に選べる? 従業員に喜ばれる物件と選ぶ際の注意点
借上社宅とは、企業が借り上げた賃貸物件を社宅として従業員に貸し出す福利厚生の制度です。
対象とする物件は基本的に企業が選定しますが、近年では福利厚生の充実化を図るために、一定の条件を設けて従業員が自由に物件を選べる制度を導入している企業も見られています。
人事総務部門のご担当者さまのなかには「従業員が物件を選べるようにする際の注意点はあるか」「従業員に喜ばれる物件をどのように選べばよいか」と気になる方もいるのではないでしょうか。
この記事では、借上社宅において従業員が物件を自由に選べるケースや従業員に喜ばれる社宅の選び方、物件を選ぶときの注意点などを解説します。
なお、借上社宅のメリット・デメリットはこちらの記事をご確認ください。
→【おすすめ!】記事と合わせて読みたい「社宅制度と住宅手当のメリット・デメリット」
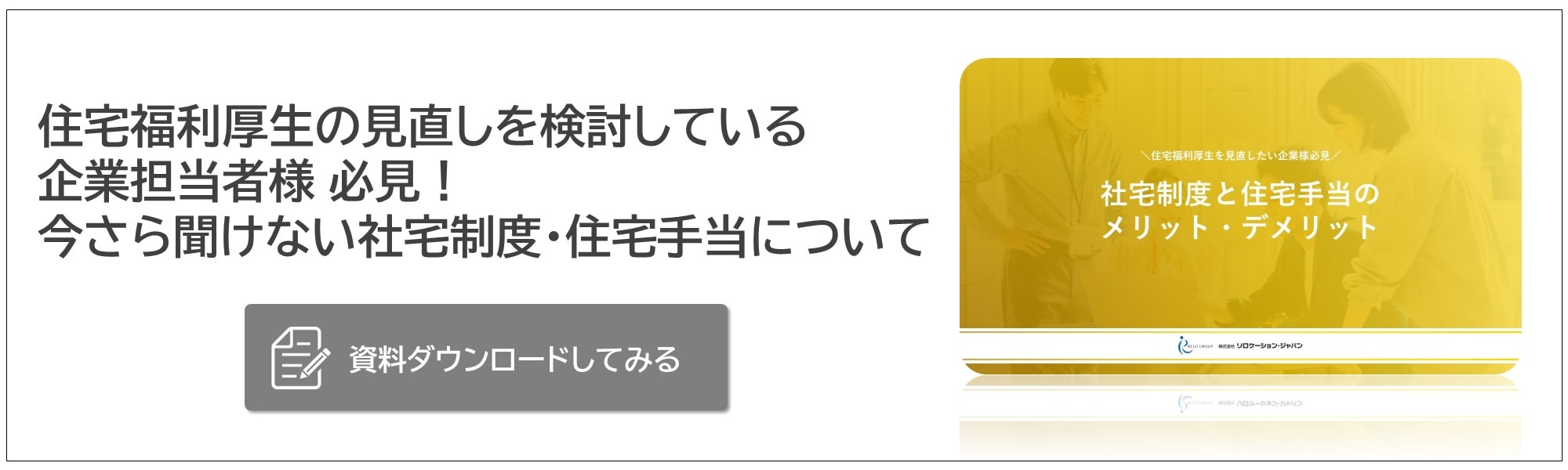
目次[非表示]
借上社宅の物件を従業員が自由に選べるケース
借上社宅の物件を従業員が自由に選べるようにしている企業では、社宅規程で一定の条件を設けて選定できる範囲を定めていることが一般的です。
▼従業員による物件選定に関する主な条件
- 家賃の上限
- 物件の間取りや広さ
- 物件があるエリア など
条件なく自由に物件を選べるようにした場合には、福利厚生費や交通費の管理が煩雑化したり、従業員間で不公平感が生まれてしまうことがあります。
また、税制上の借上社宅として認められるには、従業員から一定額以上の社宅使用料を徴収することや、住宅の規模による異なる条件などが定められています。
福利厚生の公平性を確保して借上社宅を適正に運用するために、従業員が選べる物件の条件を社宅規程で明確に定めておくことが重要です。
なお、借上社宅の入居条件を設定する項目については、こちらの記事で解説しています。併せてご確認ください。
出典:国税庁『No.2600 役員に社宅などを貸したとき』
従業員に喜ばれる借上社宅の選び方
企業が借上社宅の物件を選定する場合には、間取りや立地などについて従業員から不満が生じる可能性があります。従業員のニーズや生活のしやすさなどを踏まえて物件を選ぶことが重要です。
▼社宅物件を選ぶ際のポイント
ポイント | 具体例 |
間取り |
|
立地 |
|
設備 |
|
会社までのアクセスがよく生活がしやすい物件を選ぶことで、利便性が高まり満足度の向上につながります。また、現代の生活様式に合った間取りや最新の設備が備わった物件であれば、従業員に喜ばれやすいと考えられます。
なお、社宅にする物件の選び方や内見・内覧のポイントについてはこちらの記事で解説しています。併せてご覧ください。
→【おすすめ!】社宅だけじゃない!?社有社宅・寮管理の煩雑業務もまるっと解決! 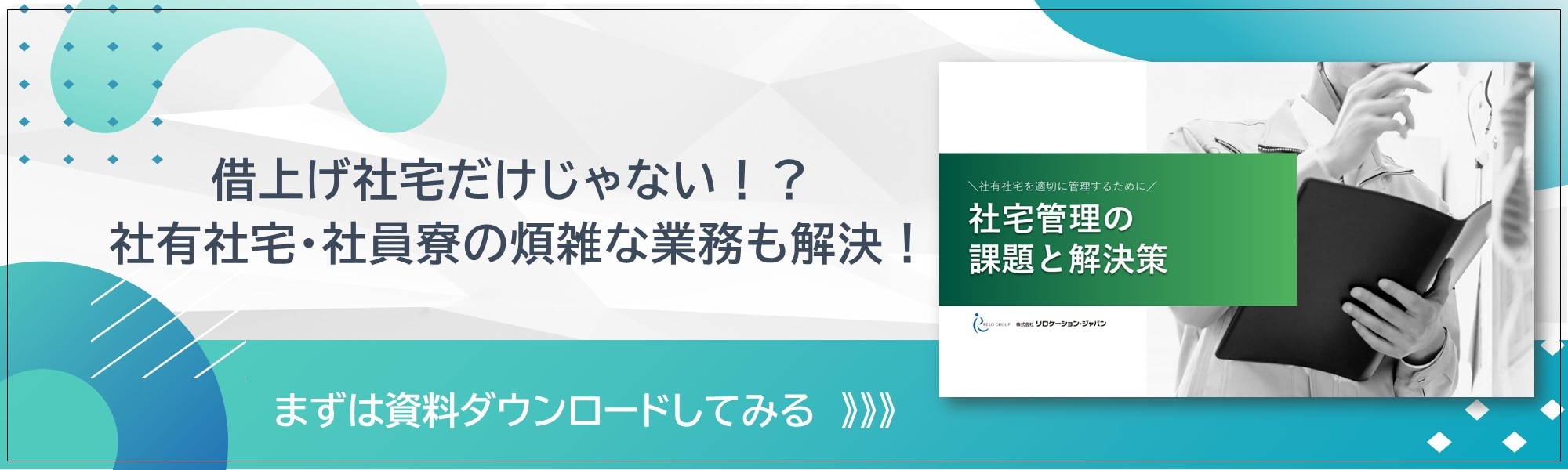
借上社宅の物件を選ぶときの注意点
企業または従業員自身で借上社宅の物件を選ぶ際には、契約内容や入退去に関するトラブルを防ぐための対策が必要になります。
賃貸借契約の形態を確認する
借上社宅にする物件を選定する際は、賃貸借契約の形態について事前に確認しておくことが必要です。賃貸借契約の形態には、主に普通借家契約と定期借家契約の2種類が存在します。
▼賃貸借契約の形態
形態 | 契約期間 | 更新の有無 |
普通借家契約 | 1年以上(期間の定めなし) | 正当な事由がない限りは更新 |
定期借家契約 | 1年未満でも有効(3ヶ月や半年など) | なし(期間満了によって終了) |
国土交通省『定期借家制度』を基に作成
定期借家契約の場合、一定の契約期間が定められています。期間が満了すると更新はできないため、新しく物件を探し直さなければならなくなることがあります。
長期での入居または入居期間が決まっていない場合には、普通借家契約で借りられる物件を選ぶことが必要です。
なお、普通借家契約と定期借家契約の違いや、借上社宅の賃貸借契約に必要な書類についてはこちらの記事をご確認ください。
出典:国土交通省『定期借家制度』
社宅利用のマニュアルを作成する
従業員に借上社宅を貸与する際は、社宅規程に加えて社宅利用に関するマニュアルを作成・共有しておく必要があります。
賃貸物件によって共用部の利用ルールが異なったり、賃貸借契約に特約が設けられたりする場合もあるため、物件ごとの留意事項をまとめておくことが重要です。
▼マニュアルを策定する内容例
- ゴミ出しや駐輪場の利用などに関するルール
- 汚損・破損が発生した場合の金銭的な負担に関する規定
- 原状回復工事に関する特約の有無と企業との負担割合
- 楽器の演奏に関するルール
- ペット飼育の可否 など
借上社宅の利用に対して事前に従業員との認識を合わせておくことで、トラブルの防止とスムーズな入退去につながります。
なお、原状回復工事の費用やトラブルの防止策についてはこちらの記事をご確認ください。
まとめ
この記事では、借上社宅の物件選びについて以下の内容を解説しました。
- 借上社宅の物件を従業員が自由に選べるケース
- 従業員に喜ばれる借上社宅の選び方
- 借上社宅の物件を選ぶときの注意点
借上社宅の運用において従業員のニーズや生活スタイルに合わせた物件を選ぶことで、満足度の向上につながると考えられます。
従業員に物件を選ばせて福利厚生の充実化を図る際には、社宅規程で物件の条件を設けて一定の範囲内で自由に選択できるようにすることがポイントです。
また、借上社宅の物件を選ぶ際には、賃貸借契約の形態を確認するとともに、社宅利用のマニュアルを作成して、契約内容や入居中における従業員とのトラブルを防ぐことも必要です。
『リロケーション・ジャパン』では、借上社宅の物件選びから賃貸借契約の手続き、運用管理に至るまでをトータルサポートしています。転貸方式によるフルアウトソーシングによって家主との個別の賃貸借契約が不要になるため、契約トラブルの防止や業務負担の削減につながります。
詳しいサービス内容は、こちらの資料をご確認ください。
→【気になる!】借上げ社宅管理の業務改善方法とは?詳しく知りたい。 





