
社宅制度を導入するには。基本的な流れと押さえておきたいポイント
社宅制度は、従業員の安定した生活を支援する福利厚生の一種です。
従業員にとって毎月の家賃負担を抑えられるほか、入社・転勤時に住居を円滑に確保できるメリットがあることから、人材の定着化や採用力の強化にもつながると考えられます。
これから社宅制度の導入を検討している人事総務部門のご担当者さまは、住宅手当との違いや社宅の種類について理解を深めたうえで、運用体制の整備を進めることが重要です。
この記事では、社宅制度と住宅手当との違いや社宅の種別、導入までの基本的な流れ、押さえておきたいポイントについて解説します。
なお、リロケーション・ジャパンの社宅管理サービスについてはこちらの資料をご覧ください。
→【詳しく知りたい!】『リロの社宅管理』を導入・利用企業様の事例はこちら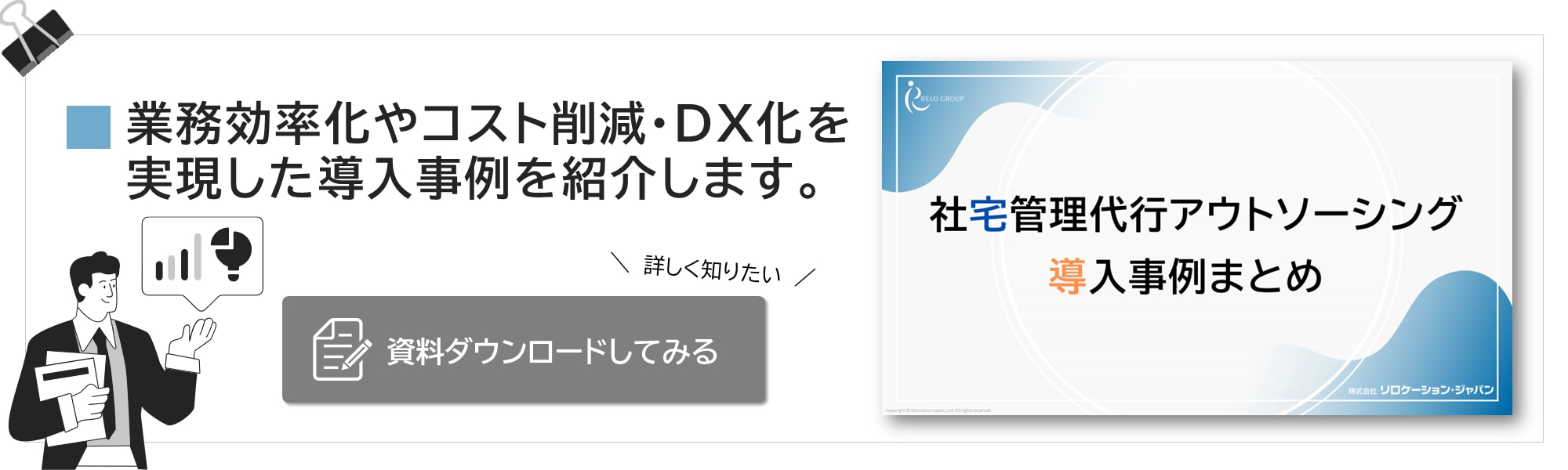
目次[非表示]
- 1.社宅とは
- 2.住宅手当との違い
- 3.社宅制度の種類
- 4.社宅制度を導入する流れ
- 4.1.➀社宅の運用形態を決定する
- 4.2.②社宅規程を作成する
- 4.3.③運用体制・フローを構築する
- 5.社宅制度の導入時に押さえておきたいポイント
- 6.まとめ
社宅とは
社宅とは、会社が従業員に貸与する住居のことです。福利厚生の一環として生活の基盤となる住居を提供することにより、従業員の経済的な負担を軽減できます。
会社が社宅を提供する目的には、主に以下が挙げられます。
▼社宅を提供する目的
- 安定した住環境を確保して人材の定着化を図る
- 住宅関連の支出を減らして満足度を向上させる
- 遠方からの入社希望者を増やして採用力を高める
- 転勤時の引越しを支援して人材の流動化を図る など
また、社宅は無償で提供するのではなく、毎月一定の社宅使用料を従業員の給与から差し引いて徴収する仕組みとなります。
福利厚生における社宅の位置づけについては、こちらの記事をご確認ください。
住宅手当との違い
住宅関連の福利厚生として代表的な制度に“住宅手当”があります。
住宅手当は、従業員が契約している賃貸物件の家賃や、持ち家に対する住宅ローンの返済を一部補助する目的で支給する手当です。社宅制度と住宅手当では、支給する対象物や税金の扱いに違いがあります。
▼社宅制度と住宅手当の違い
社宅制度 | 住宅手当 | |
支給の対象物 | 住居 | 現金 |
税金の扱い | 所得税が課税されない | 所得税が課税される |
社宅制度の場合、従業員から毎月一定額以上の社宅使用料を徴収していれば、給与として所得税は課税されません。そのため、従業員の手取り額や社会保険料への影響を防ぐことが可能です。
これに対して住宅手当は、給与の一部として現金で支給されます。支給した手当分については所得税の課税対象となるほか、給与額が増えることで社会保険料の負担が増加する可能性があります。
住宅手当についてはこちらの記事で詳しく解説しています。
出典:国税庁『No.2597 使用人に社宅や寮などを貸したとき』『No.2508 給与所得となるもの』
→【おすすめ!】記事と合わせて読みたい「社宅制度と住宅手当のメリット・デメリット」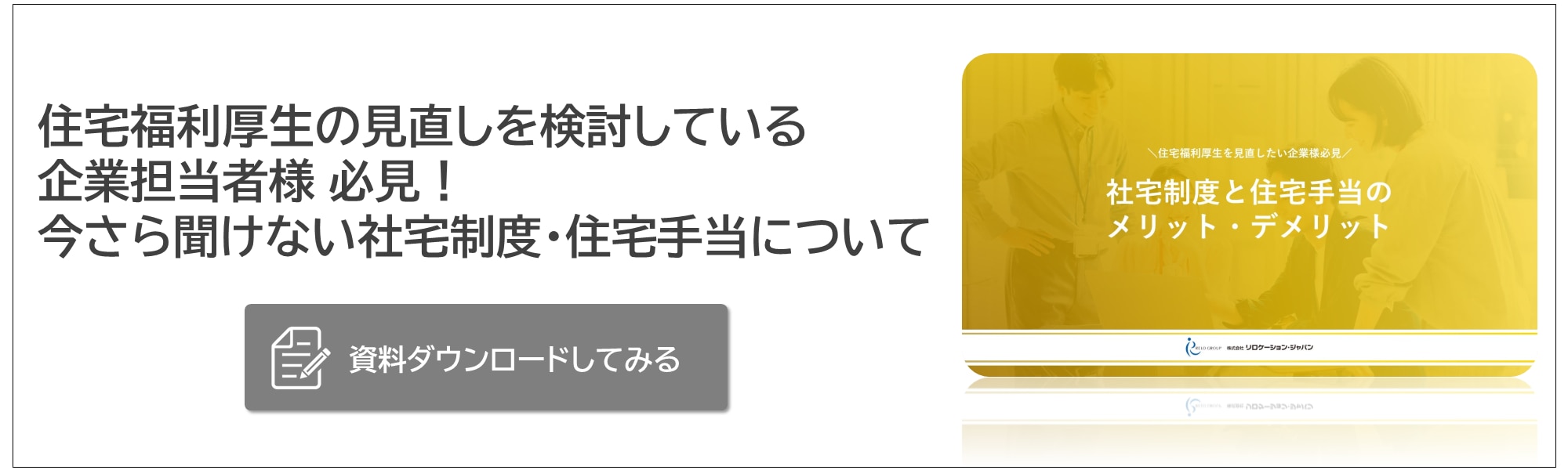
社宅制度の種類
社宅制度は、運用形態によって大きく2つの種類に分けられます。
▼社宅制度の種類
種類 | 概要 |
社有社宅 | 会社が居住用建物を購入または建設して従業員に貸し出す |
借上社宅 | 賃貸物件を会社名義で契約して従業員に貸し出す |
社有社宅は、自社所有の不動産として事業所の拠点や規模に合わせて運用することが可能です。一般的な物件の種別には、複数人で共同生活を行える共用スペースを備えた寮や、単身者向けのアパートなどが挙げられます。
一方の借上社宅は、家主と契約を交わして賃貸物件を借りる運用形態のため、必要なときに柔軟に社宅を提供できます。マンションを一戸単位で借り上げる方法のほか、フロア単位・一棟単位などで借り上げる場合もあります。
社宅の種類については、こちらの記事をご確認ください。
社宅制度を導入する流れ
社宅制度を導入する際は、予算と運用上の負担を考慮したうえで運用体制や社宅規程を整備することが重要です。
➀社宅の運用形態を決定する
社有社宅と借上社宅のどちらを採用するか、自社のリソースを踏まえて運用形態を決定します。運用形態によって発生する費用や運用管理の業務などが異なります。
▼社有社宅と借上社宅の比較
社有社宅 | 借上社宅 | |
導入・運用費用 |
|
|
運用管理業務 |
|
|
社有社宅の場合、物件の購入または建設が必要になります。借上社宅よりも初期費用が高額になるほか、建物・設備の維持管理費用が発生するため、運用負担が大きくなる可能性があります。
借上社宅を選ぶと、物件の維持管理を管理会社に任せられるため、社宅担当者の業務負担を軽減できます。また、社宅を提供する目的や従業員の要望を踏まえて、エリア・物件を選べることから満足度も向上すると考えられます。
人事院がまとめた令和4年度の『民間企業の勤務条件制度等調査』によると、社宅制度がある企業のうち36.3%が社有社宅、80.7%が借上社宅を運用しています。
借上社宅のメリット・デメリットは、こちらの記事をご確認ください。
出典:人事院『民間企業の勤務条件制度等調査』
②社宅規程を作成する
社宅規程とは、社宅の使用料や入居者の条件、入退去の手続き方法などのルールをまとめた規程のことです。
社宅制度に関するルールが明確でない場合、従業員同士で不公平感が生じたり、認識の違いによってトラブルにつながったりする可能性があります。
社宅規程を作成しておくと、従業員とのトラブルを防いで運用管理を円滑に行えるようになります。
▼社宅規程の主な記載項目
項目 | 内容 |
入居資格 | 社宅に入居できる従業員の範囲・家族構成・年齢 など |
入居期間 | 社宅に入居できる期間の上限 |
物件の条件 | 物件の賃料や会社からの距離、間取りの制限 など |
入退去の手続き | 入退去の申込方法や提出書類、申請先の部署 など |
使用料 | 社宅使用料の金額(月額賃貸料の割合)や徴収方法 |
費用負担 | 社宅に関する費用の負担区分・割合 |
禁止事項 | 第三者への転貸、居室の増改築、ペット飼育 など |
退去事由・期限 | 規程違反や退職などによる退去の条件と退去期限 |
なお、社宅規程の作成例はこちらの記事で解説しています。
③運用体制・フローを構築する
社宅規程の作成が完了したら、担当部署と人員を選定して運用体制を構築します。
社宅の運用においては、入退去のタイミングだけでなく月次・年次でさまざまな業務が発生します。管理する戸数が増えるほど社宅担当者の負担につながるほか、運用フローが煩雑化して人的ミスや属人化が発生しやすくなります。
社宅担当者の負担をできる限り抑えるには、運用フローの標準化を図り、複数の人員で効率的に業務を行える体制をつくることが重要です。
▼運用体制・フローを構築する方法(例)
- 社宅関連業務を洗い出してフローを可視化する
- 業務マニュアルを作成してフローを標準化する
- 各業務の発生頻度や所要時間を踏まえて人員を選定する
- 社宅管理データを一元管理できるITツールを導入する
なお、社宅の運用管理に関する課題はこちらの記事で解説しています。
→【おすすめ!】借上げ社宅管理の業務改善方法とは?詳しく知りたい。
社宅制度の導入時に押さえておきたいポイント
社宅制度を導入する際は、従業員が利用しやすく公平性が保たれた制度設計を行うとともに、社内リソースを考慮して外部への委託を検討することがポイントです。
▼ポイント
- 会社負担となる費用項目・割合を明確にする
- 従業員のニーズや地域の特性を考慮する
- 社内担当部門での業務工数や対応時間を想定して社宅管理代行サービスを活用する
家賃に対して設定する社宅使用料の割合や、そのほか発生する諸費用の負担区分については、社宅規程に明記しておく必要があります。従業員負担となる費用を明確にしておくと、入居後や退去時のトラブルを防止できます。
また、満足度の高い社宅制度を目指すには、従業員の家族構成・職種の特性などを踏まえて入居資格や立地条件を設定したり、家賃上限をエリアの相場に合わせたりすることも欠かせません。
社宅の運用管理を行えるリソースの確保が難しい場合には、社宅管理代行サービスを活用して外部に委託することも一つの方法です。詳しくは、こちらの記事をご確認ください。
まとめ
この記事では、社宅制度について以下の内容を解説しました。
- 社宅の概要
- 住宅手当との違い
- 社宅制度の種類
- 社宅制度を導入する流れ
- 社宅制度の導入時に押さえておきたいポイント
社宅制度は、住居に関する経済的な負担を抑えられることから、従業員の満足度向上につなげられる福利厚生といえます。しかし、運用形態によって導入・運用にかかる費用や発生する業務などは異なります。
特に社有社宅では、会社が所有する不動産として維持管理を行う必要があるため、費用・労力面で負担が大きくなりやすいと考えられます。物件の維持管理にかかる負担を抑えつつ、会社の規模やニーズに柔軟に対応できるようにするには、借上社宅がおすすめです。
『リロケーション・ジャパン』の社宅管理サービスでは、包括転貸方式による借上社宅のフルアウトソーシングを行っております。通常の業務委託契約とは異なり、家主と個別の賃貸借契約を交わさず運用窓口を一本化できるため、契約トラブルのリスク回避と業務工数の削減に貢献します。
詳しくは、こちらの資料をご確認ください。





