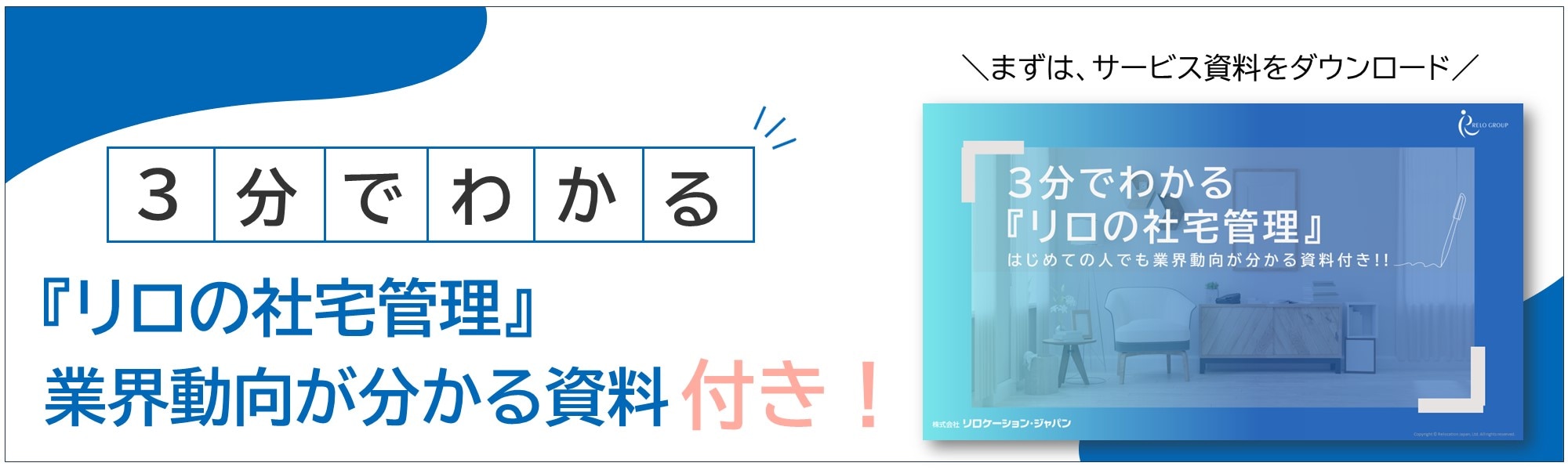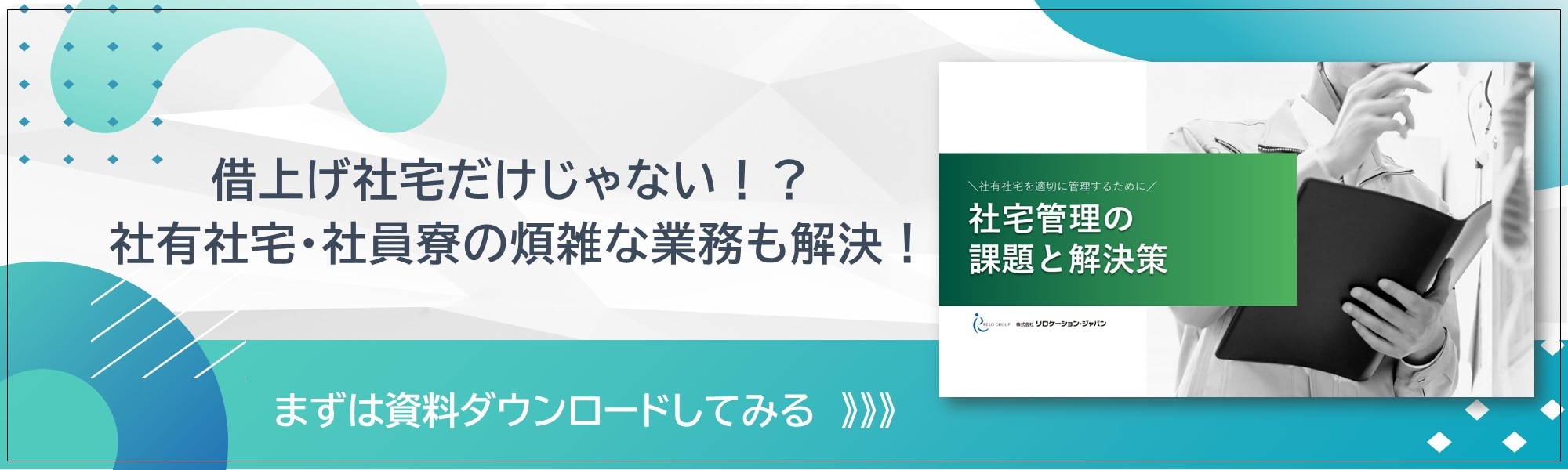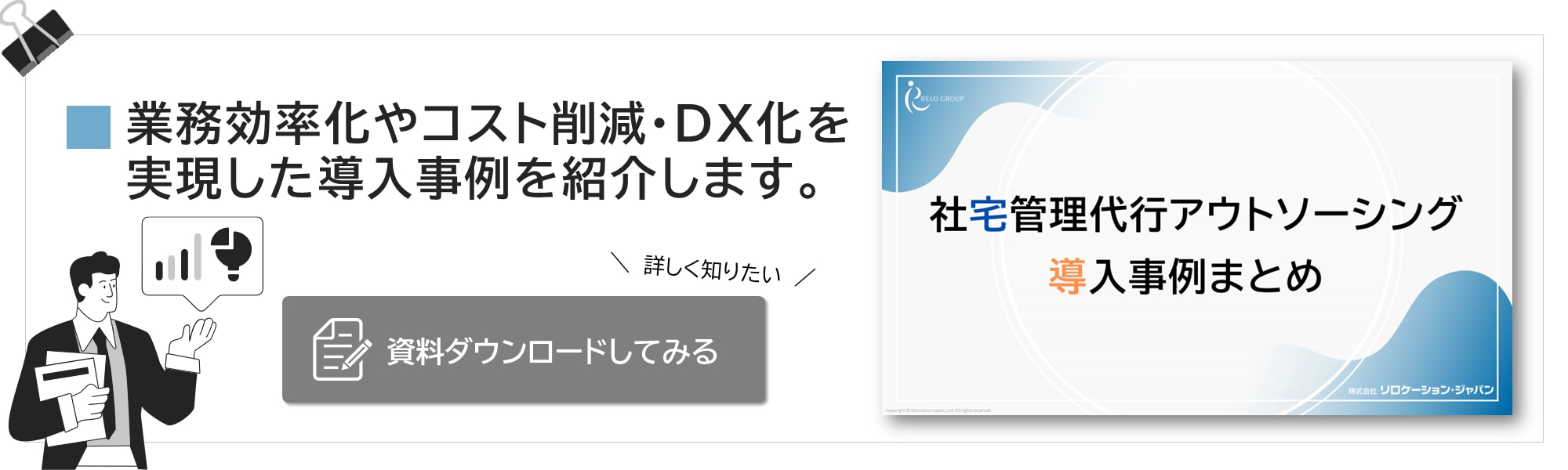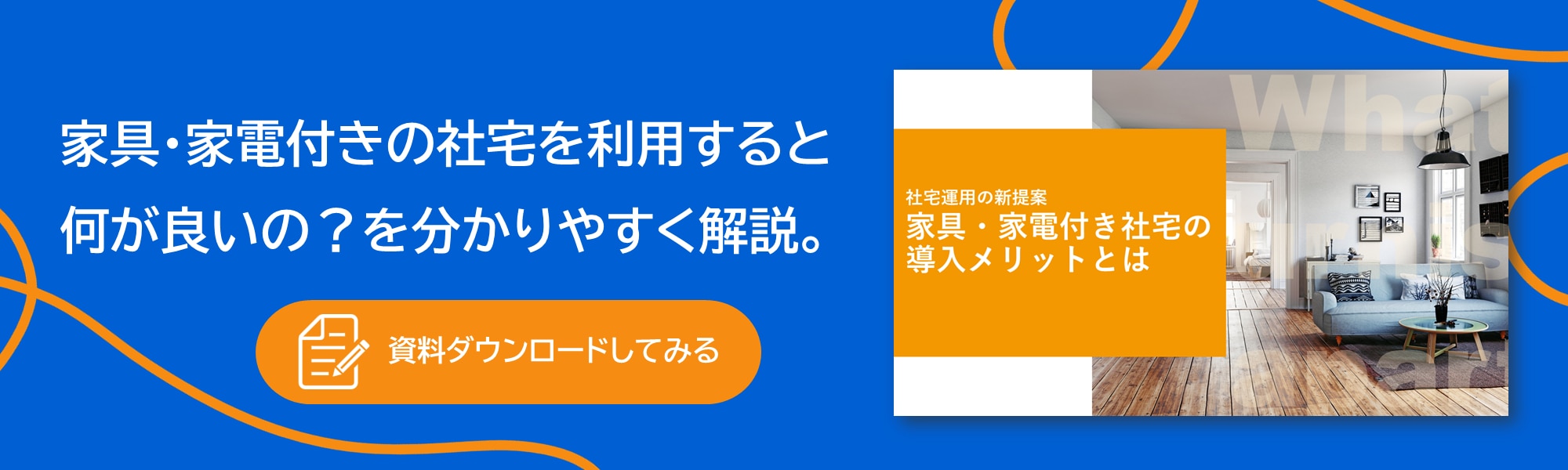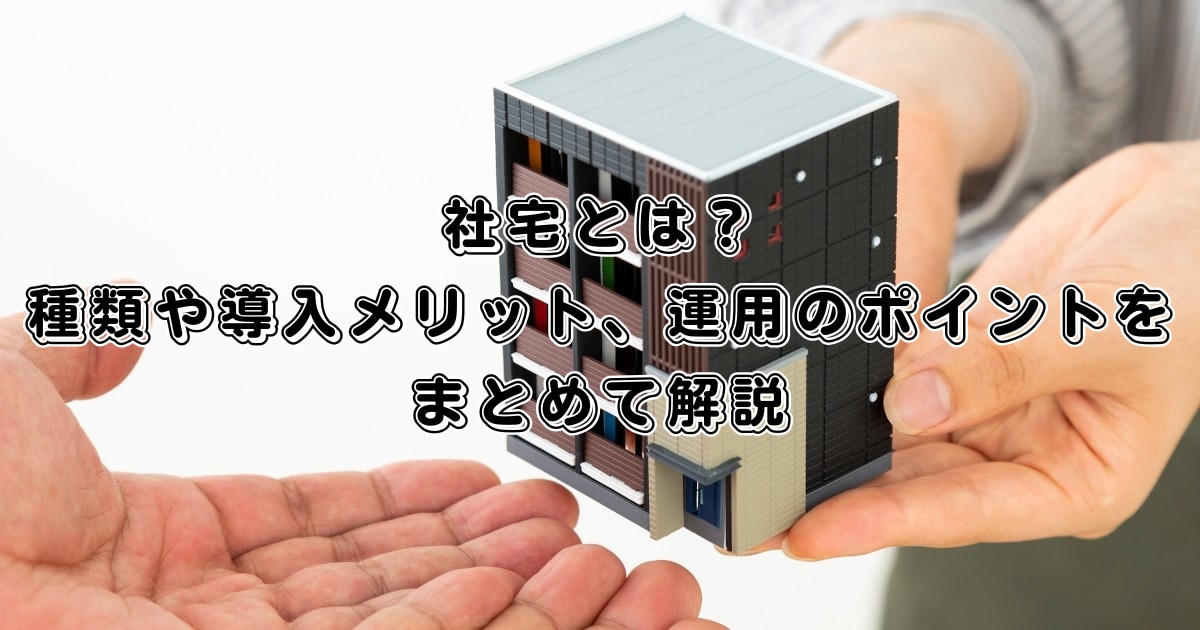
社宅とは? 種類や導入メリット、運用のポイントをまとめて解説
※2024年2月1日更新
社宅は、従業員の生活をサポートする福利厚生の一種です。家賃の支払いや入社・転勤に伴う引越しの負担を抑えられるため、従業員満足度の向上、優秀な人材の確保につながることが期待されます。
企業の人事総務部門のご担当者さまのなかには「社宅にはどのような種類があるのか」「従業員に喜ばれる社宅制度を運用するにはどうすればよいか」などと気になる方もいるのではないでしょうか。
この記事では、社宅の種類やメリット、運用のポイント、注意点などの基礎知識について解説します。
目次[非表示]
→面倒な社宅管理業務をまるっとお任せしたい。サービス概要資料はこちら!
社宅とは
社宅とは、企業が従業員のために提供する住居を指します。企業が従業員に住居を貸与して、従業員から家賃またはそれに相当する費用の全部あるいは一部を徴収することが一般的です。
住宅関連の福利厚生には“住宅手当”も挙げられますが、社宅とは運用や課税の仕組みが異なります。
▼社宅と住宅手当の違い
社宅 | 住宅手当 | |
運用方法 | 一定割合の使用料を従業員の給与から天引きして企業が差額を負担する | 一定額を給与に上乗せして家賃を補助する |
所得税の課税 | 従業員の自己負担割合によっては課税対象となる | 課税対象となる |
少子高齢化によって企業の人手不足が深刻化するなか、人材の確保と定着化を図るために、働きやすい魅力的な職場づくりを行うことが求められています。
住居に関する福利厚生は、金銭的な負担軽減に直結するほか、安定した生活基盤を整える支援となることから、従業員にも喜ばれやすいといえます。
社宅制度を導入して福利厚生を充実させることで、従業員満足度の向上や採用の促進につながり、人材の定着化にも結びつくと考えられます。
なお、福利厚生における社宅の位置づけや社宅制度の成り立ちについては、こちらの記事で解説しています。
社宅の種類
借上社宅は、賃貸物件を企業が借り上げて従業員に貸し出す方法です。法人名義で賃貸借契約を締結して、企業が管理会社またはオーナーへ家賃を支払います。家賃については企業と従業員の負担区分を決めて、一定の使用料を給与から天引きする仕組みとなります。
一方の社有社宅は、企業が所有するアパートやマンションのなどの一室を従業員に貸し出す方法です。従業員の給与から社宅の使用料を徴収します。
▼借上社宅と社有社宅の特徴
社宅の種類 | 特徴 |
借上社宅 |
|
社有社宅 |
|
社宅の種類については、こちらの記事で詳しく解説しています。
また、借上社宅の賃貸借契約書についてはこちらの記事をご覧ください。
→【おすすめ!】社宅だけじゃない!?社有社宅・寮管理の煩雑業務もまるっと解決!
社宅を導入するメリット
福利厚生として社宅制度を導入することで、企業と従業員の両方にさまざまなメリットが期待できます。
企業側のメリット
企業側のメリットには、以下が挙げられます。
▼メリット
- 企業イメージの向上
- 従業員満足度の向上
- 多様な人材の採用促進
社宅制度は、従業員の生活基盤を支える福利厚生となるため、従業員の住宅環境について考えている企業としてイメージが向上します。
住居にかかる金銭的な負担を抑えて手取り額が増えれば、生活のゆとりや仕事へのモチベーションが生まれて、従業員満足度の向上にもつながります。
また、社宅制度があると入社や転勤に伴う引越しの労力と費用の負担を抑えられることから、地方出身者、外国人労働者などの多様な人材の採用が促進されると期待できます。
従業員側のメリット
社宅に入居する従業員には、以下のメリットがあります。
▼従業員側のメリット
- 個人で賃貸借契約を結ぶよりも安く住める
- 住居を選定や契約、家賃の支払いなどの手続きが必要ない
社宅では、企業側で家賃の一部を負担するため、従業員が個人で賃貸借契約を結ぶよりも安い費用で住むことが可能です。
また、物件の選定や賃貸借契約、家賃の支払などに労力がかからなくなることから、仕事とプライベートに時間を充てやすくなります。
社有社宅や借上社宅のメリットについては、こちらの記事で解説しています。
→【詳しく知りたい!】『リロの社宅管理』を導入・利用企業様の事例はこちら
社宅を導入する際に必要な準備
企業が社宅を導入する際には、公平かつ円滑に制度を運用できるように事前準備を行うことが重要です。
社宅規程や使用誓約書を作成する
社宅を導入する際は、社宅規程や使用誓約書を作成しておくことが重要です。
社宅規程は、社宅の利用条件や入居・退去時の手続きなどのルールを定めた書面です。社宅を利用する際のルールを明文化しておくことで、従業員とのトラブルを防いでスムーズに社宅制度を運用できるようになります。
▼社宅規程で定める項目
- 社宅への入居資格(対象者)
- 入居期間
- 社宅の使用料
- 社宅に関する費用の負担区分
- 生活するうえでの規則
- 入居・退去時の手続き
- 社内規定を違反した場合の対応 など
また、使用誓約書は、社宅の入居にあたって従業員が遵守する事項を記載して誓約を求める書面を指します。社宅使用誓約書に盛り込む内容については、以下の記事で解説しています。
なお、社宅の入居条件を決める項目は、こちらの記事で解説しています。
費用負担の区分を明確にする
入居する従業員と企業との間で、各費用を誰がどれくらいの割合で支払うのかをあらかじめ決めておくことが必要です。
借上社宅の場合、月々の家賃のほかに入居時の初期費用や管理費・共益費などが発生します。また、社有社宅の場合には、建物・設備の維持管理費がかかります。
▼社宅の運用にかかる主な費用
なお、借上社宅の初期費用と光熱費の負担区分については、こちらの記事で解説しています。併せてご確認ください。
手続きやマナーに関するマニュアルを作成する
社宅を利用する従業員に手続きやマナーなどの情報を共有しておくと、スムーズな入居とトラブルの防止につながります。
▼マニュアルに盛り込む内容
- 住民票の異動に関する手続き
- 印鑑登録の変更
- 子どもがいる場合の手続き
- ペットの登録手続き
- マイナンバーカードや保険の住所変更
- 引越し挨拶のマナー
- 電気・ガス・水道の契約手続き
- 運転免許証や車庫証明 など
なお、引越しに伴う住民票の異動や住所変更の手続きについては、こちらの記事で解説しています。
社宅における引越し挨拶のマナーについてはこちらの記事をご覧ください。
従業員に喜ばれる社宅を運用するポイント
従業員に喜ばれる社宅を運用するには、快適で暮らしやすい環境を整備するとともに、スムーズな入居をサポートすることがポイントです。
①生活や通勤がしやすい物件を選ぶ
社宅にする物件を選定する際は、生活の利便性や通勤のしやすさなどを考慮する必要があります。物件の間取りや住宅設備、周辺環境などをチェックしておくことがポイントです。
▼社宅にする物件を選ぶポイント
ポイント | 選び方 |
間取り | 入居する人数やライフスタイルに合わせて使いやすい間取りを選ぶ |
住宅設備 | 生活で日常的に使う設備のほか、共用部の設備の利便性や防犯性も確認する |
通勤や買い物のしやすさ | 最寄り駅までの距離や会社までの通勤時間、周辺の施設状況を確認して生活がしやすい場所を選ぶ |
社宅にする賃貸物件の選び方については、こちらの記事で解説しています。
また、社宅の平均的な間取りについてはこちらの記事をご確認ください。
②家具・家電付きにする
家具・家電を企業側で用意すると、入居時にかかる初期費用を抑えられるほか、引越し後にスムーズに新生活を始められるため、従業員に喜ばれやすくなります。
▼家具・家電付きにする方法
- 会社が家具・家電を購入して、貸し出すまたは備え付ける
- 家具・家電のリースまたはレンタルを利用する
- 家具・家電付きの賃貸物件を選ぶ
家具家電付きの社宅については、こちらの記事で詳しく解説しています。
→【おすすめ!】記事とあわせて読みたい「家具・家電付き社宅の導入メリットとは」
③社有社宅のリフォーム・リノベーションを行う
社有社宅の場合は、老朽化した建物や設備のリフォーム・リノベーションを行うことも検討が必要です。
建物や設備が老朽化していたり、生活様式に合わない間取りになっていたりすると、入居者が住みにくさを感じることがあります。
間取りや設備、建具などを改修することで、快適に暮らしやすい環境となり、入居者の満足度向上や社宅の稼働率向上が期待できます。
なお、社有社宅のリフォーム・リノベーションについてはこちらの記事で詳しく解説しています。
社宅を導入する際の注意点
社宅を導入する際は、従業員が負担する費用や入居後の生活環境、社内での運用管理体制などに問題が生まれないように事前に対策をしておく必要があります。
入居時に原状回復費用の負担区分を説明しておく
借上社宅に入居する従業員に対して、原状回復費用の負担義務や負担区分について説明しておく必要があります。
国土交通省がまとめた『原状回復をめぐるトラブルとガイドライン』では、賃貸借契約の原状回復について以下のように定義しています。
▼原状回復の定義
賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること
引用元:国土交通省『「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」について』
経年劣化や契約により定められた使用方法に従って利用することで生じた傷、汚れに関しては、賃借人に原状回復費用の義務は発生しません。
一方で、入居者の故意・過失・不注意などで傷や汚れが生じた場合には、賃借人が退去する際に原状回復義務が生じます。社宅の運用においては、「原状回復費用が発生した際に企業と従業員のどちらが負担するのか」をめぐってトラブルが起こることも少なくありません。
原状回復費用の負担割合でトラブルが発生しないように、社宅規程で企業が負担する項目や割合を事前に明文化しておくことが重要です。
出典:国土交通省『「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」について』『「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」に関する参考資料』
防犯やプライバシーの対策が必要
従業員が安心して暮らせる社宅を提供するためには、防犯・防災・プライバシーについても対策を講じておく必要があります。
社宅がある場所や建物内の設備によっては、防犯面に不安が残るケースがあります。また、社宅で万が一の災害が発生した場合に備えて、避難の実施や二次被害を防ぐための準備をしておくことが重要です。
▼社宅における防犯・防災の対策例
対策例 | |
防犯 |
|
防災 |
|
なお、複数の従業員が同じ建物内で生活する社有社宅については、従業員同士のプライバシーにも配慮が求められます。一人ひとりが安心して生活できるように、プライバシーに関するルールを社宅規程で明文化することも対策の一つです。
社宅の防犯設備やプライバシー対策、防災については、以下の記事で詳しく解説しています。
社宅管理の業務負担につながる可能性がある
社宅の導入によって、社宅担当者の業務負担につながる可能性があります。
社宅の運用には、入居申し込みの受付や契約の手続き、使用料の徴収、入居者からの問い合わせ対応などさまざまな管理業務が発生します。社内のリソースに課題がある場合には、社宅管理を外部の事業者に委託することも一つの方法です。
社宅管理の業務を外部に委託することで、社宅担当者の負担が軽減されてコア業務に集中できるようになります。そのほか、入居者へのきめ細かなサポートによって従業員満足度の向上につながることも期待できます。
社宅管理を委託するメリットや委託方式の種類については、こちらの記事をご確認ください。
→お客様にいちばん選ばれている『リロの社宅管理』サービス概要資料はこちら
まとめ
この記事では、社宅の基礎知識について以下の内容を解説しました。
- 社宅の概要と種類
- 社宅を導入するメリット
- 社宅を導入する際に必要な準備
- 従業員に喜ばれる社宅を運用するポイント
- 社宅を導入する際の注意点
社宅は、従業員の安定した生活をサポートする福利厚生です。社宅を導入することで、企業イメージの向上や従業員満足度の向上、多様な人材の確保などのさまざまなメリットが期待できます。
公平かつ円滑に社宅制度を運用するには、社宅規程を作成してルールや費用負担を明文化するとともに、手続き・マナーに関するマニュアルを作成して共有しておくことが重要です。また、社宅を提供する際は、快適で暮らしやすい環境を整備するとともに、スムーズに入居ができるようにサポートすることもポイントです。
社宅の管理・運営にはリソースと専門的な知識が求められるため、外部への委託を視野に入れてみてはいかがでしょうか。国内マーケットシェアNo.1を誇る『リロケーション・ジャパン』の社宅管理サービスは、借上社宅のフルアウトソーシングや社有社宅の運用代行などに対応しています。社宅管理・運営の業務負担を軽減して、円滑な運用をサポートいたします。
詳しくは、こちらをご覧ください。